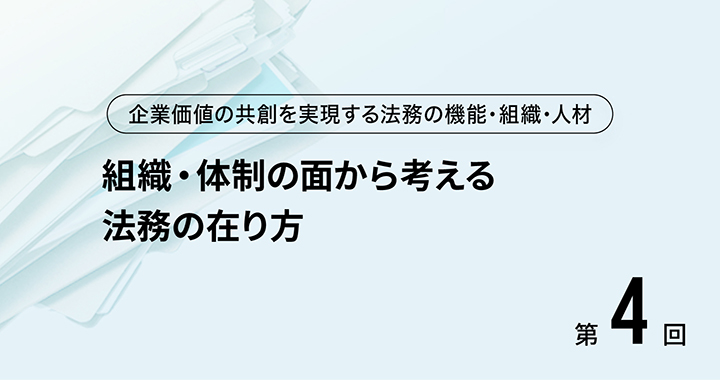
第4回:組織・体制の面から考える法務の在り方
執筆協力
- この記事について
-
企業において法務が担う役割については、従来の守りの法務機能とともに、攻めや戦略的な観点からの法務機能の強化が求められるようになってきました。
この特集では、改めて事業の推進に資する法務機能を考えるとともに、
✅ コーポレートガバナンス・グローバルグループガバナンスを実現する体制の整備
✅ 組織全体をコントロールする本社機能・法務機能の強化
✅ 組織を支える法務人材の育成・評価
など、成長を続ける企業において、企業価値の維持・創出を支える法務の1つの姿を提示することを目的としています。第4回は、国際的競争力の高い企業が持つ4つの特徴とはどのようなものか、過去の調査や事例を踏まえて深掘りし、組織・体制の面において法務機能や法務人材が目指すべき姿を明らかにしていきます。
目次
はじめに
本特集の第1回において、これからますます企業に求められる戦略的法務機能の発揮のための組織設計として、ビジネス機能の中に法務機能を作り、よりスピーディーに情報をキャッチする体制も効果的であるという一つの考え方を示しました。もちろん各企業の経営やビジネス形態が法務機能に求めるものはさまざまであり、法務機能の立ち位置をどうするかという組織・体制作りに画一的な正解があるものではありません。
経済産業省「国際競争力強化に向けた日本企業の法務機能の在り方研究会」が令和元年11月19日に公表した「国際競争力強化に向けた日本企業の法務機能の在り方研究会 報告書~令和時代に必要な法務機能・法務人材とは~」(以下、「令和報告書」という。2023年12月21日アクセス)は、法務機能とはクリエーション、ナビゲーター、ガーディアンの3つの機能を意味し、そのうちどれかが意識されていない、または備わっていないならば、その法務機能は不十分であると指摘しています(13頁)。
すなわち、これら3つの機能をタイムリーかつ有効に発揮できるような、経営やビジネスとの距離ないし距離感を解消し、これらに密着した組織・体制を取ることが日本企業の国際競争力強化につながっていくはずであることを示しています。
実際に、第1回において述べた通り、国際的競争力の高い企業の法務部門の4つの特徴を見てみると、まさにこの3つの機能を発揮するにふさわしい、目的志向性の強いハイレベルで能動的な組織・体制を有していることが分かります。
- 国際的競争力の高い企業の法務部門の4つの特徴
-
① 質・量ともに豊富な人材
② 意思決定プロセスへの関与を含むビジネスとの連携
③ 企業戦略の実現に資する守備範囲
④ グローバルな法務ガバナンスの計画的推進
そこで、今回は、これらの4つの特徴について、なぜ国際的競争力の高い企業がこのような特徴を持っているのかを考えてみたいと思います。
前提としての経営陣の法務に対する期待|法務部門がビジネスのPartner &Guardianであること
国際的競争力の高い企業が対峙している状況
国際的な競争に晒されている企業は、自らの企業価値の拡大と投資リターンの最大化を目的として、既存のマーケットはもちろん、時にはボーダレスに新たなマーケットにおける戦略的取り組みを日常的に進めています。
近年の日本企業もM&Aをその有力な事業ポートフォリオ構築ないし組み換えの手法として用いることが一般的になってきていますし、SDGsという新たな企業の社会的責任の在り方を踏まえたサステナブル経営の観点からも、従来とは異次元の、レベルの高い持続的なリーガルリスクマネジメントが必要になっています。このような状況の下では、企業として、経営における組織や人材のレベルも第一級の競合企業や取引の相手方、多様なステークホルダーと対峙しまた協調していく必要があり、法務機能などコーポレート機能もグローバルレベルのものを備えていなければ同じ土俵に立つこともかないません。
法務部門は新たなステージへ
そこで、国際的競争力の高い企業では、経営戦略に基づいたコーポレート機能の変革が加速しています。経営法友会の「会社法務部〔第12次〕実態調査の分析報告」(米田憲市編・経営法友会法務部門実態調査検討委員会著『会社法務部〔第12次〕実態調査の分析報告』〔商事法務、2022年〕。以下、「実態調査報告」という)においても、一定の規模を有する法務部門を中心に、「守り」から「攻め」に転じて、経営・事業部門のPartnerとして積極的に経営に参画しようという姿勢が顕著に表れており、伝統的な予防法務や臨床法務という観点よりも、いわゆる「GRC」と呼ばれるガバナンス・リスク・コンプライアンスの3つのキーワードを取り上げて、会社のGuardianが目指す姿であるとの回答が多数を占めています。
この変革のプロセスでは、法務部門も、その存在自体が従来の枠の中で自己目的化していないか、本当に企業全体の法務機能の最適化が実現できているのかを厳しく見直す必要があります。法務機能は、経営戦略や事業戦略を実現するためのものであり、法務部門の仕事を表す言葉ではないのです。
法務機能は、以下の3つに集約できます。
- 企業(ビジネス)を成功に導くために法的観点から貢献すること
- 企業をリーガルリスクや信用毀損リスク(reputation risk)から守ること
- リーガルリスクや信用毀損リスクが顕在化した場合に備え、その影響を最小化するためのシステムを構築・維持すること
今日では、事業環境の激変に対応してこれらを更に深掘りし、企業のステークホルダーが経営に、そして経営がコーポレート機能に対して何を期待しているかを常に意識しつつ、自らの組織の在り方や機能を適切に変革し、コンプライアンスを含む企業における法務機能の最適化を主導していくべき時に来ていると言えるでしょう。国際的競争力の高い日本企業は、まさにこのような変革の中にあり、4つの特徴にそれが色濃く表れ始めています。
4つの特徴①|人材
法務人材に求められるもの
ここで改めて言うまでもなく、法務部門の戦略は経営戦略や事業戦略に従い、部門の人材戦略もこれらに基づく組織の戦略に従います。企業における法務機能が果たすべき役割は、次の表に示したように、社外弁護士の役割とは大きく異なっており、明確な棲み分けを意識した組織・体制の在り方を構築した上で、必要な人材のスペックを考えるという流れになります。
| 法務部員(社内弁護士を含む) | 社外弁護士 | |
|---|---|---|
| 役割・責任・立場 | ・Professional Generalist ・Partner & Guardian ・企業としての意思決定や判断への貢献、最適解の提示 ・意見の留保、差し控え不可 | ・Specialist ・Coach & Advisor ・法的に完全な回答の提示 前提事実や条件に応じた意見の留保、差し控え可能 |
| 求められる能力・資質 | ・多分野に亘る幅広い専門知識 ・自社やビジネスに対する深い理解 ・広範なリスク認識能力とシナリオ想定力 ・マネジメント能力・リーダーシップ (最適解の選択、それへの誘導) ・ITリテラシー ・交渉力 ・英語力 | ・自らの専門分野における高度な知識・知見 ・高度なリサーチ力および分析力 ・精緻なロジック構成力、表現力 ・交渉力 (注:ITリテラシー、英語力も必要な場合が増えている。) |
令和報告書は、これからの法務機能を支える「経営法務人材」こそが、国際競争力強化に向けて今求められている企業法務部員のロールモデルであると位置付け、その基本的な資質、能力の要素や育成方法のフレームワークを示しました。
しかし、その一方で、現実において企業法務担当者がこの「経営法務人材」としての全ての要素を兼ね備えるのは、決して容易ではないとも率直に指摘しています。令和報告書は、経営法務人材を、上記のような能力等に加えて「企業内プロとして組織と専門性の二重コミットメントといった資質を備えた人材。経営と法務の専門性を兼ね備えた者」としています。
すなわち、法務の専門性や職業能力を基盤に、重層的、副次的な専門知識と経営センス(ここでは、取締役会やCEOなど、経営者の戦略、方針、思考経路や自社のパーパス、事業の在り方、将来像を適切に把握、理解、推察して先手を打てるという優秀人材としての特性〔コンピテンシー〕を意味し、経営能力そのものではありません)を獲得した、高度なプロフェッショナル・ゼネラリストこそが経営法務人材となります。
さらに、経営法務人材の中でも特に戦略分野に特化して経営や事業の中枢のひとりとして尖鋭的に貢献できる人材は、戦略法務人材と呼ぶべきです。
戦略法務人材の特性と育成
クリエーション、ナビゲーター、ガーディアンという3つの機能のバランスは経営が何を目指しているかによって決定すべきでありますが(令和報告書13頁)、このVUCAと言われる時代において、企業の経営戦略、事業戦略、知財戦略、商品戦略、地域戦略、広報戦略、スタートアップ戦略など、企業の各戦略分野に特化(密着)した法務に関する専門・プロ人材であり、よりスペシャリスト的な機能を期待される人材のニーズは今後ますます高まっていくことになると考えられます。
経営法務人材としての資質を備えた上で、通常の法務部員以上の、場合によっては営業部門の人間よりも、さらに戦略を主導するだけの事業分野や商品・地域に関する幅広くアップデートされた知見、多様なネットワーク、語学能力を駆使して、リーダーシップを発揮することが求められます。その優秀人材としての特性(コンピテンシー)は、基本的には経営人材と同様であるものの、知識・知見はより幅広く、またマインドセットは成果に向けてより尖鋭化されている必要があります。国際競争力の高い企業の経営が求める法務人材像は、まさにこのようなものであろうと考えられます。
さて、このような質の高い法務人材は突然現れるものではなく、若い頃からの長期的な育成が必要です。経営法務人材(そして戦略法務人材)は、プロフェッショナルを目指す企業法務担当者にとっての自己実現の一つの終着点であり、その頂点に立つのが経営陣の1人である最高法務責任者(Chief Legal Officer〔CLO〕ないしGeneral Counsel〔GC〕)です。
令和報告書に先立って平成30年4月に経済産業省より公表された「国際競争力強化に向けた日本企業の法務機能の在り方研究会 報告書」(以下、「平成報告書」という。1月10日アクセス)においては、日本と米国の企業におけるCLO・GCの設置率に有意な違いがあることも指摘されました。単純比較はできないものの、CLO・GCの米国企業における設置率がほぼ100%であるのに対して、日本企業の場合は23%にとどまっています(9頁)。
米国企業は法務部門を利益部門の一つと位置付け、相応のコストをかけて維持するとともに、GCやCLO、あるいはCCOという形で経営の中に法務機能・リーガルリテラシーを取り込み、経営陣との距離が近い専門集団によって経営を支えるという戦略的な組織構造となっていることがうかがわれます。
法務部門の長であることに留まらず、全社的に法務機能が適切に働いているか、課題がどこにあるかを経営の視点から総覧できる最高法務責任者の存在は、企業価値の創造の観点から必須であることはもちろんのこと、ステークホルダーに対する自社の事業の在り方やリスクマネジメント、社会的責任ないしサスティナビリティへの取り組み、危機対応などの説明責任を全うするという観点からも、ますます重要になっていくものと思われます。
一方、人材の量ももちろん大切です。実態調査報告では、法務部門に所属する人数が平均8.4名という結果になっています(25頁)。事業の内容や規模にもよりますが、一般論としては、やはり人数が絶対的に少なければ役割や機能を十分に果たせません。
自らの法務機能を最大化するために法務部門の人材ポートフォリオを質・量の両面から適切に整備することは、法務部門のマネジメントにとって最も重要なタスクの一つであると言えます。
4つの特徴②|ビジネスとの連携
企業の意思決定に法務機能のコミットを
企業の意思決定は取締役会から現場末端に至るまで、さまざまなレベルで日常的に行われていますが、そのプロセスに法務機能、法務リテラシーを組み込んでいくことは、組織・体制の設計においては極めて重要です。特に近年の企業を取り巻く事業環境は日々変化しており、多くの新たな経営課題やリスク要因が生じることで、企業の意思決定には難しさが増しています。
課題としては、組織上、事業の意思決定や実行と法務がリンクしていない場合が少なくないこと、法的リスクを十分な法的分析なく現場の判断で取れてしまう仕組みであったため、後々、企業が大きなインパクトを受けた例もあること、複合化するイシューやリスクに対しては、ビジネス・財務・税務・法務・労務等の各機能面からの総合的な判断が重要になるものの、社内のさまざまなファンクションやプロセスが断裂してしまっており、全体最適の統合的対応ができず、機能劣化や非効率化もあることなどが指摘されています(平成報告書27-28頁)。
これらはいずれも企業の意思決定を劣化させ、国際的競争力を殺ぐ重大な組織・体制的欠陥であり、ステークホルダーに対する合理的な説明も困難であるといっても過言ではありません。
平成報告書のキーワードであるPartner & Guardianを提唱した米国General ElectricのGCであったハイネマンは、自著“The Inside Counsel Revolution”(Jr. Heineman, Benjamin W., The Inside Counsel Revolution: Resolving the Partner-Guardian Tension (Amer Bar Assn, 2016). 邦題:『企業法務革命』)において、CEOは意思決定と業務執行に適切な者を関与させるとともに、GCを重要な意思決定に主体的に参画させるべきである、と喝破しています。
方法論は別として、企業の意思決定においては、法務機能を始めとするコーポレート機能が適切に働き、適法性・適切性ないし倫理性を組織的に担保することが求められます。後述するような守備範囲を拡大した法務部門がビジネスのエコシステムに制度的に参画し、日常的に情報収集するとともに、ビジネスの初期段階から案件形成に参画して、積極的かつ的確な提案を行ったり、場合によっては軌道修正をしたりするなど、適切に影響力を行使できる制度的な保障は、手遅れを回避しサステナブルな企業経営を実現していくにおいて必須であると言えましょう。
平成報告書では、法務部門が経営陣から意見・判断を求められる頻度、重要交渉への参加、法務部門の判断での重要案件の変更のいずれも、日本企業は米国企業に比べて圧倒的に低いという結果が指摘されています。米国企業の法務部門が経営・事業において重要な役割を担っていることがうかがわれるわけですが、国際的競争力を有する日本企業の場合には、こういった面でも米国企業の状況に近づいてきていると思われます。
しかし、近年の米国企業の法務部門はその先を行っており、いわゆるリーガルオペレーションズといわれる一連の業務改革の動きとして、専門性を集中すべき戦略的な分野と、それ以外の分野を明確に分離し、非弁護士の、例えばマネジメント支援・DX・HR等の専門家をチームに加えて仕事の効率を高めたり、生成AIの活用によって情報収集を効率化したりするなど、チームのプラクティスマネジメントを高度化するということも行われています。
令和報告書は、法務機能の実装ということについて、General Electricに象徴される米国流の革命(大幅な人材の入れ換えを伴うトップダウン型の実装)とは対極に立つ日本企業の漸進的な改革(ボトムアップ型の実装)を肯定しつつ、日本企業の法務部門としてもさらに情報収集体制や業務基盤の整備を加速するように促しています。
法務部門の初期からの関与・分権化などの新たな取り組み
一方で、明るい兆候もあります。実態調査報告では、重要案件(重要な企画・事業計画等のプロジェクトおよびM&A・協業等の重要な契約)への対応や、コーポレートガバナンスや内部統制への関与、危機対応、社内意思決定への企画・提案なども法務部門の役割としての認知度が高まっています。さらに、重要案件について法務部門がどのように関与しているかという質問に対しては、検討・企画段階や、中盤、契約交渉過程等から関与しているところが過半数を超えています(相談があった場合のみ対応は2割強)。ビジネスとの連携が深まっているとともに、従来の受け身の姿勢に大きな変化が起きていることが分かります。
法務機能は法務部門だけのものではありません。ビジネスのエコシステムそのものに法務機能が組み込まれており、個々の意思決定においてこれが自律的に働くという組織・制度の在り方が望ましいとするならば、法務機能があたかも神経系統のように存在する状態、すなわち法務担当者が現場にいること、本社法務部門に要員が集中するのではなく分権化を推進するということも今後さらに検討の視野に入ってくるものと考えられます。
この点、実態調査報告では、資本金の大きい企業の約2割が事業所単位に法務担当者を配置しており、国際競争力の高い大手企業などのメガクラス法務部門(31名以上)では51%が法務担当者を分散配置していると回答しており(15頁)、社内各所において法務機能を発揮しているものと推測できますが、その位置付けや役割といった在り方については引き続き検証が必要であると考えます。
4つの特徴③|守備範囲
従来型法務機能の3つの柱
法務部門の職責を端的にPartner & Guardianと表現した場合、その範囲は非常に広くなることが想定されます。従来、法務は、その機能の切り口から臨床法務、戦略法務、予防法務という3つの柱で説明されてきました。
臨床法務とは、企業が事業活動の過程で巻き込まれる法的紛争による損失やコストを最小限に抑えていく機能です。グローバル化に伴って巨額化、多様化、複雑化する紛争や危機の企業に対する定性的、定量的インパクト(信用の毀損、損害賠償や罰金など金銭的な損失)を軽減することが求められます。
戦略法務とは何かについてはいろいろな考え方がありますが、一般的には、企業を取り巻く法的ルール(法律、政府規制、契約)の枠組みの中で、これらを駆使しながら、事業活動遂行のための有用な戦略や戦術を検討、立案し、案件を安定的、持続的に成功に導く機能を指すことが多いと思います。高度かつ複雑な案件の法律構成、契約スキーム策定および関係契約書案の作成・検討などを通じて、高度化、高速化する取引の構造的リスクを回避し、企業が目論む取引の安全性・収益性・効率性確保に寄与することが求められます。
予防法務とは、損失、紛争、危機の発生を未然に回避するためのさまざまな制度や手段を事業活動の中に織り込んで行く機能です。企業にとっての経営課題である紛争・コンプライアンス・欠陥契約のリスクや、顕在化したリスクのインパクトを極小化することが求められます。
事後・臨床的法務から事前・能動的法務へ
従来型の法務部門は、社外弁護士と同様、特定の問題が起きた場合に、その担当部署の依頼や相談、あるいは経営陣からのトップダウンの命令を受けて対応するという、事後的で臨床的な対応がその主要な機能であったと言えます。このような法務部であれば、組織的にも大規模である必要はなく、費用対効果の面でも、一見、優位性があるように思われます。
しかし、社会の法化や企業活動のグローバル化が進み、VUCAの時代と言われビジネスが飛躍的に高度化、複雑化し、リスクインパクトが大きくなった現在、事後対応では結局のところ、時間・労力・コストが余計にかかり、機会損失にも繋がりかねないということが広く認識され、従来の受動的、伝統的な臨床法務から、能動的な予防法務や戦略法務こそが現代の企業法務の本丸であるという考え方が、実務界では一般的になっています。
もっとも、これらを固定的、硬直的に捉えるのは適切ではなく、いずれも不可欠な機能であり、これらはリーガルリスクマネジメント機能という上位概念で包括的に捉え、分野や事象によって複合的に発揮されるべきものでしょう。平成報告書も指摘するように(3頁)、法務を「業務」の切り口から見ると、法務関連業務の守備範囲は従来の契約審査、法律相談、訴訟対応等を超えて拡大し続けています。
例えばESG・経済安全保障対応などのリーガルリスクマネジメントやレピュテーションリスクマネジメントといった経営課題に繋がる分野において、主体的に、または他の部門と連携しながら、関係する社内の委員会等に参画するなどにより、プレゼンスを示し、リーダーシップを発揮している法務部門も増えています。
ところで、法務部門がどのような機能を担うべきかについては、各社が各社の事情に応じて個別具体的に考えるべきことだろうという見解があります。しかし、経営に対して法務の専門性から貢献するPartner&Guardianというミッションを踏まえれば、法務部門の果たすべき機能は自ずと決まってくるものであり、そのトップたるCLOやGCの職責も同様です。
法務マターであれば、法務部門がそのすべてを担うか否かは別として、企業グループ全体の法務マターの隅々に目が届き、主要なイシューやリスクを理解しており、その対応やリスクマネジメントができていて、かつこれらの状況について内外に適切に報告・説明できるような、経営法務人材である最高法務責任者が必要であることは論をまちません。国際的競争力の高い企業はまさにこういった考え方を取っているところも多いものと思われます。
4つの特徴④|グローバルな法務ガバナンス
海外事業の拡大とグローバルな法務の課題
国際協力銀行の「わが国製造業企業の海外事業展開に関する調査報告ー2023年度 海外直接投資アンケート結果(第35回)」(2023年12月21日アクセス)によれば、わが国の製造業の海外売上高比率は昨年度に続き上昇傾向にあり、コロナ直前の水準を上回る39.0%となったと報告されており、引き続き高い水準で推移するものと見込まれています。
アジアや米州を中心に回答企業の多くが生産や販売の現地法人を設立しており、海外事業を中期的に拡大・強化するという回答も約4割に上っています。一方で、海外のグループ企業において、粉飾決算や資産の横領など不祥事、事業活動における不正、贈収賄・汚職、サイバー犯罪などが相変わらず発生しており、国際的競争力の高い企業の法務部門では、これらの予防や対応に注力しています。
具体的には、CLOやGCなど日本の本社法務の最高責任者が、海外を含むグループ会社のCLOやGC等の法務責任者を通じて連携し、グループ会社の状況を把握する体制を取るとともに、コンプライアンス体制の強化を促しているところも少なくありません。しかし、そのやり方についてはさまざまな方策が考えられるとともに、現地法人と異なりM&Aで買収した現地企業についてはなかなか一筋縄ではいかない部分があります。
グローバル企業の法務人材ローテーションの例
ある米国企業の例を見てみましょう。G社とU社は、いずれもM&Aによって多くの事業子会社を抱えていましたが、法務部門の人材ローテーションには違いがありました。
G社は子会社をあたかも支店のように扱っており、本社GCが子会社GCの人事権も握っていました。子会社GCが本社GCや幹部に異動することや、優秀な部下を本社法務部門に引き上げることもあり、少なくとも幹部クラスは一つの人材プールで動いていました。
一方、U社の場合は事業子会社の独立性が非常に強く、子会社GCと本社GCはdotted line(直属でない弱い関係)でしかつながっておらず、子会社GCの人事権もない状態でした。子会社と本社との間の人材ローテーションはなく、人材が囲い込まれている状態です。これはG社(同化重視)とU社(自律性尊重)の子会社管理手法の違いが大きく影響していると思われます。
日本企業の場合にはこのU社のような状況にあることが多いのではないかと思われますが、そうであったとしても、少なくとも重要な情報は収集できるようにdotted line(報告の必要な関係)の存在を明確にするがあります。可能であれば、グループ会社の取締役会等を実際に機能するものに整備し、ここに本社からコーポレート要員を派遣して現場でのガバナンスを効かせるとともに、いつ、誰に対して、どのような報告をするかについて、明快で効率的な報告ルールを策定し、グループ全体で運用するなど、管理の仕組みを制度的に構築することが望ましいと考えられます。
その上でdotted lineの強度を高めていくことになりますが、子会社の経営陣からは時に反発を受けたり、非協力的な姿勢が取られたりするようなこともあるかもしれません。しかし、本社法務最高責任者や担当者と子会社の法務責任者や担当者の間では、同じ職能を持った人間同士として、グループや自社の法務機能を強化し、ともにサステナブルな発展を志向するという共通の目的を持ちやすいというメリットもあります。
両者間のコミュニケーションを密にし、将来的にはあたかも一つの法律事務所のようにグループ全体の法務部門が連携し、グループ全体の法務機能の水準をグローバル水準に引き上げるべく、本社法務の強力なリーダーシップが期待されるところです。国際的競争力の高い企業では、グローバルな法務ガバナンスという一つの大きな経営課題の一環として、まさにこのような営みが日々行われているのです。
おわりに
以上のとおり、国際的競争力の高い企業では、戦略法務と、オペレーション法務(本連載第1回参照)のいずれにおいても機能を最大限発揮できる組織・体制を志向しています。中小企業であっても国際的競争力が求められるならば、リソースが許す限り、上記の4つの特徴を備えた法務機能のための組織・体制作りに経営課題として取り組んでいく必要があると考えられます。







