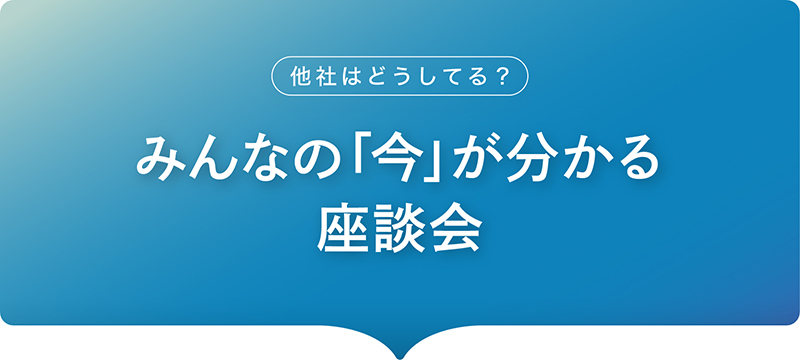完全合意条項とは?
定義や定めた場合のリスク、
日本法における例文などを分かりやすく解説!
- この記事のまとめ
-
「完全合意条項」とは、契約当事者間の合意内容を、契約書に書いてある内容だけに限定する条項です。英米法のEntire Agreement Clauseをルーツとしており、最近では日本における企業間取引の契約書にもよく見られます。
完全合意条項を定める場合、合意内容を契約書に全て書き込まなければなりません。そのため、通常の契約書よりもいっそう慎重なレビューが求められる点に注意が必要です。
今回は完全合意条項について、基本から分かりやすく解説します。
※この記事は、2022年10月20日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。
目次
完全合意条項とは
「完全合意条項」とは、契約当事者間の合意内容を、契約書に書いてある内容だけに限定する条項です。英米法のEntire Agreement Clauseをルーツとしており、最近では日本における企業間取引の契約書にもよく見られます。
完全合意条項の法的効果
完全合意条項を定めた場合、合意内容は、契約書に明記された内容に限定されます。
契約交渉の段階で、当事者が口頭で何らかの合意をするケースはよくあります。例えば、
といった具合です。
しかし、最終的に締結した契約で完全合意条項が定められた場合、上記のような口頭での合意は全て無効となります。完全合意条項により、契約書に書かれたことだけが契約内容となるからです。
また、正式な契約を締結する前の段階で、議事録や覚書などによって書面合意をする例も見られます。取引条件を段階的に決めていく契約などでは、よく用いられる手法です。
この場合も、最終契約において完全合意条項が定められた場合、先行する書面合意は全て無効となり、最終の契約書に書かれたことだけが契約内容となります。
完全合意条項の由来|口頭証拠排除の原則(Parol Evidence Rule)
完全合意条項は、もともと英米の契約書で実務上定められていたのが、日本にも導入されたものです。
英米の契約書において完全合意条項(Entire Agreement Clause)が定められることが多いのは、「口頭証拠排除の原則(Parol Evidence Rule)」があるためと考えられます。
- 口頭証拠排除の原則(Parol Evidence Rule)とは
-
口頭証拠排除の原則とは、当事者が最終的に契約書を締結した場合、契約書作成以前に、
・契約書と矛盾する内容
・契約書を変更する内容
があったとしても、裁判所は考慮しないという原則です。例えば、口頭やメールによる合意で、契約書の内容と矛盾するものは排除されることになります。
英米では、慣習法の考え方が採用されています。
慣習法の下では、契約自由の原則が強く働き、法律よりも当事者の合意内容が尊重される傾向にあります。
ただし、不明確な合意を認めてしまうと紛争の複雑化につながります。そのため、口頭証拠排除の原則によって、裁判で認められる証拠が限定されているのです。英米法における完全合意条項は、口頭証拠排除の原則を明文化したものです。
一方、1990年代以降、日本でも企業間の契約実務が発展し、かつ英米圏との取引が増えたことに伴い、日本法準拠の契約においても完全合意条項がよく見られるようになりました。
ただし日本法では、英米法とは異なり、口頭証拠排除の原則が明示的に採用されているわけではありません。つまり日本の裁判所は、口頭やメールなどでの合意を証拠として認め、契約内容を修正することがあり得るのです。
完全合意条項を定める目的
完全合意条項を定める目的は、主に以下の2点です。
契約解釈に関するトラブルを未然に防ぐため
完全合意条項により、契約内容が契約書に書いてある事項だけに限定されます。
つまり、契約内容を把握するに当たり、当事者が何を考えて契約を締結したか、今までの慣行はどうだったかといった事情を考慮する必要がなく、契約書の文言だけに集中すればよくなるのです。
契約の解釈を巡っては、当事者間でトラブルになることがよくあります。契約解釈を巡るトラブルは多くの場合、契約書に書いていない事情に関して、当事者の間で認識や理解の食い違いがあることに起因しています。
完全合意条項を定めておけば、契約書の文言以外の事情を根拠にして、契約解釈を争うことができなくなります。つまり、契約解釈に関するトラブルの原因そのものを、最初から摘んでおけるのです。
このように完全合意条項には、契約解釈に関するトラブルを未然に防ぐ効果があると考えられます。
トラブル発生時の明確な解決基準を設けるため
完全合意条項は、契約に関するトラブルが実際に発生してしまった場合にも効果を発揮します。トラブルを解決するに当たり、参照すべき基準が契約書のみとなり、明確化されるからです。
また、訴訟に発展した場合でも、完全合意条項が明記された契約書を裁判所に提出すれば、契約書以外の事情が考慮されなくなります。その結果、審理の長期化を防ぐことにつながるでしょう。
また、当事者にとっても訴訟の結果が予測しやすくなるため、自発的な和解を促す効果も期待できます。
このように、完全合意条項によって参照すべき基準を契約書一つに絞ることで、紛争をスムーズに解決できる可能性が高まると考えられます。
完全合意条項を定めるリスク
なお、完全合意条項を定めることにはリスクもあります。
例えば、
などに、完全合意条項を契約書に定めてしまうと、予想外の損失を招く可能があります。
また、一般的に、完全合意条項を定める場合、リスクマネジメントの観点から、通常の契約書よりも膨大な分量になりがちです。分量が多くなればなるほど、契約審査にかかる時間・手間も多くなるため、完全合意条項を定めるべきかどうかは、慎重に判断すべきです。
完全合意条項が定められる契約の例
完全合意条項は、企業間取引に関する契約において幅広く見られます。その中でも、完全合意条項が定められることの多い契約の種類をいくつか紹介します。
完全合意条項の例文(条文例)
完全合意条項の例文を紹介します。
- 例文
-
本契約は、本契約の主題事項に関する当事者間の完全な合意を構成するものであり、書面によるか口頭によるかを問わず、かかる主題事項に関する当事者間または当事者のうち一部の者の間で本契約締結前になされた合意および取り決めは全て効力を有しないものとする。
「本契約の主題事項」とは、契約によって予定されている取引のことです。完全合意条項が、当該取引に関連する事項全般に適用されることを明らかにしています。
「完全な合意」の意味は、例文の後半で具体的に示されています。
つまり、
ということです。
単に「完全な合意」と記しただけでは、どのような効果を持つ条項であるのか不明確になってしまいます。そのため上記のように、具体的にどのような効果があるのかを明記しておくことが大切です。
特に日本法準拠の契約における完全合意条項は、英米と異なり単に法律の原則を明文化したものではありません。完全合意条項を置くことではじめて、契約書以外の合意を排除する効果を生じさせることができます。
そのため、完全合意条項の具体的な効果を、必ず条文中に明記しておきましょう。
完全合意条項を定める際の注意点
完全合意条項を定める場合、契約書の中で何をどのように定めるかがいっそう重要となります。完全合意条項のある契約をレビューする際には、特に以下のポイントに留意して確認を行いましょう。
定めるべき事項が網羅されていることを確認する
完全合意条項が定められた場合、契約書に書かれていない内容は契約に含まれません。つまり、解釈や慣行などによって契約内容を補充することはできないので、書くべきことは漏らさず書いておく必要があります。
完全合意条項を定めた契約書は、膨大な分量になるケースが多いです。これは、常識的な内容でも細かく記載することで、定めるべき事項に漏れを生じさせないようにするためです。
不明確な文言がないことを確認する
完全合意条項が定められた契約書は、紛争が発生した際の重要な解決基準となります。それなのに、契約書の中に不明確な文言が含まれていると、紛争解決基準として十分に機能しません。
完全合意条項が定められていない契約書であれば、不明確な部分を交渉段階のやり取りや実務慣行などにより、意味を補充して解釈することも可能です。
これに対して、完全合意条項が定められている場合は、交渉段階での事前合意などがあったとしても、その内容は契約解釈に当たって考慮できません。したがって、不明確な部分については基本的に、法令のルールが適用されることになります。その結果、当事者が予期せぬ形で契約内容が修正されてしまう事態になりかねません。
完全合意条項が無効となるケースもある
契約書に完全合意条項を定めたとしても、常に有効と認められるとは限りません。当事者の属性や契約の内容によっては、完全合意条項の有効性が否定される可能性もあります。
例えば東京地裁平成7年12月13日判決の事案では、株式売買契約について、契約書に記載のない買戻特約の存否が争われました。株式売買契約には完全合意条項が定められていたところ、東京地裁は次のように判示して、完全合意条項の有効性を認めました。
上記判示を裏から解釈すれば、契約実務についての経験や、契約内容を理解する能力が不十分な当事者によって締結された契約の完全合意条項は、その効力が制限され得ると読み取れます。
また、具体的な取引条件について十分な規定が置かれていないにもかかわらず、完全合意条項が定められている場合は、かえって契約内容が不明確となってしまいます。このような場合にも、完全合意条項が無効と判断される可能性があります。
この記事のまとめ
完全合意条項の記事は以上です。最新の記事に関する情報は、契約ウォッチのメルマガで配信しています。ぜひ、メルマガにご登録ください!
参考文献
喜多村勝德著『契約の法務 第2版 [勁草法律実務シリーズ]』勁草書房、2019年
滝川宜信著『リーダーを目指す人のための実践企業法務入門〔全訂版〕』民事法研究会、2018年