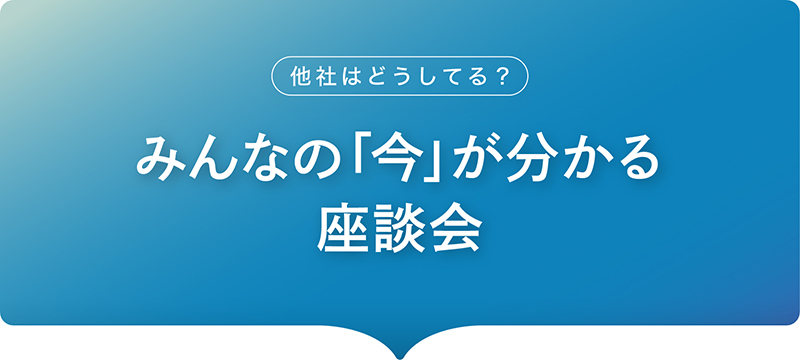反訴とは?
本訴との関係・要件・メリット・デメリット・
手続き・注意点などを分かりやすく解説!
- この記事のまとめ
-
「反訴」とは、訴訟の被告(訴えられた側)が原告(訴えた側)に対して、同じ手続きの中で訴訟を提起し返すことをいいます。
本訴の目的である請求または防御の方法と関連する請求については、口頭弁論の終結前に限り、本訴と同一の裁判所に反訴を提起することができます。反訴のメリットは、双方の請求が1つの手続きで審理されるため、負担の軽減や矛盾解決の防止につながる点です。別々に訴訟を提起する場合と比べて、訴訟費用が安くなることもあります。
その一方で、被告側の請求についても訴訟費用の負担が生じるほか、審理の対象が増えることによって訴訟が長引く傾向にあるのが、反訴のデメリットといえます。反訴の提起は、裁判所に反訴状などを提出して行います。反訴は本訴と併合した上で審理され、本訴と同様に判決が言い渡されます。
この記事では反訴について、要件・メリット・デメリット・手続き・注意点などを解説します。
※この記事は、2024年10月21日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。
目次
反訴とは
「反訴」とは、訴訟の被告(訴えられた側)が原告(訴えた側)に対して、同じ手続きの中で訴訟を提起し返すことをいいます。
民事訴訟とは
「民事訴訟」とは、権利義務に関する紛争(争い)を解決するための裁判手続きです。
訴訟を提起する側を「原告」、その相手方を「被告」といいます。原告と被告は、裁判所の公開法廷において主張と立証を行い、裁判所がどちらの主張を認めるべきか判断します。
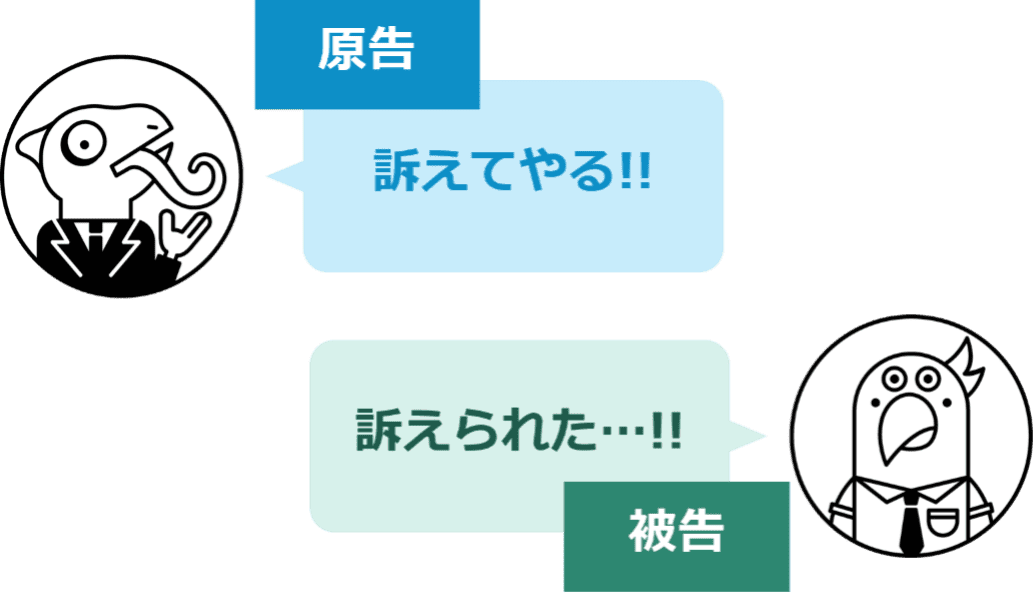
最終的に裁判所は、原告の請求を認めるかどうかを示す判決を言い渡します。判決が確定すると、当事者はその内容を遵守しなければなりません。判決に従わない場合は、強制執行によって財産を失う可能性があります。
本訴と反訴
民事訴訟の被告は、同じ手続きの中で、原告に対して訴訟を提起し返すことが認められています。これを「反訴」といいます。
反訴が提起される場合、元々裁判所に係属していた訴訟を「本訴」といいます。本訴と反訴は、同じ訴訟手続きの中で審理されることになります。
反訴を提起するための要件
民事訴訟の被告が反訴を提起するためには、以下の要件を全て満たしていることが必要です。
1|反訴の請求と、本訴の請求または防御の方法の間に関連性があること
2|口頭弁論の終結前であること
3|本訴の係属する裁判所に対して反訴を提起すること
4|反訴の請求が、他の裁判所の専属管轄に属していないこと
5|反訴の提起により、著しく訴訟手続きを遅滞させることにならないこと
1|反訴の請求と、本訴の請求または防御の方法の間に関連性があること
反訴を目的とする請求は、本訴の請求または防御の方法と関連していなければなりません(民事訴訟法146条1項本文)。
<OK例>
契約違反を理由とする損害賠償請求訴訟を提起された被告が、同じ契約に関する原告の契約違反を理由に、損害賠償を請求する反訴を提起した。
<NG例>
契約違反を理由とする損害賠償請求訴訟を提起された被告が、その契約とは全く関係がない場面でのパワハラを理由に、損害賠償を請求する反訴を提起した。
反訴を認める目的は、本訴と反訴を同じ手続きで審理し、訴訟資料を共通して利用できるようにすることで、審理を効率化する点にあります。
反訴の請求と、本訴の請求または防御の方法の間に全く関連性がない場合は、訴訟資料の共通利用による審理の効率化が期待できないため、反訴の請求が却下されてしまいます。
2|口頭弁論の終結前であること
すでに口頭弁論が終結している場合には、反訴を提起することができません(民事訴訟法146条1項本文)。本訴の審理が終了しているのに反訴の提起を認めると、訴訟手続きを遅滞させることになるからです。
なお、第一審の口頭弁論が終結した後でも、控訴を提起した上で控訴審において反訴を提起することはできます。
ただし後述するように、控訴審における反訴の提起には相手方の同意が必要です。反訴は特段の事情がない限り、第一審の口頭弁論が終結する前に提起しましょう。
3|本訴の係属する裁判所に対して反訴を提起すること
反訴を提起できるのは、本訴の係属する裁判所です(民事訴訟法146条1項本文)。
反訴は本訴と同じ訴訟手続きによって審理されるので、本訴が係属中の裁判所以外の裁判所に提起することは認められません。
ただし後述するように、簡易裁判所において地方裁判所の管轄に属する反訴請求がなされた場合には、簡易裁判所から地方裁判所に移送されることがあります。
4|反訴の請求が、他の裁判所の専属管轄に属していないこと
本訴の係属する裁判所以外の裁判所の専属管轄に属する請求については、反訴を提起することができません(民事訴訟法146条1項1号)。このような請求を行う場合は、専属管轄を有する裁判所に別の訴訟を提起する必要があります。
ただし例外的に、特許権・実用新案権・回路配置利用権・プログラムの著作物についての著作者の権利に関する請求の訴えについて、民事訴訟法6条1項の規定に基づき東京地方裁判所または大阪地方裁判所が専属管轄を有する場合には、当該請求について反訴を提起することが認められています(民事訴訟法146条2項)。
5|反訴の提起により、著しく訴訟手続きを遅滞させることにならないこと
反訴の提起により、著しく訴訟手続きを遅滞させることとなるときは、反訴が却下されます(民事訴訟法146条1項2号)。併合審理によって迅速化・効率化を図るという反訴の趣旨にそぐわないためです。
なお、著しく訴訟手続きを遅滞させるものとして反訴が却下された場合でも、別の訴訟によって改めて請求を行うことはできます。
反訴のメリット
反訴には、主に以下の2つのメリットがあります。
① 双方の請求が1つの手続きで審理される|審理の効率化・負担軽減・矛盾解決の防止
② 別の訴訟を提起するよりも、訴訟費用が安くなることがある
双方の請求が1つの手続きで審理される|審理の効率化・負担軽減・矛盾解決の防止
反訴が提起されると、本訴と反訴は同じ訴訟手続きの中で審理されます。
本訴の請求または防御の方法と反訴の請求は関連しているため、訴訟資料を共通利用することにより、審理の効率化が期待できます。
当事者にとっても、本訴と反訴が1つの訴訟手続きで審理されれば、2つの訴訟を争う場合に比べて負担軽減につながります。
さらに、本訴と反訴が併合審理された場合は、それぞれの判決も同じ裁判所が言い渡します。
別々の訴訟手続きで審理されると、2つの判決が互いに矛盾するおそれが懸念されますが、本訴と反訴が併合審理されていれば矛盾した判決が示されることもありません。
別の訴訟を提起するよりも、訴訟費用が安くなることがある
本訴の目的と反訴の目的が共通している場合、被告が納付すべき訴訟費用は、反訴請求の手数料額から本訴請求の手数料額を控除した残額で足ります。
例えば、原告が100万円の貸金返還債務不存在確認訴訟を提起したのに対して、被告が同じ貸金について200万円の返還を請求する反訴を提起したとします。
この場合、本訴の目的と反訴の目的は同じ貸金返還請求権なので、被告が納めるべき反訴の訴訟費用は、別に貸金返還請求訴訟を提起する場合よりも安くなります。
反訴のデメリット
反訴のデメリットとしては、主に以下の2点が挙げられます。
① 被告側にも費用負担が発生する
② 訴訟が長引く傾向にある
被告側にも費用負担が発生する
反訴を提起する際には、被告側も反訴の訴訟物の価額に対応する訴訟費用を支払う必要があります。また、連絡用の郵便切手も裁判所に納付しなければなりません。
別に訴訟を提起する場合に比べると安くなるケースもありますが、反訴の提起に当たっては、被告側にも一定の費用負担が生じ得ることに留意しましょう。
訴訟が長引く傾向にある
反訴を提起すると、訴訟手続きにおける論点が増えるため、審理が長引く傾向にあります。
別に訴訟を提起する場合に比べると効率的な審理が期待できるものの、本訴のみの場合に比べれば、長期化によって手間が増えることは間違いありません。
反訴を提起する必要があるのかどうか(勝訴の見込みはあるか、和解の条件交渉で十分ではないかなど)を、事前にきちんと精査しましょう。
反訴の手続き
被告が反訴を提起する場合、以下の流れで訴訟手続きが進行します。
① 反訴状などの提出
② 本訴と反訴の併合審理
③ 判決言渡し・判決書の送達
④ 控訴・上告
反訴状などの提出
反訴を提起する際の手続きは、本訴を提起する場合と同じです(民事訴訟法146条4項)。
本訴では「訴状」を裁判所へ提出するのと同様に、反訴を提起する際にも訴状を提出します(「反訴状」と呼ぶのが一般的です)。
また反訴状と併せて、反訴における請求や主張する事実を裏付ける証拠資料も、裁判所に対して提出します。
本訴と反訴の併合審理
反訴が適法に提起された場合、本訴と反訴は併合され、同じ訴訟手続きの中で審理されます。
具体的には、公開の口頭弁論期日において主張の提出や証拠調べなどを行います。争点や証拠を整理する必要がある場合は、口頭弁論期日の合間に非公開の弁論準備手続や書面による準備手続が行われることもあります。
争点と証拠の整理が済んだ段階で、当事者や証人に対する尋問が行われた後、判決に至るのが一般的です。
なお、訴訟の審理の途中で、裁判所が当事者に対して和解を提案することがあります(民事訴訟法89条)。当事者間に和解が成立した場合には、和解調書が作成されて訴訟手続きが終了します。
判決言渡し・判決書の送達
和解の見込みがない場合は、審理が熟した段階で裁判所が口頭弁論を終結させ、後日に判決を言い渡します。
判決の言渡し日においては、判決主文のみ読み上げられるのが一般的です。主文と理由が記載された判決書は、裁判所の書記官室で受け取るか、または数日後に郵送で送達されます。
控訴・上告
第一審の判決に不服があれば控訴、控訴審の判決に不服があれば上告をすることができます。控訴・上告の期間は、判決書の送達を受けた日から2週間以内です(民事訴訟法285条・313条)。
なお、控訴・上告による審理の対象は、当事者が不服を申し立てた範囲に限られます(同法296条1項・313条)。
例えば、本訴の判決に対して被告が控訴せず、反訴の判決に対して原告が控訴したとします。この場合は、反訴に関して不服が申し立てられた部分のみが、控訴審における審理の対象です。
期間内に適法な控訴が行われなかった場合、または上告審判決が言い渡された場合には、判決が確定します。
反訴を提起するときの注意点
民事訴訟の被告が反訴を提起する際には、以下の各点に注意しましょう。
① 反訴の提起により、簡易裁判所から地方裁判所へ移送されることがある
② 控訴審における反訴の提起には、相手方の同意が必要
③ 反訴提起の期間は制限されることがある
反訴の提起により、簡易裁判所から地方裁判所へ移送されることがある
本訴が簡易裁判所に係属している状況で、被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、原告の申立てがあるときは、簡易裁判所は決定で本訴と反訴を地方裁判所へ移送しなければなりません(民事訴訟法274条1項)。
具体的には、訴訟物の価額が140万円を超える請求や、不動産に関する請求などが地方裁判所の管轄に属します(裁判所法24条)。
訴訟物の価額を算定できないか、または算定がきわめて困難であるときは160万円とみなされるので、地方裁判所の管轄となります(民事訴訟費用等に関する法律4条7項)。
簡易裁判所に係属中の本訴について反訴を提起する際には、反訴の目的である請求が地方裁判所の管轄に属するかどうかを確認しておきましょう。
控訴審における反訴の提起には、相手方の同意が必要
控訴審において反訴を提起できるのは、相手方の同意がある場合に限られています(民事訴訟法300条1項)。控訴審から反訴が審理される場合、原告(反訴被告)は第一審における防御の機会を失ってしまうためです。
なお、相手方が異議を述べないで反訴の本案について弁論をしたときは、反訴の提起に同意したものとみなされます(同条2項)。
反訴提起の期間は制限されることがある
裁判長は当事者の意見を聴いて、反訴の提起をすべき期間を定めることができます(民事訴訟法301条1項)。
裁判長が定めた期間の経過後に反訴を提起する場合には、裁判所に対し、期間内に反訴を提起できなかった理由を説明しなければなりません(同条2項)。合理的な理由説明ができなければ、著しく訴訟手続きを遅滞させるものとして、反訴が不適法却下されるおそれがあるのでご注意ください。