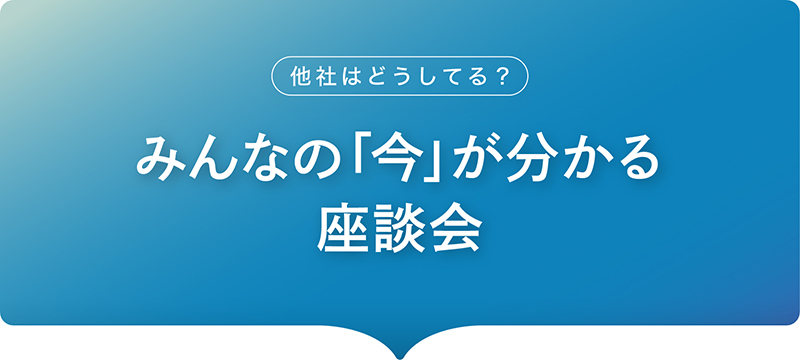契約における管轄・紛争解決条項とは?
ルールと実務上の留意点を解説!
| 法改正のまとめ資料を無料でダウンロードできます ✅ 10分で読める!2026年施行予定の法改正まとめ ✅ 10分で読める!2025年施行予定の法改正まとめ |
- この記事のまとめ
-
契約における管轄・紛争解決条項についてのルールと実務上の留意点をわかりやすく解説!
国際取引において、当事者間で紛争解決についてどのように決めればいいかは、契約交渉において頭を悩ますポイントです。何となくで決めてしまって、のちに大きな負担となるケースも少なくありません。しかし、セミナーなどで取り上げられることも少なく、なかなか知る機会がないのが実際ではないでしょうか。
日本においても平成23年(2011年)の民事訴訟法改正により国際裁判管轄が明文化されたり、新たな仲裁センターが新設されたりと、近年国際取引における紛争解決に向けた法整備が進んでいます。
この記事では、契約における管轄・紛争解決条項についてのルールと実務上の留意点を解説します。
※この記事では、法令名などを次のように記載しています。
- 民訴法…民事訴訟法
- チサダネ号判決…最三判昭和50年11月28日 民集29巻10号1554頁
(※この記事は、2021年11月12日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。)
目次
契約書における合意管轄・準拠法の役割とは?
契約書においては、その契約書がどのような法律に従って解釈されるのかという準拠法(英文契約においては“Governing Law”、“Choice of Laws”などと呼ばれます。)やその契約に関する紛争についてどの裁判所で取り扱われるべきかという管轄についての条項(英文契約においては“Jurisdiction”、“Venue”、“Forum Selection”などと呼ばれます。)が定められるのが一般的です。
このような準拠法や管轄についての定めを置く目的は、契約の当事者にとって、適用法令や紛争解決地の予測が立たなくなると、のちのち当事者が予測していない問題や予測していない地での紛争に巻き込まれるリスクが生じ、とりわけ複数の国の当事者が関与する国際取引などで契約取引の安定性が害されるおそれがあるためです。
通常、これらの条項は契約書の最後に置かれる「一般条項」のセクション(英文契約においては“General Provisions”、“Miscellaneous”などと呼ばれるセクションとなります。)に定められることが多く、契約書において見落としがちです。しかし、特に国際取引などにおいては、事後的に紛争が生じた場合に、準拠法や管轄の定めによっては、外国での訴訟を強いられたり、外国法の調査が必要になったりすることで多額の時間とコストを要し、思わぬ不利益を被るリスクがあります。
そこで本記事では、契約における管轄・紛争解決条項についてのルールと実務上の留意点を解説していきます。
合意管轄のルールや実務上の留意点は?
管轄合意とは、対象となる紛争についてどの地の裁判所で取り扱われるべきかを定めるものをいいます。
そして、管轄合意は、大きく、その効果に着目して①専属的合意と②付加的合意に、当事者の所在地に着目し①国内裁判管轄に関するものと②国際裁判管轄に関するものに、合意の内容に着目して①一方当事者の所在地とするもの、②第三国(中立国)とするもの、③クロス式(訴訟の被告の所在地)とするものに分類することができます。
| 管轄合意の主な分類 | |
|---|---|
| 効果に着目するもの | ・ 専属的合意 ・ 付加的合意 |
| 当事者の所在地に着目するもの | ・ 国内裁判管轄に関するもの ・ 国際裁判管轄に関するもの |
| 合意の内容に着目するもの | ・ 一方当事者の所在地とするもの ・ 第三国(中立国)とするもの ・ クロス式(訴訟の被告の所在地)とするもの |
専属的合意と付加的合意
専属的合意とは、ある地の裁判所を、対象となる紛争の専属的な管轄裁判所とする合意をいいます。当該合意により、対象となる紛争については、当該裁判所でしか訴訟を提起することができなくなります。
これに対して、付加的合意とは、法律上管轄が認められる裁判所に加えて、その他の地の裁判所にも対象となる紛争について管轄を認める合意をいいます。
上記のとおり、管轄合意は当事者の予測可能性を担保するためのものですので、実務においては専属的合意を行うのが一般的です。では、契約上「専属的」管轄裁判所(exclusive jurisdiction)とする旨を明記しない場合はどうなるでしょうか。その場合は、当事者の意思解釈により、専属的とする合意だったのか付加的とする合意だったのかを判断することとなります。
したがって、「専属的」という文言がなかったとしても、裁判所により、当事者間において、専属的にある裁判所を管轄裁判所とする趣旨であったと判断されることはありますが、無用な紛争を避けるためにも、契約書において「専属的」合意であると明確に定めておくのが良いでしょう。
国内裁判管轄と国際裁判管轄
国内裁判管轄について
国内裁判管轄に関する合意とは、日本国内のどの裁判所が管轄を有するかに注目するものです。例えば、大阪に所在する会社と東京に所在する会社が契約を締結する際に、東京地方裁判所に管轄を定める場合などがあります。
そもそも、訴訟を提起する際に、どの裁判所に訴訟を提起すべきかは、民訴法4条以下で定められています。請求によってそれぞれ異なりますが、例えば、甲(大阪に所在)が乙(東京に所在)に対して契約上の金銭の支払請求を行う場合、通常①被告である乙の所在地(民訴法4条1項)又は②「財産権上の訴え」(同法5条1号)として義務履行地(特別な指定がない場合、持参債務とされ原告の所在地)を管轄する裁判所に訴訟提起することになるのです。したがって、甲は大阪地方裁判所又は東京地方裁判所のどちらかを選択して、訴訟を提起できることになります(大阪に所在する甲としては大阪地方裁判所に訴訟提起するのが便宜でしょう。)。
しかし、乙からみると、東京と大阪どちらの裁判所で訴訟がされるかは甲の選択に委ねられることとなり、突然大阪での訴訟に巻き込まれるリスクを負うことになります。これを避けるために、合意によって管轄地を決定しておく必要が生じるのです。あらかじめ東京地方裁判所を専属的管轄裁判所とする合意をしておくことで、このようなリスクを避けることができます。
国内管轄合意が有効となるためには、①一審に関するものであること(民訴法11条1項)、②一定の法律関係に基づく訴えに関するものであること(同法11条2項)、③書面又は電磁的記録によってなされたものであること(同法11条2項、3項)が必要とされます。
したがって、第一審裁判所ではない「東京高等裁判所を専属的管轄裁判所とする。」旨の合意は認められません。もっとも、簡易裁判所を管轄裁判所とすることは認められており、管轄裁判所を例えば「東京簡易裁判所又は東京地方裁判所とする。」などと定めることも実務上珍しくありません。
国際裁判管轄について
これに対して、日本国内だけではなく、国を超えて、どの国の裁判所で訴訟をすべきかを定めるのが国際裁判管轄に関する合意になります。国内裁判管轄は、単に日本国内のどこで裁判をするかという問題だったのに対して、国際裁判管轄は、世界中のどの国の裁判所で裁判をするかという問題となり、その影響は国内裁判管轄の場合に比べて大きく、より慎重な判断が必要となります。
裁判に参加することの時間や費用はもちろんのこと、外国で弁護士を探して選任する困難性、使用言語の違い、そして国によって訴訟手続が異なることによる予測困難性と、外国で訴訟を行うことには多くの困難が伴います。実際上、自国の企業に有利な判決が出るというリスクも存在します。
したがって、予想しない国での訴訟に突然巻き込まれることによる不利益は、国内の紛争より大きく、事前に管轄国を決めておくことがとても重要になります。
国際裁判管轄を定める場合、実務上、管轄国の裁判制度を理解しておくことが重要となります。例えば、アメリカにおいては、各州に裁判所が所在するほか、州裁判所と連邦裁判所で取り扱う事件が異なるため、どの州の裁判所かを明らかにしたうえで、どのような種類の事件においても管轄を持たせるために州裁判所と連邦裁判所のいずれも管轄裁判所とするのが一般的です。
このように、各国によって裁判制度が異なり、日本とは異なる制度を有していることは珍しくないため、その点も考慮したうえで、不測の事態が生じないよう慎重に管轄合意の内容を記載することが求められるのです。
国際管轄合意が有効となるためには、形式的には①書面又は電磁的記録によってなされたものであること(書面性)が必要とされています(民訴法3条の7第2項、3項)。この書面の署名については、少なくとも当事者の一方が作成した書面に特定の国の裁判所が明示し指定されており、当事者間の合意の存在と内容が明白であれば足り、当事者双方の署名までは不要と考えられています(チサダネ号判決参照)。
また、実質的要件として②一定の法律関係に基づく訴えに関するものであること(民訴法3条の7第2項)、③外国裁判所の専属的管轄合意の場合、当該裁判所が法律上又は事実上裁判権を行うことができないときでないこと(同法3条の7第4項)、④訴えが国際的な専属管轄の対象(同法3条の5参照)ではないこと(同法3条の10)が必要とされます。
一定の法律関係に基づく訴えに関するものとは、あまりに広範で包括的な訴えを対象とするものを排斥する趣旨ですので、例えば「本契約に関する」という特定がなく「甲乙間のあらゆる紛争」を対象とした場合、一定の法律関係に基づくとはいえず、管轄合意の全部又は一部が無効となる可能性があります。
さらに、消費者契約及び労働契約においては、弱い立場に立たされる当事者を保護する趣旨から、事業者に一方的に有利な内容でないことが条件とされていることにも注意が必要です(同法3条の7第5項、6項)。
(なお、日本において訴訟提起がされた場合に、国際裁判管轄に関する合意について日本の民訴法に従って判断されるのは、「手続は法廷地法による」との不文律を根拠とするものです。)
(管轄権に関する合意)
「民事訴訟法」 e-Gov法令検索 – 電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ
第3条の7 当事者は、合意により、いずれの国の裁判所に訴えを提起することができるかについて定めることができる。
2 前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 第1項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
4 外国の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意は、その裁判所が法律上又は事実上裁判権を行うことができないときは、これを援用することができない。
5 将来において生ずる消費者契約に関する紛争を対象とする第1項の合意は、次に掲げる場合に限り、その効力を有する。
(1) 消費者契約の締結の時において消費者が住所を有していた国の裁判所に訴えを提起することができる旨の合意(その国の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意については、次号に掲げる場合を除き、その国以外の国の裁判所にも訴えを提起することを妨げない旨の合意とみなす。)であるとき。
(2) 消費者が当該合意に基づき合意された国の裁判所に訴えを提起したとき、又は事業者が日本若しくは外国の裁判所に訴えを提起した場合において、消費者が当該合意を援用したとき。
6 将来において生ずる個別労働関係民事紛争を対象とする第1項の合意は、次に掲げる場合に限り、その効力を有する。
(1) 労働契約の終了の時にされた合意であって、その時における労務の提供の地がある国の裁判所に訴えを提起することができる旨を定めたもの(その国の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意については、次号に掲げる場合を除き、その国以外の国の裁判所にも訴えを提起することを妨げない旨の合意とみなす。)であるとき。
(2) 労働者が当該合意に基づき合意された国の裁判所に訴えを提起したとき、又は事業主が日本若しくは外国の裁判所に訴えを提起した場合において、労働者が当該合意を援用したとき。
また、条文に記載のない条件として、被告の住所地国に専属管轄を認める合意について、それがはなはだしく不合理で公序法に違反する場合、無効とされる場合があることは覚えておくべきでしょう。
管轄合意に関するルールは平成23年(2011年)の民訴法改正(平成23年5月2日法律第36号)により明文化されましたが、それ以前は明文規定がなくチサダネ号判決による判例法理に従って判断されてきました。チサダネ号判決においては、管轄合意が要件を満たす場合であっても、「管轄の合意がはなはだしく不合理で公序法に違反するとき等の場合」には無効となる旨が示されています。
- チサダネ号判決の判断枠組み
-
チサダネ号判決は、
ある訴訟事件についてのわが国の裁判権を排除し、特定の外国の裁判所だけを第一審の管轄裁判所と指定する旨の国際的専属的裁判管轄の合意は、(イ)当該事件がわが国の裁判権に専属的に服するものではなく、(ロ)指定された外国の裁判所が、その外国法上、当該事件につき管轄権を有すること、の二個の要件をみたす限り、わが国の国際民訴法上、原則として有効である
としつつ
管轄の合意がはなはだしく不合理で公序法に違反するとき等の場合
には無効となる可能性がある点を判示している。
当該公序による無効の枠組みは、民訴改正により国際裁判管轄に関するルールが明文化された後も適用されると考えられております。
また、平成23年(2011年)改正民訴法における合意管轄に関する規定は平成24年(2012年)4月1日の施行日以前の合意には適用されないこととされているため(民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律(平成23年5月2日法律第36号)附則2条2項)、平成24年(2012年)4月1日以前の契約に基づく紛争については、以前としてチサダネ号判決の枠組みに従って判断されることになるのです。
事後的に不当に押し付けられた管轄合意であるといった主張がなされ、当該公序要件によって管轄合意が無効となるリスクを軽減するためにも、実務上当事者間において管轄合意の内容をしっかりと協議・交渉し、その内容を記録として保存しておくことが重要となります。
なお、民訴法には、日本に管轄があると認められる場合においても、事案の性質、当事者の訴訟負担、証拠の偏在等を考慮して特別な事情がある場合に、例外的に訴えを却下することができる定めがありますが(民訴法3条の9)、日本の裁判所に専属的管轄を認める合意がある場合には当該特別な事情による却下の定めは適用されないとされているため、当該条文によって管轄が否定されるおそれはありません。
管轄裁判所の決め方とは?
管轄合意の内容は主に3つの方法によって決められることが多いです。最も一般的なのは、当事者の一方の地を管轄裁判所とする方法でしょう。当事者の交渉の結果として、どちらか一方が所在する地の裁判所を管轄とします。
しかし、特に国際的取引において、相手方の地の国で裁判を行うことによる負担が大きいため、契約交渉において双方が納得せず、管轄合意が契約の成立の妨げになることは珍しくありません。
したがって、折衷的に、中立的な第三国を管轄国とする方法やクロス式に管轄を定める方法が取られることがあります。もっとも、第三国とする方法は、下記で述べる仲裁合意の場合によく見られますが、裁判管轄の場合、当事者と無関係の国で裁判を行うこととなり、第三国における管轄自体が否定されるリスクがありますので、好ましくはありません。
クロス方式で定める方法について
クロス式に管轄を定める方法とは、例えば、甲が乙に対して訴訟提起をする場合には乙国で、乙が甲に対して訴訟提起をする場合には甲国で訴訟をすると定める方法をいいます。
このように、それぞれ訴訟提起に巻き込まれる被告当事者の国で裁判を行うこととすることにより、訴訟提起をする側のハードルを上げ全体的な訴訟リスクを軽減させるとともに、当事者間の公平性を実現するのです。
その他の紛争解決手段の定め
その他の紛争解決手段として、裁判以外の手段を規定することも実務上行われています。例えば、訴訟を提起する前に当事者間での書面のやり取りや協議の機会を設けることを必要的な手続きとするといった定めがあります。
その中で最もよく用いられるのが紛争解決を仲裁によるとする仲裁合意です。これは、当事者間の紛争を公的機関である裁判機関ではなく、中立的な第三者機関(仲裁人)に委ねて、紛争を解決することをいいます。
仲裁とは?
仲裁を行うメリットとしては、仲裁人は当事者が自由に選ぶことができるために、一方当事者の所在国で裁判を行うことにより不利な判断がなされるというリスクを解消できることや、専門性・国際性を持った仲裁人を選任することができるため、迅速かつ適切な判断を期待できる点にあります。また、訴訟手続と異なり、仲裁手続は全て非公開が原則ですので、営業秘密の漏洩リスクや紛争に巻き込まれたこと自体によるレピュテーションリスクを避けることもできます。
他方で、仲裁はあくまで公的手続ではないため、現状判決の強制執行のように相手方に強制的な履行を行わせることができず、当事者の任意の履行に期待するしかありません。また、通常一審制をとっているため、仲裁判断に不服があったとしても、裁判手続と異なり不服申立てができません。
このように仲裁による紛争解決にはメリット・デメリットがありますが、通常裁判手続には多くの時間と費用を要し、ひとたび訴訟に巻き込まれると長期にわたって不安定な立場に置かれることも少なくありません。このようなリスクを避けるために仲裁制度を活用することも有益な選択肢として検討すべきでしょう。
仲裁合意について
仲裁での紛争解決を行うには、当事者間に仲裁合意があることが必要となります。仲裁合意は、管轄地を決定するだけでよかった裁判管轄合意と異なり、いかなる地でいかなる方法で行うかといったルールをあらかじめ詳細に決めておく必要があります。
具体的には①仲裁機関、②仲裁地、③従うべき仲裁規則を定めておくのが一般的です。また、仲裁人の数や仲裁言語もあらかじめ指定しておく場合もあります。世界各国に仲裁機関があり、それぞれが定める仲裁規則がありますので、当事者双方にとって適切と思われるものを選択します。
その場合に、第三国の仲裁機関を選択することも少なくありません。有名な第三国仲裁機関としては、シンガポール国際仲裁センター(Singapore International Arbitration Centre)などが挙げられます。
日本には、例えば国際商取引に関する紛争解決を取り扱う日本商事仲裁協会(Japan Commercial Arbitration Association)や知的財産に関する紛争解決を取り扱う日本知的財産仲裁センター(Japan Intellectual Property Arbitration Center)がありますが、2018年2月に新たに日本国際紛争解決センター(Japan International Dispute Resolution Center)が新設され、さらなる仲裁の活用が期待されています。
なお、仲裁合意がなされているにもかかわらず日本の裁判所に訴訟が提起された場合に、当事者が仲裁合意の存在を主張した場合、その訴えは却下されることになります(仲裁法14条1項本文)。
この記事のまとめ
このように管轄合意に関しては実は様々なルールがあり、契約上不用意な規定を置いてしまうと、のちのち予期せぬ土地での訴訟に巻き込まれ多額の費用と時間を費やすリスクがあるのです。
一見見落としがちですが、契約交渉においては、不利益な内容になっていないか、有効な内容になっているか、他に適切な選択肢はないのかなどを改めて確認してみることをお勧めします。その際に、本記事が参考になれば幸いです。
参考文献
日本商事仲裁協会「仲裁条項の書き方」(様々な仲裁条項の例を掲載している。)