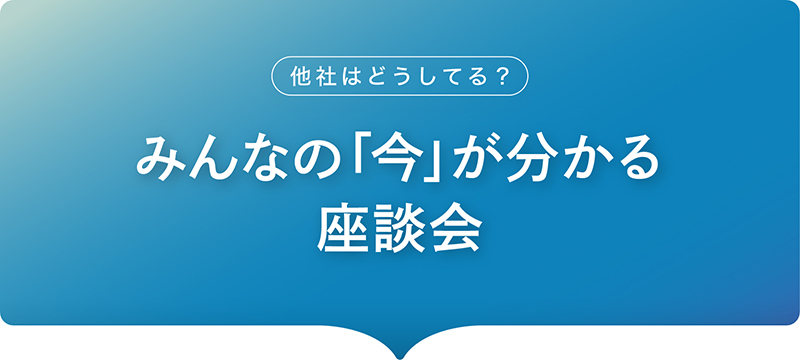撤回・解除とは?
法令用語としての意味・効力・解約との違いや
法律上のルールなどを分かりやすく解説!
| おすすめ資料を無料でダウンロードできます ✅ [法務必携!]ポケット契約用語集~基本編~ |
- この記事のまとめ
-
法令用語としての「撤回」とは、意思表示の効力を将来に向かって消滅させること(撤回前は有効)をいいます。
これに対して、「解除」とは、当事者の一方的な意思表示によって、契約の効力を当初に遡って消滅させることをいいます。
また、「解約」とは、将来に向かって契約を終了させること(解約前の効力は有効)をいいます。ただし、法令や契約では、「解除」の意味で「解約」を用いることがありますので注意しましょう。法律行為(契約)の撤回は相手方の同意があれば認められ、契約の解除については契約において解除事由を定めることも可能です。
この記事では法律行為の撤回・解除について、意味・効力・違いや法律上のルールなどを解説します。
※この記事は、2023年11月22日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。
※この記事では、法令名を次のように記載しています。
- 特定商取引法…特定商取引に関する法律
目次
「撤回」とは
法令用語としての「撤回」とは、意思表示の効力を将来に向かって消滅させることをいいます。撤回前の期間においては意思表示が有効であり、撤回した時点以降の期間においてのみ意思表示の効力が消滅します。
撤回ができる者・方法・期間
意思表示を撤回できるのは、その意思表示をした者またはその代理人もしくは承継人です。ただし、常に意思表示を撤回できるわけではなく、法律または契約によって撤回が認められる場合に限られます(後述)。
撤回の意思表示は、相手方に対する通知によって行います。内容証明郵便などによって撤回通知書を送付するのが一般的です。
撤回ができる期間は、原則として相手方がその意思表示に対して承諾を与えるまでです。ただし、法律に特別の規定がある場合は、その規定に従います。
撤回の効力
撤回された意思表示は、将来に向かってその効力を失います。一方、撤回前の段階では意思表示が有効であり、有効だった意思表示に基づいてなされた行為が覆されることはありません。
「解除」とは
「解除」とは、当事者の一方的な意思表示によって、契約の効力を当初に遡って消滅させることをいいます。
解除ができる者・方法・期間
契約を解除できるのは、解除権を有する契約当事者です。解除権は、法律または契約の規定に従って発生します。
契約の解除は、相手方に対する意思表示によって行います(民法540条1項)。内容証明郵便などによって解除通知書を送付するのが一般的です。
なお、契約解除の意思表示は撤回できません(同条2項)。
契約の解除権は、行使できる時から20年間行使しないと時効によって消滅します(民法166条2項)。
また、解除権の行使期間について契約上の定めがあるときは、その定めに従います。
解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は解除権者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができます。催告によって定められた期間内に解除通知を相手方に到達させないと、解除権が消滅します(民法547条)。
解除の効力
契約が解除されると、その契約は当初に遡って無効となります。
したがって、解除された契約の当事者は、契約に基づいて受けた給付(金銭の支払い・物の引渡しなど)を相手方に返還するなどの原状回復義務を負います(民法545条1項本文)。金銭を返還するときは、受領の時から利息を付さなければなりません(同条2項)。
なお、契約の解除によって第三者の権利を害することはできないとされています(同条1項但し書き)。
例えばAがBに対して不動産を売却し、BがCに対してその不動産を売却した後、AがBとの不動産売買契約を解除したとします。この場合、AとCのどちらが不動産の所有者となるかが問題となります。
判例上は、登記を先に経由した側が保護されるものと解されています(解除前の第三者について最高裁昭和33年6月14日判決、解除後の第三者について最高裁昭和35年11月29日判決)。
「解約」とは|解除との違い
解除に対比される概念として、将来に向かって契約を終了させることを「解約」といいます。
解除が契約を当初に遡って消滅させるものであるのに対して、解約は契約の効果を将来に向かって消滅させるものです。解約の場合、解約前の契約に基づいて行われた給付等は有効なので、当事者は原状回復義務を負いません。
もっとも契約においては、「解除」の意味で「解約」を用いることがあります。どちらの意味で用いられているのかが契約上明らかではないときは、相手方との間で認識を共有した上で、その効果の内容を契約に明記することが望ましいです。
撤回・解除の違い
これまで解説した内容を踏まえて、撤回と解除の違いをまとめました。
| 撤回 | 解除 | |
|---|---|---|
| 対象 | 意思表示 | 契約(当事者の合意) |
| 期間 | 相手方が承諾するまで | 解除権が時効消滅するまで、または相手方の催告によって解除権が消滅するまで |
| 効力 | 将来に向かって意思表示の効力が消滅する | 当初に遡って契約の効力が消滅する |
クーリング・オフとは
特定商取引法その他の法律では、一定の契約について「クーリング・オフ」を認めています。
クーリング・オフとは、一定の期間に限り、ペナルティなしで消費者が事業者に対する意思表示を撤回し、または事業者と締結した契約を解除できる制度です。消費者が締結時に冷静な判断をしにくい類型の契約につき、再考の機会を与えるためにクーリング・オフが認められています。
主なクーリング・オフの対象取引と期間は、以下のとおりです。
| クーリング・オフの対象取引 | クーリング・オフの期間 |
|---|---|
| 訪問販売(キャッチセールスを含む) | 契約締結書面の受領日を含めて8日間 |
| 電話勧誘販売 | 契約締結書面の受領日を含めて8日間 |
| 特定継続的役務提供 | 契約締結書面の受領日を含めて8日間 |
| 個別信用購入あっせん(個別クレジット契約) | 契約締結書面の受領日を含めて8日間 |
| 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地・建物の売買契約 | クーリング・オフができる旨の告知を受けた日を含めて8日間 |
| ゴルフ会員権契約(50万円以上) | 契約締結書面の受領日を含めて8日間 |
| 保険契約 | クーリング・オフに関する事項が記載された書面の受領日と申込日のいずれか遅い日を含めて8日間 |
| 投資顧問契約 | 契約締結書面の受領日を含めて10日間 |
| 現物まがい商法 | 契約締結書面の受領日を含めて14日間 |
| 連鎖販売取引(マルチ商法) | 契約締結書面の受領日を含めて20日間 |
| 業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法) | 契約締結書面の受領日を含めて20日間 |
意思表示を撤回できる場合の例
意思表示を撤回できる場合としては、クーリング・オフが認められる場合のほか、以下の例が挙げられます。
① 承諾の通知を受けるのに相当な期間が経過した場合
② 申込者が撤回権を留保した場合
③ 申込みをした対話が継続している場合
④ 相手方が撤回に同意した場合
承諾の通知を受けるのに相当な期間が経過した場合
承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができません(民法525条1項)。
その反対解釈として、承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過すれば、申込みの意思表示を撤回することができます。
「相当な期間」がどのくらいの長さであるかは、取引の性質によって個別に判断されます。曖昧さを回避するためには、申込み通知において承諾期間を明記することが望ましいでしょう。
なお、承諾期間を明記した申込みは撤回できず、承諾期間が経過すると自動的に失効します(民法523条)。
申込者が撤回権を留保した場合
承諾期間の定めの有無に関わらず、申込者が撤回をする権利を留保したときは、申込みの意思表示を撤回することができます(民法523条1項・525条1項)。
ただし、撤回権に条件や期限が付されている場合には、その定めに従います。
申込みをした対話が継続している場合
相手方と対話している最中にした申込みの意思表示は、対話が継続している間であればいつでも撤回できます(民法525条2項)。
なお、対話中に行った申込みは、対話が継続している間に承諾の通知を受けなかったときは失効します。ただし、申込者が対話の終了後もその申込みが効力を失わない旨を表示したときは、この限りではありません(同条3項)。
相手方が撤回に同意した場合
法律の規定によって申込みを撤回できる場合に当たるか否かに関わらず、相手方が撤回に同意した場合には、その申込みを撤回できます。契約を成立させるかどうかは、当事者の自由な意思に委ねるべき事項だからです。
契約を解除できる場合の例
契約を解除できる場合としては、クーリング・オフが認められる場合のほか、以下の例が挙げられます。
① 相手方の債務が不履行となった場合|催告解除と無催告解除
② 契約上の解除事由に該当した場合
相手方の債務が不履行となった場合|催告解除と無催告解除
相手方が負う契約上の債務が不履行となった場合には、契約を解除できることがあります。これを「債務不履行解除」といいます。
債務不履行解除の手続きには、「催告解除」と「無催告解除」の2種類があります。
催告解除とは
「催告解除」とは、相手方に対して債務の履行を催告した上で、履行がなかった場合に契約を解除する手続きです(民法541条)。
催告解除は、まず相当の期間を定めて債務の履行を催告し、相当の期間が経過した後で契約を解除するという手順で行います。
ただし、履行の催告と解除は同じ通知によって行うことができます。実務上は、「○○日以内に債務を履行してください。履行しなければ、その時点で契約を解除します。」という内容の通知を発送するのが一般的です。
「相当の期間」としてどの程度の期間を設定すべきかについては、履行すべき債務の性質によって異なります。
一般的には、金銭債務であれば2~3営業日以上の履行期間が必要と考えられます。実務上は、1週間から2週間程度の履行期間を設けることが多いです。
履行期間を定めなかった場合や、相当の期間に満たない履行期間を設定した場合でも、催告解除通知が無効になるわけではありません。催告時から客観的な相当の期間が経過すれば、解除の効果が発生すると解されています(最高裁昭和31年12月6日判決、最高裁昭和44年4月15日判決)。
なお、相当の期間が経過した時点における債務の不履行が、その契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、契約を催告解除することができません(民法541条但し書き)。
無催告解除とは
「無催告解除」とは、相手方に対して債務の履行を催告することなく、直ちに契約を解除する手続きです(民法542条)。
以下のいずれかに該当する場合には、無催告解除が認められます。
① 契約の全部を無催告解除できる場合
(a) 債務の全部の履行が不能であるとき
(b) 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき
(c) 債務の一部の履行が不能である場合または債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき
(d) 契約の性質または当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき
(e) (a)~(d)のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が履行の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき
② 契約の一部を無催告解除できる場合
(a) 債務の一部の履行が不能であるとき
(b) 債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき
契約上の解除事由に該当した場合
相手方が契約によって定められた解除事由に該当した場合も、契約を解除できます。催告解除と無催告解除のどちらが認められるかは、契約の定めに従います。
- 契約上の解除事由の例
-
・契約上の義務違反(特に、無催告解除を認める場合)
・実行前提条件の不充足
・表明保証違反
・反社会的勢力に該当したこと
・倒産手続が開始したこと
・財務状況が深刻に悪化したこと
・天災地変などにより、債務の履行が困難になったこと
など
| おすすめ資料を無料でダウンロードできます ✅ [法務必携!]ポケット契約用語集~基本編~ |