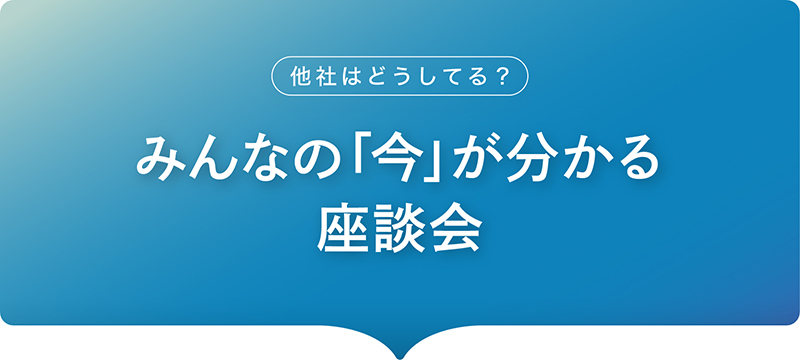分離可能性条項(分離条項)とは?
規定の目的・例文・レビューポイント
などを分かりやすく解説!
- この記事のまとめ
-
分離可能性条項(分離条項)とは、契約内容の一部が無効になったとしても、他の条項は引き続き有効であることを定めた条項です。
分離可能性条項は、国際取引に関する契約(主に英文契約)で定めるケースが多いです。国際取引の場合、外国法が適用され、契約内容の一部が無効となるリスクが高くなるためです。
分離可能性条項は、このようなリスクを最小限に抑えるために定められます。
なお、契約が無効となるリスクを回避するには、分離可能性条項を定めるだけでは不十分で、そもそも無効にならないよう契約書を作成することが大切です。
国際取引の契約書のレビューは、必要に応じて現地法に詳しい弁護士のアドバイスを受けながら対応しましょう。
今回は分離可能性条項(分離条項)について、規定の目的・例文・レビューポイントなどを分かりやすく解説します。
※この記事は、2022年11月16日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。
目次
分離可能性条項(分離条項)とは
分離可能性条項(分離条項)とは、契約内容の一部が無効になったとしても、他の条項は引き続き有効である旨を定めた条項です。
分離可能性条項は、国際取引に関する契約(主に英文契約)で定めるケースが多いです。
国際取引の場合、日本では法律違反とならない条項が、外国法では無効となる場合もあります。そのため、国際取引では、分離可能性条項を定め、契約が無効となるリスクをケアすることが多いのです。
分離可能性条項の法的効果
分離可能性条項を定めた場合、一部の条項が無効になったとしても、その他の条項は原則として有効に存続します。
無効となった条項については、契約に基づくルールがなくなるため、法令(民法など)が適用されます。これに対して、その他の条項は有効に存続するため、引き続き契約書が適用されます。
例えば、金銭消費貸借契約において、以下のような条項を定めたとします。
(利息)
第○条
1.借入人は貸付人に対し、毎月末日までに、貸付人が別途指定する銀行口座に振り込む方法により、本件貸し付けに係る利息を支払う。なお、振込手数料は借入人の負担とする。
2.前項に定める利息の金額は、以下の式により計算する。
利息=当該月末日0時0分時点における本件貸し付けの元本残高×30%×当該利息計算期間の実日数÷365
第2項は、利率を「年30%」と定めていますが、これは利息制限法1条違反となります。したがって、利息制限法の上限金利が自動的に適用されます。
しかし、分離可能性条項を定めておけば、第2項(の一部)が無効になったとしても、第1項は影響を受けず、有効に存続します。つまり、利息の請求自体は可能(利率だけ変わる)ということです。
分離可能性条項を定める目的
分離可能性条項の目的は、予期せぬ条項の無効が発生した場合に、その影響を最小限に抑えることです。
一部の条項が無効になった場合に、それ以外の条項まで無効となってしまうと、契約書を再締結する必要性がでてきてしまいます。それだけでなく、これまでなされた取引に関しても、依拠すべき契約(=ルール)が無効となることに伴い、当事者間で紛争が生じることになりかねません。
分離可能性条項が定められる契約の例
分離可能性条項を定める例が多いのは、主に異なる国・地域の企業間で締結する契約書です。
典型例としては、英文契約書が挙げられます(英文契約書では、分離可能性条項は”severability”と訳されます)。
英文契約書では、準拠法を定めるのが一般的です。
- 準拠法とは
-
準拠法とは、その契約書の解釈に当たり、準拠すべき国の法令を定めたものです。
【例文】
(準拠法)
本契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。日本国内で行われる契約の場合は、日本法を準拠法とするのが一般的です。異なる国同士の契約では、どちらの国を準拠法とするのかという問題が発生しますが、基本的には、当事者は通常、自国の法律を準拠法とすることを望みます。
国際取引の場合、準拠法とされた法について、当事者双方が十分に精通しているケースはまれです。
例えば、日本企業と米国企業が締結する契約において、中立性の観点から、第三国であるシンガポール法を準拠法と設定したとします。この場合、双方にとって自国の法律ではないので、双方の契約審査が十分に機能せず、無効な条項が見過ごされてしまうおそれがあります。
また、各国の法令に基づき、条項に対して準拠法以外の法が適用されることもあり得ます。その結果、予期せず契約の一部が無効になってしまうケースが散見されます。
こうした事情から、異なる国・地域の企業間で締結する契約書では、契約の一部無効による影響の拡大を防ぐ目的で、分離可能性条項を定める例が多くなっています。
分離可能性条項に定めるべき事項・例文(条文例)
分離可能性条項では、主に以下の事項を定めます。
・契約の一部の無効・違法・執行不能が、他の条項に影響しない旨
・無効・違法・執行不能とされた条項についての協議
契約の一部の無効・違法・執行不能が、他の条項に影響しない旨
本契約の一部の条項が無効、違法または執行不能となった場合においても、その他の条項の有効性、合法性および執行可能性はいかなる意味においても損なわれることはなく、また影響を受けない。
分離可能性条項のメインとなる内容として、契約の一部の
・無効
・違法
・執行不能
が、他の条項に影響しない旨を定めます。
無効・違法・執行不能とされた条項についての協議
本契約の当事者は、無効、違法または執行不能とされた本契約の一部の条項について、できる限り当事者双方の当初の意図を反映するよう修正すべく協議する義務を負う。
上記の例文は、無効・違法・執行不能とされた条項を修正するために協議することを、当事者双方の義務としています。
なお、協議の結果、修正結果についての合意がない限り、その修正は有効になりません。あくまでも「誠実に協議をして対応を検討する」という姿勢を確認するものにとどまります(一般条項である誠実協議条項と同じです)。
分離可能性条項を定める際の注意点(レビューポイント)
分離可能性条項を定める場合、チェックすべき主なポイントは以下のとおりです。
・分離可能性条項は一般条項|本文の終盤に定める
・そもそも契約条項が無効にならないように注意すべき|他の条項の充実を
分離可能性条項は一般条項|本文の終盤に定める
分離可能性条項は、契約におけるメインの取引内容を定めるものではなく、一般条項として位置づけられるものです。よって、他の一般条項と同様に、本文の終盤に定めるのが適切です。
そもそも契約条項が無効にならないように注意すべき|他の条項の充実を
分離可能性条項そのものは定型的な内容なので、特に注意深くレビューする必要はありません。
分離可能性条項によってリスクが最小限に抑えられるとはいえ、契約の一部が無効となってしまえば、取引に影響が出ることは避けられません。
こうした事態を避けるためには、契約を締結する前の段階で、契約中に無効な条項が含まれていないかどうかきちんと検討する必要があります。
各条項が無効にならないためにとるべき対応
各条項が無効にならないようにするためには、以下のポイントに留意して契約をレビューすることが大切です。
・明確な文言で条文を作成する
・適用される法令を調査する
・現地法弁護士にアドバイスを求める
明確な文言で条文を作成する
第一に、すべての契約条項は明確な文言で記載しなければなりません。文言が曖昧だと、ルールの内容が一つに定まらず、最悪の場合、契約条項が無効になってしまいます。
- 契約書の5W1H
-
・主体(「誰が」「誰に」、Who)
→「甲は乙に対して」・時期(「いつ」、When)
→「売買実行日に」・場所(「どこで」、Where)
→「X不動産の所在地において」・条件(「~した場合には」、Why)
→「売買代金全額の支払いと引き換えに」・行為(「何を」、What)
→「X不動産を引き渡す」・方法(「どのような方法で」、How)
→「X不動産の鍵を交付する方法で」(例)
「甲は乙に対して、売買実行日に、X不動産の所在地においてX不動産の鍵を交付する方法で、乙の甲に対する売買代金全額の支払いと引き換えに、X不動産を引き渡す。」
5W1Hを丁寧に記載すると、条文は長い文章になってしまいがちです。しかし、契約書の条文を作成する際には、読みやすさよりも内容の明確性が重視されます。疑義のない条文に仕上げるためにも、5W1Hをよく意識してレビューを行いましょう。
適用される法令を調査する
一般に、法令の規定には「強行規定」と「任意規定」の2つがあります。
・強行規定
契約で法律と別の内容を定めたとしても、法律が強制的に優先して適用される規定
・任意規定
契約で法律と異なる内容を任意で定めた場合、法律よりも契約の内容が優先して適用される規定
(ただし契約で別の内容を定めない場合は、自動的に法律のルールが適用される)
特に注意深くチェックすべきなのは、強行規定に違反する条項が含まれていないかどうかです。強行規定に違反する条項は無効となるため、レビューの段階で削除または修正する必要があります。
また、国際取引に関する契約書の場合、準拠法に加えて、それ以外の法における強行規定の適用可能性についても検討が必要です。
特に、米国やEU圏の企業と取引をする際には、実際の取引が日本で行われる場合でも、米国法・EU法が域外適用されることがあります。その結果、予期せず契約の一部が無効となってしまうケースも想定されるので、いっそう注意深いレビューを行わなければなりません。
現地法に詳しい弁護士にアドバイスを求める
契約の準拠法が外国法の場合、自社の法務部門や顧問弁護士だけでは、準拠法に関する調査を十分に行うことは困難です。
そのため、現地法に詳しい弁護士にアドバイスを求めながらレビューを行うことが望ましいです。
特に、同じ相手と継続的な取引を想定する場合には、最初の契約を締結する段階で、現地法に詳しい弁護士を交えた慎重な契約レビューを行うべきです。依頼できる弁護士に心当たりがなければ、顧問弁護士に紹介を依頼するのがよいでしょう。
この記事のまとめ
分離可能性条項(分離条項)の記事は以上です。最新の記事に関する情報は、契約ウォッチのメルマガで配信しています。ぜひ、メルマガにご登録ください!
参考文献
阿部博友著『リーガルイングリッシュ ビジネスコミュニケーションの技法』中央経済社、2021年