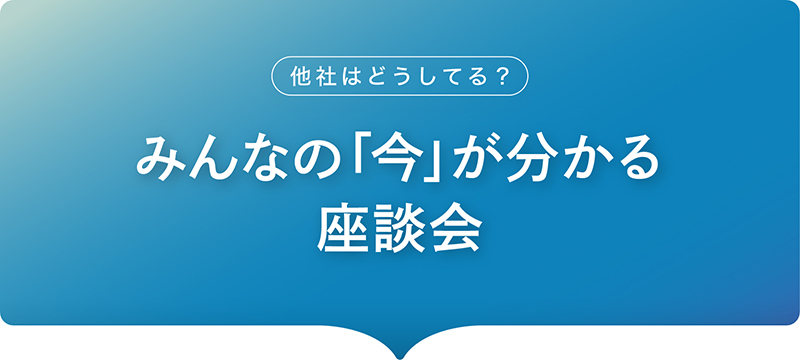事業譲渡契約とは?
会社法上の手続きや収入印紙などの
基本を分かりやすく解説!
※この記事は、2022年12月8日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。
目次
事業譲渡契約とは
事業譲渡とは、会社が他社に事業を取引行為として譲渡することをいい、事業譲渡契約とは、この事業譲渡という取引をする際に締結する契約をいいます。
この記事では、事業譲渡と事業譲渡契約について詳しく見ていきます。
事業譲渡とは
事業譲渡の定義
事業譲渡とは、会社が他社に事業を取引行為として譲渡することをいいますが、判例は、事業譲渡のうち株主総会の特別決議を要する事業譲渡(詳細は「会社法上の手続き」を参照)について、以下のとおり定義しています(なお、この判例は平成17年改正前商法の「営業」譲渡に関するものですが、「事業」譲渡と同じものと考えて問題ありません)。
最大判昭和40・9・22民集19巻6号1600頁
裁判所ウェブサイト
「一定の営業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産(得意先関係等の経済的価値のある事実関係を含む。)の全部または重要な一部を譲渡し、これによって、譲渡会社がその財産によって営んでいた営業的活動の全部または重要な一部を譲受人に受け継がせ、譲渡会社がその譲渡の限度に応じ法律上当然に同法25条〔筆者注:現在の会社法21条〕に定める競業避止業務を負う結果を伴うもの」。
特にポイントとなるのは、「一定の営業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産(得意先関係等の経済的価値のある事実関係を含む。)」の点です。
このような定義からは、個々の財産を譲渡したり、財産の寄せ集めを譲渡するだけでは事業譲渡とはいえず、ある事業を行うために必要となる資産等(不動産、動産、知的財産、契約上の権利義務等)を一体のまとまりとして一括して譲渡する行為が、事業譲渡に当たるといえます。
事業譲渡の特徴|株式譲渡・会社分割との違い
事業譲渡の特徴は、契約により、譲渡対象とする資産等を自由に選択できる点にあります。
一方、事業譲渡といっても、つまりは個別の資産等の承継に係る取引行為が一括して行われることですので、例えば、
債務の承継→債権者の承諾が必要(民法472条3項)
従業員の承継→個々の従業員との間で転籍等の手続きが必要(同法625条1項)
不動産の承継→対抗要件(登記)がなければ第三者に対抗できない(同法177条)
などの手続き負担が重くなる可能性があります。
事業譲渡は経済的に見て、会社分割(吸収分割)と同様の機能を持つといわれていますが、吸収分割では、吸収分割契約に従って包括的に資産等が承継されます。
このため、原則として債務の承継に当たり債権者の承諾は不要ですし、従業員の承継についても、「会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律」の手続きを経ることによって、従業員との雇用契約を包括的に承継させることが可能です。
事業譲渡=個別の取引行為が一括して行われる
会社分割=包括的に資産等が承継される
この点が、大きな違いとなっています。
また、事業譲渡を株式譲渡とも比較してみましょう。
株式譲渡の場合、譲渡の対象は会社の株式です。当該会社の株式の100%を取得できた場合には、当該会社自体を所有することができたということになります。
一方、事業譲渡の場合、譲渡の対象はあくまで会社の事業です。事業譲渡を受けても当該事業に係る権利義務を承継するに過ぎず、当該会社自体を所有することになるわけではありません。
会社法上の手続き
事業譲渡のうち、一定のものについては、ただ当事者間で事業譲渡契約を締結するだけではその効果が生じず、会社法上必要とされる手続きを経なければなりません。
以下では、会社法上の手続きが必要となる場面や手続きの内容について、詳しく見ていきます。
事業譲渡の実行に当たり必要な手続き
まず、事業を譲渡する側の当事者(譲渡会社)で必要となる手続を見ていきます。
事業譲渡のうち、
① 事業の全部の譲渡
② 事業の重要な一部の譲渡(譲渡する資産の帳簿価額が総資産額の20%を超えないものを除く)
については、効力発生日の前日までに、株主総会の特別決議によって、当該事業譲渡の承認を受けなければなりません(会社法467条1項1号・2号・309条2項11号)。
反対にいうと、
①´ 事業の全部の譲渡に当たらない場合
②´ 譲渡する資産の帳簿価額が総資産額の20%を超えない場合
②″ 譲渡する資産の帳簿価額が総資産額の20%を超えるが、重要な事業譲渡に当たらない場合
は株主総会の承認は不要です。
もっとも、通常、事業譲渡は、「重要な財産の処分」に当たることが多いと考えられ、その場合は取締役会の承認が必要です(会社法362条4項1号)。
次に、事業を譲り受ける側の当事者(譲受会社)においても、一定の場合に、会社法上の手続きを経る必要がありますので、この際に必要となる手続きについて見ていきます。
事業の譲受けのうち、「他の会社……の事業の全部の譲受け」をする場合は、効力発生日の前日までに、株主総会の特別決議によって当該事業の譲受けについて承認を受ける必要があります(会社法467条1項3号・309条2項11号)。
もっとも、譲受会社が対価として交付する財産の帳簿価額が総資産額の20%を超えない場合は株主総会の承認は不要です(会社法468条2項、会社法施行規則137条)。なお、事業の譲受けが「重要な財産の……譲受け」に当たる場合は取締役会の承認が必要です(会社法362条4項1号)。
また、事業譲渡に当たっては、株主の株式買取請求権にも注意する必要があります。
譲渡会社については、
① 事業の全部の譲渡
② 事業の重要な一部の譲渡(譲渡する資産の帳簿価額が総資産額の20%を超えないものを除く)
に当たる場合、
譲受会社については、
③「他の会社……の事業の全部の譲受け」(譲受会社が対価として交付する財産の帳簿価額が総資産額の20%を超えない場合を除く)
に当たる場合、
これらの事業譲渡等に反対する株主には株式買取請求権が与えられますので、これに伴う手続きも経る必要があります(会社法469条・470条)。
略式事業譲渡の場合
「事業譲渡の実行に当たり必要な手続き」に記載のとおり、一定の事業譲渡等を行う場合、株主総会の承認が必要となります。
この例外として、事業譲渡等の相手方が事業譲渡等をする会社の特別支配会社(総株主の議決権の90%以上を有する場合。会社法468条1項、会社法施行規則136条)である場合は、株主総会の承認は不要です(会社法468条1項)。これを、略式事業譲渡といいます。
株主総会の承認を得ない事業譲渡の効力
「事業譲渡の実行に当たり必要な手続き」に記載のとおり、一定の事業譲渡等を行う場合、株主総会の承認が必要です。
では、仮に株主総会の承認を受けずに事業譲渡等を行った場合、そのような事業譲渡等の効力はどうなるでしょうか。
判例(最一小判昭和61・9・11判時1215号125頁)は、会社が株主総会の承認を受けずに事業の全部または重要な一部を譲渡した場合、当該譲渡は無効であると判断しています。
譲受会社としては、このような判例を踏まえると、
その事業譲渡が譲渡会社の株主総会の承認を要するものであるか否か
→株主総会の承認を要する場合はその承認を受けているか
について、十分確認することが必要といえます。
なお、「一般的な事業譲渡の手続き」に記載のとおり、株主総会の承認が必要な事業譲渡に当たらないものの、「重要な財産の処分」に当たる場合は取締役会の承認が必要です(会社法362条4項1号)。
この取締役会の承認を欠いた場合であっても原則として当該財産の処分は有効となります。ただし、相手方が取締役会決議を経ていないことを知っていた、または知ることができたときは無効と考えられています(最三小判昭和40・9・22民集19巻6号1656頁)。
事業譲渡をした場合の法律関係
会社法では、会社間で事業譲渡がされた場合の法律関係についても規定していますので、主要なものを紹介します。
まず、譲渡会社は、同一・隣接する市町村内で、譲渡後20年間、譲渡した事業と同一の事業をすることはできなくなります(競業避止義務、会社法21条1項)。
当事者間で別途合意すれば、この競業避止義務を排除・軽減・加重することもできますが、加重する場合、期間の上限は譲渡後30年間です(会社法21条2項)。
なお、譲渡会社は、期間や場所の制限なく、不正の競争の目的(譲渡した事業の顧客を奪うなど)を持って同一の事業をすることはできません(会社法21条3項)。
会社法上のこれらの規定も踏まえ、「(事業譲渡実行後の)遵守事項」に記載のとおり、事業譲渡契約では競業避止義務について合意するか検討することが必要です。
事業譲渡契約に盛り込むべき主な条項と書き方のポイント・注意点
事業譲渡の合意
事業譲渡契約ですので、まずは、譲渡人から譲受人に譲渡人のある事業を譲渡することを明確に規定します。この際、譲渡の対象となる事業を特定する必要がありますので、譲渡人が行っている他の事業の内容も踏まえ、「甲が営む〇〇事業」といった形で特定します。
譲渡日(効力発生日)
「事業譲渡の実行に当たり必要な手続き」に記載のとおり、一定の事業譲渡を行う場合、効力発生日の前日までに、株主総会の承認を受けなければなりません。このため、事業譲渡契約において、この効力発生日を特定しておくことが一般的です。
譲渡資産の特定
「事業譲渡の特徴 |株式譲渡・会社分割との違い」に記載のとおり、事業譲渡の場合、会社分割のようにある事業に関する権利義務を包括的に承継することになるのではなく、当事者間で譲渡対象とする資産等を決定した上、各資産等の承継手続きを個別に行うことが必要です。
このため、事業譲渡契約では、譲渡対象とする資産等を、別紙に掲載するなどの方法により、過不足がないよう具体的かつ詳細に特定することが必要です。
特に譲受会社としては、簿外債務(貸借対照表にない債務)や偶発債務(将来債務となる可能性がある債務)を承継することがないよう、譲渡対象となる資産等の特定には十分注意することが必要です。
譲渡対価
事業譲渡契約では、当然のことながら、譲受人が譲渡人に支払う事業譲渡の対価についても規定することとなります。確定額で規定することが多いのではないかと考えられますが、その他、譲渡対価の算定方式を定める場合等も考えられます。
従業員に関する取り決め
「事業譲渡の特徴 |株式譲渡・会社分割との違い」に記載のとおり、事業譲渡の場合、会社分割とは異なり、譲渡会社の従業員が当然に譲受会社に承継されるわけではありませんので、譲受会社に承継される従業員を特定するとともに、当該従業員との間で個別に転籍等の同意を取得することが必要となります。
そこで、事業譲渡契約においても、まず、譲受会社へ転籍する従業員等を別紙に掲載するなどして特定することが必要です。
加えて、特に譲受会社の立場からは、例えば「(事業譲渡実行前の)遵守事項」において、譲渡会社に、承継される従業員から転籍等に関する承諾書を取得する努力義務を課したり、特に当該事業を行うために欠かせないキーパーソンについては、転籍等に関する承諾書の取得を「前提条件」として規定するなどの対応が考えられます。
前提条件
前提条件とは、当該条件を満たしていない場合には、当事会社が事業譲渡実行の義務を負わないとする規定です。いずれの立場の当事者としても、「このような条件が達成されていなければ事業譲渡を実行しても目的が達成できない」といった事項を、前提条件として規定しておくことになります。
例えば、以下の事項を前提条件として規定することが多いです。
- 表明保証事項が効力発生日においても真実かつ正確であること
- 会社法上の手続き(株主総会の承認等)が履践されていること
- 事業譲渡契約上の義務違反が存在しないこと
その他、特に、譲受会社の立場からは、
- 重要な資産等に悪影響が生じていないこと
- 重要な契約・債務の承継について契約相手方の承諾を得られていること
- キーパーソンとなる従業員の転籍について当該従業員の承諾を得られていること
を前提条件とすることも考えられます。
表明保証
事業譲渡契約においても、他のM&A契約と同様、表明保証条項(ある時点における一定の事実が真実かつ正確であることを表明し保証する条項)を設けることが多いです。
具体的な表明保証事項は、デューデリジェンスの結果も踏まえ、当事者間の交渉で決定されますので案件ごと様々ですし、多岐の事項にわたることが多いですが、事業譲渡契約では、例えば、以下のような事項について表明保証をすることが考えられます。
- 契約の締結・履行権限に関する事項(双方)
- 必要な社内手続き・法的手続きの履践に関する事項(双方)
- 譲渡対象となる事業・資産・債務・契約・従業員等に関する事項(譲渡会社)
表明保証条項に違反した場合は、金銭補償の対象としたり、事業譲渡実行の前提条件を欠くものとして扱うことになります。
(事業譲渡実行前の)遵守事項
事業譲渡実行に当たっては、事業譲渡契約の締結から事業譲渡の実行までに一定の期間を要することが多いです。そして、この間に、譲渡会社が対象事業の状態を変更してしまうと、事業譲渡契約を締結した基礎が変わってしまうため、譲受会社としては、事業譲渡契約を締結した目的を達成できないかもしれません。
また、「事業譲渡の特徴 |株式譲渡・会社分割との違い」に記載のとおり、事業譲渡といっても個別の資産等の承継が一括して行われるだけですので、例えば債務の承継に当たり債権者の承諾が必要となるなど、事業譲渡契約の締結から事業譲渡の実行までに、資産等の承継のために一定の手続きを行う必要もあります。
そこで、事業譲渡契約では、特に譲受会社の立場から、事業譲渡契約の締結から事業譲渡の実行までの間に譲渡会社が遵守すべき事項を規定しておくことが多いです。
- (事業譲渡実行前の)遵守事項の例
-
・資産等の管理に関する事項
・債務や契約の承継に関する承諾取得に関する事項
・転籍する従業員の承諾取得に関する事項
(事業譲渡実行後の)遵守事項
事業譲渡実行後においても、事業譲渡契約の相手方が何らかの行為をすることによって、事業譲渡契約を締結した目的を達成できない場合も想定されます。そこで、事業譲渡契約では、事業譲渡実行後の遵守事項について規定しておくことが多いです。
- (事業譲渡実行後の)遵守事項の例
-
・競業避止義務に関する事項(譲渡会社の遵守事項)
・譲受会社に承継した従業員(キーパーソン)の引き抜き防止に関する事項(譲渡会社の遵守事項)
・承継した従業員の雇用維持に関する事項(譲受会社の遵守事項)
なお、競業避止義務については、「事業譲渡をした場合の法律関係」に記載のとおり、会社法でも一定の競業避止義務が規定されていますが(会社法21条)、当事者間で会社法上の規定とは異なる内容で競業避止義務を定めることが可能であり、別途事業譲渡契約に競業避止に関する規定を設けることが多いです。
補償
一方当事者に表明保証違反や事業譲渡契約違反が生じた場合に、他方当事者が被った損害等について、補償を受けることができることを定める規定です。
譲受会社の立場からは、譲渡会社の補償範囲について制限を設けずに被った損害等の補償を請求できるよう交渉することが多いと考えられます。
一方、譲渡会社の立場からは、自社の補償額に上限を設けることや補償請求に期間制限を設けることを求めて交渉することが多いと考えられます。
解除
事業譲渡契約についても債務不履行があった場合には契約解除をすることができますが、事業譲渡契約の場合、事業譲渡実行後の契約解除を認めると、その影響が大きいため、事業譲渡の実行前までに限定することが一般的です。
また、解除事由を、重大な契約違反、重大な表明保証違反、重大な遵守事項違反等に限ることも考えられます。
事業譲渡契約書に貼付すべき収入印紙の金額
事業譲渡契約書には、必要な印紙税分の収入印紙を貼付する必要があります。
例えば、譲渡額が1000万円を超え5000万円以下なら2万円、5000万円を超え1億円以下なら6万円分の収入印紙が必要です(印紙税法2条・別表第一・第1号の1)。
この記事のまとめ
事業譲渡契約の記事は以上です。最新の記事に関する情報は、契約ウォッチのメルマガで配信しています。ぜひ、メルマガにご登録ください!
参考文献
橋本副孝他共編『会社法実務スケジュール 新版』新日本法規、2016年