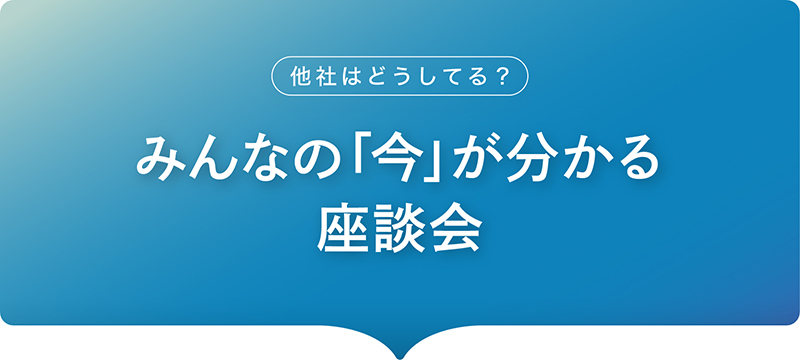著作権とは?
権利の種類・期限・著作権侵害に
ならないケースなどを分かりやすく解説!
| おすすめ資料を無料でダウンロードできます ✅ 著作権研修資料 |
- この記事のまとめ
-
著作権とは、著作物の利用に関して、著作物を創作した者(著作者)に認められた権利をいいます。著作権に関係するルールは、著作権法に定められています。
著作権は、著作物を創作したときから自動で発生します(これを無方式主義といいます)。一方、知的財産法の仲間である特許法などは、権利を取得するには、特許庁の審査にパスすることが必要であり、この点が著作権法と異なります。
著作権には、複製権や公衆送信権をはじめとして、著作権法に基づくさまざまな権利が含まれています。他人の著作権を侵害した場合、差止請求や損害賠償請求、刑事罰の対象になり得るので要注意です。
今回は著作権について、分かりやすく解説します。
※この記事は、2023年2月14日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。
目次
著作権とは
著作権とは、著作物の利用に関して著作物を創作した者(著作者)に認められた権利をいいます。
著作権の主な目的は、著作者がもつ権利を保護するとともに、著作物の公正な利用を確保することで、文化の発展に貢献することです。
自分が創作したものについて、他人が勝手に利用してよい状態だと、創作者の利益が侵害され、創作意欲が失われてしまいます。
例えば、漫画の海賊版サイトが法的に許された場合、漫画家は自分で創作した漫画を有料で販売する一方で、海賊版サイトでは無料で読めるという状態になります。こうした場合、多くの人は、無料で読める海賊版サイトを利用するため、創作者である漫画家には利益が入らないことになります。その結果、漫画家は「書いても無駄だ」と創作意欲を失い、文化も発展しなくなってしまいます。
著作権の発生要件|無方式主義
著作権は、著作物が創作された時点で自動的に発生します(著作権法17条2項、51条)。
「創作」といえるためには、誰にも思いつかないような高度な独創性は必須でないものの、作成者の何らかの個性が表現されている必要があります。
また、特許権や商標権などとは異なり、著作権の発生に法律上の手続きなどは必要ありません。これを「無方式主義」といいます(特許権や商標権などは「方式主義」)。
著作権で保護される「著作物」の例
著作権によって保護される「著作物」とは、思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するものをいいます(著作権法2条1項1号)。
①思想または感情を含むこと
②創作したものであること
③表現したものであること
④文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するものであること
著作権法10条1項各号では、以下の著作物が例示されています。
| 分類 | 具体例 |
|---|---|
| 言語の著作物 | 小説、脚本、論文、講演、歌詞、俳句 |
| 音楽の著作物 | 曲、歌詞 |
| 舞踊・無言劇の著作物 | 日本舞踊、バレエ、ダンスの振り付け |
| 美術の著作物 | 絵画、版画、彫刻 |
| 建築の著作物 | 宮廷建築 |
| 図形の著作物 | 設計図、地図 |
| 映画の著作物 | 劇場用映画、テレビ番組、ゲームソフト、YouTube動画 |
| 写真の著作物 | ポートレート写真、風景写真、報道写真 |
| プログラムの著作物 | PCアプリ、スマホアプリ |
著作権の保護期間|原則として著作者の死後70年
著作権法による著作物の保護期間は、原則として、著作者の死亡した年の翌年以降70年が経過するまでです(著作権法51条、57条)。
(例)著作物が1910年3月1日に創作され、著作者が1930年3月1日に死亡した場合
→著作物の保護期間は1910年3月1日から2000年12月31日まで
共同著作物については、最後まで残った共同著作者の死後70年が経過するまで、著作権が存続します。
ただし、以下の例外が設けられています。
(a)無名または変名の著作物の保護期間
→原則として、著作物の公表後70年が経過するまで著作権が存続します(同法52条)。
(b)団体名義の著作物の保護期間
→原則として、著作物の公表後70年が経過するまで著作権が存続します(同法53条)。
(c)映画の著作物の保護期間
→原則として、著作物の公表後70年が経過するまで著作権が存続します(同法54条)。
(d)ベルヌ条約の加盟国等を本国とする著作物
→本国における著作権の存続期間が、日本の著作権法に基づく存続期間よりも短い場合は、本国の存続期間が適用されます(同法58条)。
著作権の分類|著作権(財産権)と著作者人格権
(広義の)著作権は、財産権としての(狭義の)著作権と、著作者人格権の2つに大別されます。
①財産権としての著作権
著作者の財産的な利益を保護する権利です。後述するように、さまざまな種類の権利が含まれています。第三者に対する譲渡も可能です(著作権法61条1項)。
②著作者人格権
著作者の人格的な利益を保護する権利です。「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」の3つが認められています(同法18条~20条)。著作者人格権は、第三者に譲渡することができません(同法59条)。したがって、財産権としての著作権を第三者に譲渡した場合でも、著作者人格権は著作者に残ります。
以降では、財産権としての著作権を、単に「著作権」と呼称して解説します。
著作権に含まれる権利の種類
著作権には、以下の権利が含まれています。著作権者は、各権利によって保護された行為を独占的に行うことができるほか、当該行為を第三者に対して許諾して、ライセンス料を収受することが可能です。
①複製権(著作権法21条)
→著作物のコピーを作成する権利です。
例:漫画の出版(原稿を複製し印刷している)
②上演権、演奏権(同法22条)
→著作物を公に上演し、または演奏する権利です。
上演の例:漫画の舞台化
演奏の例:楽曲をライブハウスで歌う
③上映権(同法22条の2)
→著作物を公に上映する権利です。
例:市販のDVDをカフェなどで流す
④公衆送信権・公衆伝達権(同法23条)
→インターネットなどを通じて、著作物を公に送信する権利です。
公衆送信の例:テレビやラジオで、映画を流す
公衆伝達の例:ライブ配信で、新聞記事を映し配信する
⑤口述権(同法24条)
→言語の著作物を公に口述する(読み聞かせる)権利です。
例:詩をイベントで朗読する
⑥展示権(同法25条)
→美術の著作物または未発行の著作物を、オリジナルによって公に展示する権利です。
例:原画展を行う
⑦頒布権(同法26条)
→映画の著作物を複製物(配信動画、ブルーレイディスクなど)によって頒布する権利です。
頒布の例:映画のブルーレイディスクを販売する
⑧譲渡権(同法26条の2)
→著作物(映画の著作物を除く)を、著作物そのものと著作物を所有する権利の両者を移転する権利です。
譲渡の例:絵画を販売する
⑨貸与権(同法26条の3)
→著作物(映画の著作物を除く)の所有権は著作者においたまま、著作物を貸す権利です。
貸与の例:漫画のレンタルサービス
⑩翻訳権、翻案権等(同法27条)
→著作物を翻訳・編曲・変形・脚色・映画化し、二次的著作物を創作するする権利です。
翻案の例:小説を映画化する
⑪二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(同法28条)
→原著作物を基に創作された二次的著作物(例:小説が原作のアニメ)につき、原著作者が保有する権利です。原著作者は、二次的著作物の著作者と同一の権利を専有します。
著作権侵害の要件
著作権侵害が成立するのは、以下の要件が全て満たされている場合です。
①オリジナルが著作物であること
②直接侵害またはみなし侵害に該当すること
③著作権が制限される場合でないこと
④故意または過失(差止請求については不要)
オリジナルが著作物であること
まずは、オリジナルの創作物が著作物である必要があります。
著作物として保護されるためには、作成者の思想または感情が創作的に表現されている必要があります。これを「著作物性」または「創作性」といいます。
著作物性(創作性)が認められるためには、作成者の何らかの個性が表現されていなければなりません。短文で自由度が低すぎる場合や、ありふれた表現しか用いられていない場合などには、著作物性(創作性)が認められない可能性が高いです。
直接侵害またはみなし侵害に該当すること
著作権侵害は、「直接侵害」と「みなし侵害」の2つに大別されます。著作権侵害の成立には、直接侵害とみなし侵害のいずれかが発生していることが必要です。
直接侵害とは
「直接侵害」とは、著作権に含まれる権利(詳細は「著作権に含まれる権利の種類」参照)によって保護されている行為を、当該著作物に依拠した上で、著作権者に無断で行うことをいいます。
なお、直接侵害の成立には「依拠」が必要であり、偶然似たような著作物を創作してしまった場合などには、直接侵害は成立しません。
また、パロディ(翻案)がオリジナルの著作物の無断利用であるか否かは、パロディを見た際にオリジナルの表現上の本質的な特徴を直接感得できるか否かによって判断されます(最高裁平成13年6月28日判決)。
みなし侵害とは
「みなし侵害」とは、著作権に含まれる権利によって直接保護されてはいないものの、実質的に見て著作権侵害として取り扱うべき行為について成立します。
具体的には、以下の行為がみなし侵害に該当します(著作権法113条)。
①国内で行われたとすれば著作権侵害に当たる行為により作成された物を、国内において頒布する目的で輸入する行為
②著作権侵害行為により作成された物につき、著作権侵害であると知りながらする以下の行為
・頒布
・頒布目的所持
・頒布申出
・業としての輸出
・業としての輸出目的所持
③リーチサイト・リーチアプリに対し、侵害コンテンツのリンクを提供する行為
④リーチサイト・リーチアプリを提供する行為
⑤著作権侵害であると知りながら海賊版プログラムのライセンスを取得し、業務の一環としてコンピュータにインストール・使用する行為
⑥コピーガードを不正に解除する行為
⑦コピーガードを解除するパスワードを、公衆に対して譲渡・貸与等する行為
⑧著作物の権利管理情報を改ざんする行為
⑨権利管理情報が改ざんされた著作物またはそのコピーを、情を知って頒布等する行為
⑩国内盤CDが発行されてから4年以内に、国外盤CDを輸入・国内頒布し、または頒布目的で所持することにより、著作権者・著作隣接権者の利益を不当に害する行為
⑪著作者の名誉・声望を害する方法によって著作物を利用する行為
著作権が制限される場合でないこと
著作物であっても、一定の場合には、著作権が制限されます。
具体的には、以下の場合などには著作権が制限されており、著作権侵害が成立しません。
①私的使用目的の複製(著作権法30条)
②付随対象著作物(「写り込み」部分など)の利用(同法30条の2)
③図書館等における複製・記録・提供(同法31条)
④引用(同法32条)
⑤教科用図書等への掲載等(同法33条~33条の3)
⑥学校教育番組の放送・教材掲載(同法34条)
⑦学校などの教育機関における複製・公衆送信(同法35条)
⑧試験問題としての複製・公衆送信(同法36条)
⑨視覚障害者・聴覚障害者等のための複製等(同法37条、37条の2)
⑩営利を目的としない上演等(同法38条)
など
故意または過失|差止請求については不要
著作権侵害を理由として、侵害者に対する損害賠償請求を行うためには、侵害者の故意または過失を立証しなければなりません(民法709条)。
なお、侵害行為の差止請求を行う際には、侵害者の故意・過失は要件とされていませんので、立証不要です。
著作権侵害にならないケースとは
他人が作ったコンテンツを利用するケースでも、以下のいずれかに該当する場合には、著作権侵害に該当しません。
①利用したコンテンツが著作物ではなかった場合
②著作物であっても著作権がない場合
③権利者から著作物利用の許諾を得た場合
④著作権の譲渡を受けた場合
⑤許諾を得ることなく利用できる場合
利用したコンテンツが著作物ではなかった場合
利用したコンテンツに著作物性(創作性)がない場合、そのコンテンツは著作物として保護されないため、著作権侵害は成立しません。
例えば短文で自由度が低すぎる場合や、ありふれた表現しか用いられていない場合などには、コンテンツの著作物性(創作性)が否定される可能性があります。
著作物であっても著作権がない場合
著作物であっても、著作権が認められない場合には、無断利用について著作権侵害が成立しません。
具体的には、著作権の保護期間が切れたコンテンツのほか、以下の著作物が著作権による保護の対象外とされています(著作権法13条)。
①憲法その他の法令
②国・地方公共団体の機関・独立行政法人・地方独立行政法人が発する告示・訓令・通達その他これらに類するもの
③裁判所の判決・決定・命令・審判、および行政庁の裁決・決定で裁判に準ずる手続きにより行われるもの
④①~③に掲げるものの翻訳物・編集物で、国・地方公共団体の機関・独立行政法人・地方独立行政法人が作成するもの
権利者から著作物利用の許諾を得た場合
著作権者から利用の許諾を受けた著作物については、その利用について著作権侵害が成立しません。
ただし、許諾の範囲を超えて著作物を利用した場合は、著作権侵害が成立します。
著作権の譲渡を受けた場合
著作権は、第三者に対する譲渡が認められています(著作権法61条1項)。著作権の譲渡を受けた場合、著作物を利用する権利を独占するため、当該権利に従って著作物を利用できます。
許諾を得ることなく利用できる場合
前述のとおり、著作権が制限される場合については、著作権者の許諾を得ることなく著作物を利用できます。
著作権が制限される場合の代表例は、私的使用目的の複製(著作権法30条)・引用(同法32条)などです。ただし引用については、出所の明示(同法48条)など一定の要件を満たす必要があります。
他人の著作権を侵害した場合のリスク
他人(他社)の著作権を侵害した場合、侵害者は以下のリスクを負うことになります。
- 差止請求を受ける
- 損害賠償請求を受ける
- 刑事罰を受ける
いずれも会社にとって重大な悪影響をもたらし得るので、著作権侵害を犯さないようにチェック体制を強化しましょう。
差止請求を受ける
著作権者は、著作権を侵害する者または侵害するおそれがある者に対し、侵害の停止または予防等を請求できます(著作権法112条)。これを「差止請求」といいます。
差止請求を受けた場合、侵害行為に関連して販売・配信中の商品やコンテンツの回収を強いられ、会社の業績に大きな悪影響が生じてしまうでしょう。
損害賠償請求を受ける
著作権侵害に当たる行為をした場合、著作権者から不法行為に基づく損害賠償を請求される可能性があります(民法709条)。
著作権法114条には損害額の推定規定が設けられており、著作権者の立証負担が軽減されています。侵害者の立場から見れば、通常の不法行為よりも損害賠償責任が認められやすくなっているので要注意です。
刑事罰を受ける
著作権侵害を犯した者には、最大で「10年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金」が科されます(著作権法119条1項)。
法人の代表者・代理人・使用人その他の従業者が行為者の場合、法人にも最大で「3億円以下の罰金」が科されます(同法124条1項1号)。
この記事のまとめ
著作権の記事は以上です。最新の記事に関する情報は、契約ウォッチのメルマガで配信しています。ぜひ、メルマガにご登録ください!
| おすすめ資料を無料でダウンロードできます ✅ 著作権研修資料 |