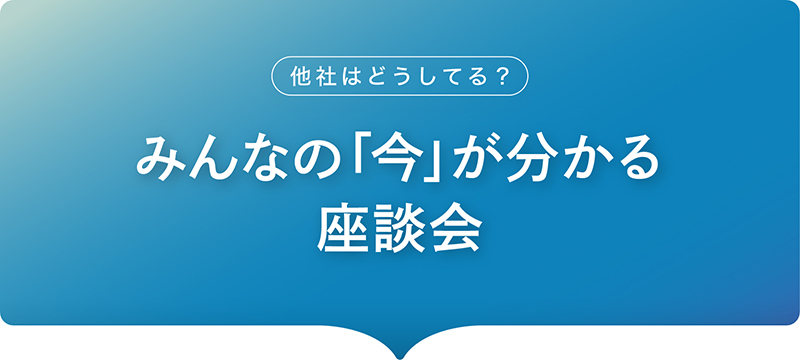特許法とは?
基本を分かりやすく解説!
| おすすめ資料を無料でダウンロードできます ✅ 知財担当者が押さえておきたい法令のまとめ |
- この記事のまとめ
-
特許法は、発明の保護と利用を図ることにより、発明を促し、産業の発展に貢献することを目的とする法律です。
主に、発明を特許と認めてもらうための要件・手続や、特許権の効力、特許権が侵害された場合の法律関係について規定しています。
この記事では、特許法の知識がない方にも基本から分かりやすく解説します。
※この記事は、2022年9月7日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。
目次
特許法とは
特許法とは、発明の保護と利用を図ることにより、発明を促し、産業の発展に貢献することを目的とする法律です。
そもそも特許とは、発明を公開する代わりに、その発明の実施を独占できる制度です。
- 実施とは
-
一般的に「実施」とは、「あることを実行すること」といった意味で使用されます。
しかし、特許法とセットで使われる場合の「実施」は、特許法にて定義がされている法令用語であり、主に以下のような意味をもちます。「物の発明」の場合|特許対象の物を生産・使用・譲渡・輸出・輸入する等の行為
「方法の発明」の場合|特許対象の方法を使用する行為
「物を生産する方法の発明」の場合|特許対象の物の生産方法により物を生産したり、その方法により生産した物を使用・譲渡・輸出・輸入したりする等の行為
※より詳細には、「特許権の効力」で説明しています。
特許権は、特許庁へ特許出願をして、審査の結果、発明が特許として認められたうえ登録されてはじめて取得できます。(特許権をもつ者のことを、特許権者といいます。)
特許権者は、特許の実施を独占できるため、他人が自らの特許を無断で実施した場合、使用の差止めや損害賠償等を請求することができます(特許法100条、民法709条)。
なお、特許法と同様の目的をもつ法律として実用新案法があります。
特許法と実用新案法では、特許法が「発明」(自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの)を保護対象とするのに対し、実用新案法は「考案」(自然法則を利用した技術的思想の創作)を保護対象としています。
つまり、実用新案法は、「発明」から「高度のもの」という要件がかけた対象を保護対象としており、「小」発明を保護しているといえます。
特許法の目的
特許法の目的は、「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与すること」です(特許法1条)。
発明は情報なので、有体物(形のあるもの)と異なり、誰か1人しか利用できないものではありません。このため、誰もが他人の発明を自由に利用できる状態だと、発明者は経済的利益を得ることが難しくなり、新たな発明をする意欲ももてません。
また、そのような状況では、発明者は、自分の発明を他人に利用され利益を奪われることをおそれ、発明を隠すようになります。その結果、他人がその発明を知る機会が失われることになり、産業の発展が妨げられてしまいます。
そこで、特許法は、発明者に一定期間独占的に発明を実施する権利を与え(「発明の保護」)、発明のインセンティブを与えるとともに、発明を公開することで他者による「発明の利用」を可能とすることで、産業の発展に貢献することを目的としているのです。
特許法の保護対象となる「発明」とは
発明の要件
「発明」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」をいいます(特許法2条1項)。
発明の要件として、以下の4つがあります。
①自然法則の利用をしていること
例えば、万有引力の法則等の自然法則それ自体、ゲームのルール等の人為的な取決め、数学の公式等は、自然法則を利用しているとはいえないため、「発明」にあたりません。しかし、例えば「万有引力の法則を利用して、何らかの装置などを開発した」といった場合には、発明にあたります。
②技術的思想があること
「技術」とは一定の課題を解決するための具体的手段であり、実施可能であり、当該技術分野における通常の知識を有する者が行えば同じ結果を得ることができることが必要とされています。
このため、スポーツの技能等の個人の技能によるものや、情報の単なる提示は、「技術的思想」とはいえず「発明」にあたりません。
③創作性があること
例えば、単に天然物を発見しただけでは、「創作」したとはいえず「発明」にあたりません。
④高度性があること
本要件は、「特許法とは」に記載のとおり実用新案の対象である「考案」(実用新案法2条1項)と区別するために設けられたにすぎない要件です。実務上、「高度」ではないという理由で「発明」に該当しないと判断されることはないとされています。
発明の種類
「発明」は、①「物の発明」と②「方法の発明」に分類され、さらに②「方法の発明」は②-1「方法の発明」と②-2「物を生産する方法の発明」に分類されます。
| 発明の種類 | 例 | |
|---|---|---|
| ① | 物の発明(特許法2条3項1号) | 機械や装置、化学物質等 |
| ②-1 | 方法の発明(特許法2条3項2号) | 測定方法、通信方法等 |
| ②-2 | 物を生産する方法の発明(特許法2条3項3号) | 薬の製造方法、製品の製造方法等 |
特許を取得するための要件|特許を受けることができる発明とは
「発明」の全てが特許を受けることができるわけではなく、「特許」を受けるためには、「発明」が特許要件を満たすことが必要です。以下、特許を取得するための要件について説明します。
「発明」が「特許」を受けるためには、
①産業上、利用できること
特許法の目的は「産業の発達」への貢献にありますので、産業上利用可能であることが特許の要件です(特許法29条1項柱書)。
ここでいう産業とは、工業に限らず、農業・運輸業・交通業など幅広い業種を指しており、これらの業種において利用できる発明であることが、特許要件の一つです。
②新規性があること
既に誰もが知っているような発明に特許権という独占権を付与することは「産業の発達」に貢献しないため(むしろマイナスであるため)、特許権が認められるためには、発明が新しいもの(新規性を有するもの)であることが必要です(特許法29条1項)。
なお、新規性が認められない場合でも、一定の要件を満たせば、例外的に救済を受けられる可能性もあります(特許法30条)。
③進歩性があること
既に知られている発明を少し改良しただけの発明に、特許権という独占権を付与することは「産業の発達」に貢献しませんので(むしろマイナスですので)、特許を受けるためには、「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者」が容易に思いつかないこと(進歩性)が必要です(特許法29条2項)。
④他人に先に出願されていないこと
別々の発明者が「同じ発明」について、それぞれ特許庁に出願した場合、先に発明した者ではなく、先に出願した者が特許を受けることができます(先願主義、特許法39条)。
具体的には、「出願日」に基づき、どちらが先に出願したかを判断します。
⑤特許を受けることができない発明に該当しないこと
「公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明」は、特許を受けることができません(特許法32条)。
「特許・実用新案審査基準」では、特許を与えるべきではないと考えられる発明の例として、遺伝子操作により得られたヒト自体や専ら人を残虐に殺戮することのみに使用する方法が挙げられています。
特許を取得できる者とは
次に、誰が特許を取得できるかについて説明します。
特許を取得できる者は、
に限られます。
特許を受ける権利をもたない者が出願したとしても、特許権は認められません(特許法49条7号)。
発明者
まず、「発明者」とは、当該発明について、その具体的な技術手段を完成させた者をいうとされています。例えば、単なる補助をしただけの者、助言をしただけの者、資金の提供をしただけの者、命令をしたに過ぎない者は発明者にはあたらないと考えられています。
職務発明
職務発明とは、従業員が、使用者(会社など)の業務命令に基づき、職務の一環として行った発明のことです(特許法35条1項)。
会社の従業員が生み出した発明については、会社と従業員のどちらに特許を受ける権利が帰属するかが問題となります。この問題を解決するため、特許法には「職務発明」に関する規定が設けられているのです(特許法35条)。
発明は本来、発明者のものですが、職務発明については、会社も資金や設備の提供をすることで発明に貢献していることから、会社に無償の(法定)通常実施権を認めています。(特許法35条1項)
- 通常実施権とは
-
通常実施権とは、特許権者との合意により定めた範囲内で、特許発明を業として実施できる権利のことです(特許法78条)。
従業員の職務発明について、会社が取得する通常実施権は、特許権者(職務発明でいえば、従業員)の意思にかかわりなく発生するため、法定通常実施権といわれています。
※通常実施権について、より詳細には、「通常実施権」で説明しています。
ただし、職務発明規程で会社に特許を受ける権利を取得させると定めたときは、発明の発生時から特許を受ける権利は会社に帰属します(同条2項・3項)。(逆をいえば、こうした定めがなければ、職務発明に係る特許を受ける権利は従業員に帰属します。)
職務発明規程で会社に特許を受ける権利を取得させたときは、従業員は、その発明に対する貢献の対価として、「相当の利益」を受ける権利を有します(特許法35条4項)。
「相当の利益」の金額について、職務発明規程で定める場合には、「使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況」等が考慮されますが(同条5項)、この考慮すべき状況等に関しては、以下のとおり指針が定められています。
出願から特許権取得までの流れ
それでは、次に特許権を取得するまでの流れについて説明します。
特許審査の流れ
特許庁における審査の流れの全体像は以下のとおりです。
- 特許審査の流れ
-
①先行技術調査
②特許出願(出願書類の作成・提出)
③方式審査
④出願審査請求(出願審査請求書を作成・提出)
⑤実体審査
⑥特許査定
⑦特許権の設定の登録(特許権が発生)※特許権の取得までにかかる期間は、「特許行政年次報告書2021年版」によると、平均して15.0か月(2020年度)となっています。
①先行技術調査
特許を出願する前に、先行技術調査を行うことが望ましいです。先行技術調査を行う際には、独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)が提供する、「J-PlatPat」を活用することができます。
②特許出願(出願書類の作成・提出)
先行技術調査の結果、問題がなさそうであれば、特許出願に進みます。
特許出願の際には、「特許願(願書)」の他、「明細書」、「特許請求の範囲」、「要約書」、「図面」等を提出する必要がありますが、これらの出願書類の作成は専門家でないと困難なことが多いので、弁理士に依頼することが多いです。
特許出願の出願書類の様式や、作成の方法については、以下の特許庁のウェブサイトに詳細な説明があります。
③方式審査
特許出願がされると、出願が法令で定める形式的な要件を満たしているかの審査(方式審査)が行われます。
方式審査の結果、不備がある場合には、補正(出願内容の補足や訂正)が命じられ(特許法17条3項)、これに対し、出願人が適切な補正をしないと出願手続が却下されます(特許法18条)。
方式審査の運用基準については、特許庁のウェブサイトに詳細な説明があります。
④出願審査請求(出願審査請求書を作成・提出)
特許庁による方式審査後、出願人が実体審査を望む場合には、出願日から3年以内に出願審査請求を行う必要があります(特許法48条の3第1項)。
この期間内に請求がされない場合には、その特許出願は取り下げたものとみなされますので(特許法48条の3第4項)、注意が必要です。
⑤実体審査
出願審査請求がされると特許庁による実体審査に進みます。実体審査では、新規性や進歩性などの特許要件が認められるかなど拒絶理由(特許法では不合格のことを「拒絶」といいます。特許法49条各号)の有無について審査が行われます。
なお、審査の結果、拒絶理由があると認められても、特許権の取得が永久にできないわけではありません。特許庁より、拒絶理由通知書が出されるので、これに対し、出願人は、意見書の提出や補正等の対応を行うことで、拒絶理由の解消を図ることができます(特許法50条、同法17条の2)。
⑥特許査定
審査の結果、拒絶理由がない(なくなった)と判断された場合、特許査定がされます(特許法51条)。特許査定とは、特許を付与すべきであるという回答がなされたという意味ですが、この時点では、まだ特許権は付与されていません。
⑦特許権の設定の登録(特許権が発生)
出願人が、特許査定の謄本の送達日から30日以内に、1~3年目までの特許料を納付すると、特許権の設定の登録がされ、特許権が発生します(特許法66条1項、同法108条1項)。
特許料が納付されないと、特許出願が却下されてしまいます(特許法18条)。
特許権の存続期間は、特許出願の日から20年ですが(特許法67条1項)、特許出願や出願審査請求から特許権の設定の登録まで長期間かかった場合は延長することができる場合もあります(特許法67条2項、3項)。
「特許権の存続期間」については、以下の関連記事で解説しています。
特許庁の判断を争うための方法
以上の特許庁の審査を経て特許権が発生しますが、特許庁の判断を争いたい(特許庁の判断に不服がある)場合には、どのような対応をとればいいでしょうか。以下主な4つの手続について説明します。
審判
まず、特許庁の審査官が行った拒絶査定や特許査定といった判断は、同じ特許庁内の審判部でその妥当性等について判断してもらうことができます。これが「審判」です。以下は主な審判手続の内容です。
拒絶査定不服審判
拒絶査定を受けた場合、謄本の送達日から3か月以内であれば、拒絶査定不服審判(拒絶査定が本当に適切に行われたかチェックをしてもらうこと)を請求することができます(特許法121条1項)。
無効審判
無効審判は、ある特許発明について、利害関係を有する者が特許の無効を求めることができる審判です(特許法123条)。
例えば他社の特許権が存在するために、自社商品の製品化が困難となっている事業者が、特許要件を満たしていないことなどを理由として、他社の特許権は無効であると請求するケースなどが想定されます。
無効となる理由は特許法123条1項各号に規定されており、特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は初めから存在しなかったものとみなされます(特許法125条)。
訂正審判
特許登録後に、特許権者が願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる審判です(特許法126条)。
他社からある特許発明について、特許の無効を求められそうな場合などに、事前に、特許権者が無効理由を解消する目的で利用することが多い手続です。
訂正事項は、特許法126条1項各号に規定されたものに限定されます。
訂正をすべき旨の審判が確定したときは、訂正後の内容に基づき特許権の設定登録がされたものとみなされます(特許法128条)。
特許異議申立て
特許異議申立てとは、特許掲載公報(特許権の取得を知らせる公報)の発行から6か月間は、特許付与の是非について再審査を求めることができる制度です(特許法113条、114条3項)。
異議申立の理由は特許法113条各号に規定されています。一旦成立した特許権を遡って存在しなかったものとみなす制度である点で無効審判と共通します。
しかし、無効審判では、利害関係のある者しか請求できないのに対し、特許異議申立ては、誰でも申し立てることができる点等が異なります。
「特許異議申立て」については、以下の関連記事で解説しています。
判定
「特許庁の判断を争うための方法」ではありませんが、特許庁が関与する手続に判定制度(特許法71条)があります。
これは、特許権の技術的範囲について、技術の専門家である特許庁に中立・公平な立場から判断をしてもらうことができる制度です。
判定制度は、計画中又は実施中の商品等が、他人の特許発明の技術的範囲に含まれる(他人の権利を侵害する可能性がある)ものであるかどうかを知りたい場合などに活用できます。(特許庁「判定制度の概要」)
審決取消訴訟
これまで解説してきた特許庁の審判の結果(審決)や特許取消決定に不服がある場合には、知的財産高等裁判所に審決を取消してもらうための訴訟(審決取消訴訟)を提起することができます(特許法178条)。
特許権の効力
それでは、次に取得した特許権にはどのような効力が認められるかについて説明します。
特許権を取得すると、特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有します(特許法68条)。ここでいう「実施」とは、以下のとおり、特許法2条3項各号で発明の種類毎に規定されています。
| 発明の種類 | 実施 |
|---|---|
| 物の発明(1号) | その物の生産、使用、譲渡、貸渡し、電気通信回線を通じた提供(プログラムの場合)、輸出、輸入、譲渡・貸渡し・電気通信回線を通じた提供の申出・展示 |
| 方法の発明(2号) | 方法の使用 |
| 物を生産する方法の発明(3号) | 方法の使用、その方法により生産した物の使用、譲渡、貸渡し、電気通信回線を通じた提供(プログラムの場合)、輸出、輸入、譲渡・貸渡し・電気通信回線を通じた提供の申出・展示をする行為 |
特許権の効力の制限
また、特許法上、以下の場合には特許権の効力が及ばないとされています。
| ① | 個人的な実施や家庭内での実施(特許法68条) |
| ② | 試験又は研究のためにする特許発明の実施(特許法69条1項) |
| ③ | 単に日本国内を通過するに過ぎない船舶若しくは航空機等(特許法69条2項1号) |
| ④ | 特許出願時から日本国内にある物(特許法69条2項2号) |
| ⑤ | 医師等の処方せんによる調剤行為・調剤する医薬(特許法69条3項) |
特許権の活用方法
それでは、次に特許権はどのように活用できるかについて説明します。主に、以下の4つの活用方法が想定できます。
自己実施
まず、当然ながら特許権者は特許発明を(他者に実施許諾せず)自分だけが独占的に活用することで利益を上げることができます。
特許権者としては、無断で自己の特許発明を実施する者がいれば、差止請求や損害賠償請求等を行使しつつ、自社による独占的な実施を維持・確保することになります。
ライセンス
次に、特許権者は、他者に特許発明の実施権を許諾等(ライセンス)することで対価を得ることも可能です。
ライセンスの方法は複数あります。以下、他者に許諾する権利としてどのようなものがあるかを、説明します。
専用実施権
専用実施権は、特許権者の意思により設定される実施権で、ライセンス契約等で定めた範囲内で特許発明を独占的に実施することができる権利です(特許法77条)。
専用実施権が設定されると、専用実施権をもつ者は、自ら差止請求権等を行使できるなど(特許法100条等)、後述の「通常実施権」と比較し強い権利を取得することができます。
一方、特許権者は、ライセンス契約などで定めた範囲内では自身も特許発明を実施することができなくなるなどの制限を受けます(特許法68条ただし書)。
なお、専用実施権は、ライセンス契約等で専用実施権を認めることを定めるのにプラスして、特許庁への設定登録をしなければ効力が生じないことに注意が必要です(特許法98条1項2号)。
特許ライセンス契約については、以下の関連記事で解説しています。
通常実施権
通常実施権は、特許権者の意思により設定される実施権で、ライセンス契約等で定めた範囲内で特許発明を実施することができる権利です(特許法78条)。
専用実施権とは異なり、通常実施権の効力の発生のために設定登録する必要はなく、また柔軟に実施権の内容を設定することができるため、実務上もよく活用されています。
一般的には、通常実施権が設定されても、特許権者は、自ら特許発明を実施したり、他者に通常実施権を許諾したりすることも制限されません。
しかし通常実施権でも、
場合もあります。
また、(独占的通常実施権者については争いがありますが、)少なくとも、通常実施権者については、専用実施権者とは異なり、自ら差止請求権等を行使することはできないと考えられています。
法定通常実施権
特許権者の意思にかかわりなく発生する実施権に、法定通常実施権があります。法定通常実施権とは、公益上の必要性や当事者間の衡平を図る観点から、法律上の規定によって発生する実施権です。
「職務発明」で前述した、従業員の職務発明について使用者が取得する実施権(特許法35条1項)が法定通常通常実施権の一つです。
また、よく問題となるものとして、先使用による法定通常実施権(特許法79条)があります。「④他人に先に出願されていないこと」のとおり、特許法には、先願主義というルールがあり、基本は早いもの勝ちです。
しかし、例外的に、特許出願された発明の内容を知らずに同じ発明をした場合等に、先に出願をした者以外の者に対しても、一定の要件のもとで当該発明の実施を認めることがあります。これが、先使用による法定通常実施権です。
裁定通常実施権
裁定通常実施権は、特許権者の意思にかかわりなく、公益上の必要性から、裁定という行政処分によって強制的に設定される実施権です。特許法上、以下の裁定通常実施権が規定されています。
| ① | 不実施の場合の裁定通常実施権(特許法83条) | 継続して3年以上日本国内において特許発明が不実施の場合で、通常実施権の許諾に関する協議が成立しないときに認められます。 |
| ② | 利用関係にある場合の裁定通常実施権(特許法92条) | 特許発明が特許法72条の利用関係にある場合で、通常実施権の許諾に関する協議が成立しないときに認められます。 |
| ③ | 公益上必要な場合の裁定通常実施権(特許法93条) | 特許発明の実施が公共の利益のため特に必要である場合で、通常実施権の許諾に関する協議が成立しないときに認められます。 |
移転(譲渡)
特許権を移転(譲渡)して対価を得ることも可能です。ただし、譲渡による特許権の移転は特許庁への設定登録をしなければ効力を有しない点に注意が必要です(特許法98条1項1号)。
担保権の設定
特許権を担保として資金調達をすることも可能です(特許法95条)。ただし、特許権を担保とするためには、特許庁への設定登録が必要となる点には注意が必要です(特許法98条1項3号)。
共有に係る特許権
特許権は以上のように活用することができますが、特許権が共有されている場合には、以下のとおり特許権の活用にあたり制限が生じる場合がありますので、注意が必要です。
| ① | 特許発明の実施 | 共有者の同意なく自由に実施することが可能(特許法73条2項) |
| ② | 持分の譲渡・質権の設定、 専用実施権・通常実施権の設定 | 共有者の同意がなければ左記の行為をすることができない(特許法73条1項・3項) |
特許権の侵害とは
特許権の侵害とは、第三者が特許権者に無断で、業として特許発明を実施することをいいます。以下では、どのような場合に、特許権の侵害となるのか説明します。
特許権侵害の類型
特許権侵害には、以下の「直接侵害(文言侵害)」、「均等侵害」、「間接侵害」の3つの類型があります。以下詳しく見ていきます。
直接侵害(文言侵害)
直接侵害(文言侵害)は、無断で業として実施された発明が、特許発明として登録されている技術的範囲の構成要件を全て満たす場合に成立します。一方、特許発明の技術的範囲の構成要件を一つでも満たしていない場合、文言侵害は成立しません。
なお、「特許発明の技術的範囲」とは、特許権者の独占的な実施が認められる発明の範囲を意味し、出願時の願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定められています(特許法70条1項)。
均等侵害
均等侵害は、厳密には特許発明の技術的範囲の構成要件を満たしていないものの、実質的には特許発明と同一の発明を実施していると評価できる場合に成立します。
最高裁平成10年2月24日判決では、均等侵害の成立要件として、以下の5点を挙げています。
間接侵害
「直接侵害(文言侵害)」で解説したとおり、特許権の侵害が成立するためには、特許発明として認められた技術的範囲の構成要件を全て満たす必要があります。
しかし、特許発明の技術的範囲の構成要件を全て満たさないとしても、特許権侵害を誘発する可能性が高い行為(=間接侵害)については、特許権によって保護すべき場合があります。
そこで特許法101条は、一定の行為を業としてすることを間接侵害として、特許権侵害に該当すると定めています。
特許権侵害の類型については、以下の関連記事で解説しています。
抗弁
それでは、特許権者から侵害を疑われた者はどのような反論をすることができるでしょうか。以下では、主な抗弁(反論)について説明します。
消尽
消尽とは、特許権者等が、特許発明を利用した製品を適切に流通させた場合、第三者が正当に購入した当該製品を、使用したり、再販売したりしても特許権侵害とならないことをいいます。
特許法上の根拠規定はありませんが、最高裁で認められている理論です。
消尽が認められる場合には、特許権侵害が否定されますので、特許権の侵害を疑われた者としては、反論として消尽を主張することができます。
無効の抗弁
特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者は相手方に対しその権利を行使することができませんので(特許法104条の3第1項)、侵害が疑われた者としては、特許が無効とされるべきものであることを反論として主張することができます。
実施権
「ライセンス」記載の各実施権が認められる場合には、抗弁として主張することができます。例えば、実務上、先使用の法定通常実施権(特許法79条)を抗弁として、特許権を侵害していないという旨を主張する場合があります。
特許権侵害をされたときの対処法
それでは、自己の特許権が侵害された場合、どのような対応をとることができるでしょうか。以下説明します。
特許権侵害に対する民事上の救済措置
差止請求権
特許権者は、自己の特許権を侵害する者・侵害するおそれがある者に対し、侵害の停止・予防の請求(差止請求)をすることができます(特許法100条1項)。
また、差止請求をするに際し、侵害の行為を構成した物や侵害の行為により生じた物の廃棄等、侵害の予防に必要な行為を請求することもできます(特許法100条2項)。
損害賠償請求権
特許権者は、特許権侵害によって損害を被った場合、損害賠償請求をすることもできます(民法709条)。
なお、特許権者の損害額に関する立証負担を軽減するために、特許法には損害額の算定規定が設けられています(特許法102条)。
信用回復措置請求権
特許権者は、特許権侵害により特許権者の業務上の信用を害した者に対して、特許権者の業務上の信用を回復するために必要な措置を請求することができます(特許法106条)。
不当利得返還請求権
特許権者は、無断で自己の特許権を実施する者に対し、不当利得返還請求(民法703条)をすることも可能です。
民事手続の特則
特許権侵害に関する民事裁判においては、通常の民事裁判と比較し、主に以下の特則が設けられています。
| ① | 過失の推定(特許法103条) | 他人の特許権を侵害した者はその侵害について過失があったものと推定されます。 |
| ② | 生産方法の推定(特許法104条) | 物を生産する方法の発明についての特許の場合、その物が特許出願前に日本国内で公表された物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定されます。 |
| ③ | 具体的態様の明示義務(特許法104条の2) | 特許権侵害訴訟の相手方は、特許権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、自己の行為の具体的態様を明らかにする必要があります。 |
| ④ | 書類の提出等(特許法105条) | 裁判所は、当事者に対し、侵害行為や侵害行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命じることができます。 |
| ⑤ | 査証(特許法105条の2) | 裁判所は、立証されるべき事実の有無を判断するために、必要性、蓋然性、補充性、相当性が認められる場合には、査証人に対し、査証(相手方当事者の工場等において必要な資料を収集し裁判所に報告書を提出すること)を命じることができます。 |
| ⑥ | 損害計算のための鑑定(特許法105条の2の12) | 特許権侵害訴訟の当事者は、裁判所が侵害行為による損害の計算をするために鑑定を命じた場合には、鑑定人に対し、必要な事項を説明しなければなりません。 |
| ⑦ | 相当な損害額の認定(特許法105条の3) | 裁判所は、特許権侵害訴訟において、損害の発生は認められるものの、損害額の立証が極めて困難である場合、相当な損害額を認定することができます。 |
| ⑧ | 秘密保持命令(特許法105条の4) | 裁判所は、特許権侵害訴訟において、準備書面等に当事者の営業秘密が記載されている場合、当事者等に対し、秘密保持命令を発することができます。 |
特許権侵害に対する行政上の救済措置
特許権を侵害する物品は関税法上、輸出入してはならない物品とされています(関税法69条の2第1項第3号、同法69条の11第1項第9号)。このため、自己の特許権を侵害する物品が輸出入されている場合、関税法上の手続を経ることで、これらの行為を水際で差し止めることができます。
特許権侵害に対する刑事上の救済措置
特許権侵害は刑事罰の対象にもなっています(特許法196条、特許法196条の2)。このため、自己の特許権を侵害された者は、警察等に刑事告訴(刑事訴訟法230条)や被害相談等をすることができます。
この記事のまとめ
特許法の記事は以上です。最新の記事に関する情報は、契約ウォッチのメルマガで配信しています。ぜひ、メルマガにご登録ください!
| おすすめ資料を無料でダウンロードできます ✅ 知財担当者が押さえておきたい法令のまとめ |