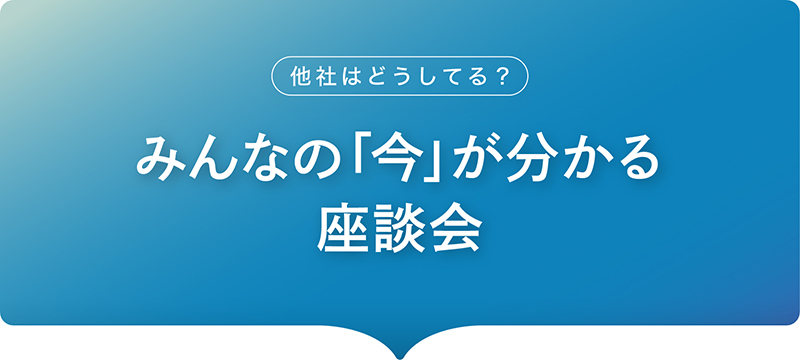企業法務の学び方(2)―コンプライアンス
- この記事のまとめ
-
企業法務を学ぶことの目的は、企業現場で起こるさまざまな事柄に対して適切な問題意識を持つことができるための土台作りにあります。適切な問題意識を持つためには、企業法務という領域が求められるようになった時代背景や歴史的経緯を正しく理解すること、時事問題について感度高く接することが重要です。
第2回は企業のコンプライアンスについて、米国と日本の実務の発展を振り返りつつ、実効的な対応についての理解を深めていきましょう。
この記事では、企業コンプライアンスの考え方の発展の歴史を紐解きながら、企業法務の学び方の手がかりを探っていきます。
※この記事は、2024年6月20日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。
目次
企業コンプライアンスの歴史を学ぶ
コンプライアンスとは
「コンプライアンス(compliance)」という用語は、今では世間でも広く認知されていますが、こうした用語が日本に普及し始めたのは、おそらく2000年代になってのことではないかと思われます。バブル経済崩壊後に発覚した企業不祥事などを経て、企業コンプライアンスの重要性が認識されるようになりました。コンプライアンスは「法令遵守」と訳され、企業が法律、社会倫理、企業倫理などを遵守することを指します。
グローバルベースでみると、「コンプライアンス」という用語は、1960年代ごろから使われはじめたとされています。コンプライアンスを含め、企業法務とは、世界の経済を牽引してきた米国を中心にその基盤が強化され、展開が図られてきた実務領域です。企業法務を語る上では、米国の歴史を紐解くことは欠かせません。
コンプライアンス・プログラムとは
「コンプライアンス」という用語のほかにも「企業倫理(business ethics)」や「インテグリティ(integrity)」のような類似の概念がある中で、なぜ「コンプライアンス」という用語が普及するようになったのかについて疑問に思われた方も少なからずいらっしゃるかもしれません。
「コンプライアンス」という用語が普及するようになったのは、「コンプライアンス・プログラム(compliance program)」という概念が米国の企業実務の中で形成されてきたことと深い繋がりがあると考えられます。
コンプライアンス・プログラムとは、企業が法令遵守を徹底するために導入する社内規程や手続きなどの諸制度のことを指します。コンプライアンス・プログラムと同様の概念として、「内部統制(internal control)」という用語がありますが、コンプライアンス・プログラムと内部統制はいずれも企業組織の統制管理に関する概念であり、コンプライアンス・プログラムは内部統制の一部をなします。
我々が常日頃使っているコンプライアンスという用語は、その起源をたどれば、コンプライアンス・プログラムという企業内部の制度設計を指していたことは、企業法務の実務には、制度を構築・整備していく要素が強いことを暗示するものと捉えられます。
プリンシパル=エージェント関係で捉えるコンプライアンス・プログラム
前回の記事では、企業法務はプリンシパル=エージェント関係の経済モデルに立ち返ることでその本質を見極めることができることに触れましたが、コンプライアンスという実務は、企業というプリンシパルが、役職員その他の会社関係者(エージェント)に対して法令遵守を求めるための諸制度・仕組み(コンプライアンス・プログラム)を整備・構築していくことに、そのエッセンスがあると捉えることができます。
コンプライアンス・プログラムの実務は、企業内部において法令遵守のための教育、管理、監視体制を強化するという文脈を超えて、規制当局との間での協力関係を構築し、法令違反の摘発に共同で当たっていくという考え方をベースとして発展している点にその大きな特徴が見出されます。
規制当局は、法令違反に対して厳罰の姿勢で臨む一方で、法令違反を自主的に開示し、規制当局に協力的な姿勢で臨んだ企業に対しては、罰金を減免するというアメとムチの政策を導入することで、企業組織における法令遵守へのインセンティブを高めていきたいと考えます。そこでは、規制当局はプリンシパルであり、企業はエージェントであると理解されます。
規制当局が示したコンプライアンス・プログラムについて、各企業は、今度は、自らをプリンシパルとして、エージェントである役職員、取引先等の企業関係者に対して、法令遵守のために、懲戒規程の導入や内部通報制度の設置などの各種施策を実施していきます。
コンプライアンス・プログラムの歴史
ここで米国におけるコンプライアンス・プログラムの歴史を紐解いてみましょう。米国において、コンプライアンス・プログラムの概念が普及しはじめたのは1960年代に遡るとされています。企業オペレーションが拡大し、複雑さを増すにつれ、企業の内部的な監視体制を制度化していく必要性が高まりました。ただ、当時のプログラムは、今日におけるコンプライアンス・プログラムと比較しても、極めて簡素なものでした。企業の法務部門が人事部門や内部監査部門と共同する形で細々と管理されていました。
コンプライアンス・プログラムは、さまざまな事件や法律の制定・改訂などを契機として、次第に拡充されていきます。
1960年代には、電機産業におけるカルテル事案の中で、訴追を受けたGeneral Electric(GE)が、コンプライアンス・プログラムを導入していることを防御(defense)の主張として取り上げました。GEの防御は成功しなかったものの、かかる事件を契機に、コンプライアンス・プログラムの考え方が一般に浸透するようになりました。規制当局は、企業の違反行為が意図的ではなく過失であることの判断の際に、コンプライアンス・プログラムの導入を考慮する立場をとるようになりました。
1977年に制定された海外腐敗行為防止法(Foreign Corrupt Practices Act:FCPA)が、企業に対して贈賄行為を予防するための内部統制の確立を義務付けたことは、コンプライアンス・プログラムの考え方がさらに浸透する契機となりました。
1980年代になると、コンプライアンス・プログラムのスタイルはさらに劇的に変化します。防衛産業と国防総省の癒着問題に端を発して1986年に民間団体により制定されたビジネス倫理および行動に関する防衛産業イニシアチブ(Defense Industry Initiative on Business Ethics and Conduct)を契機に、企業の取引を監視する仕組みのあり方がより詳細に議論されるようになりました。
この防衛産業イニシアチブは、防衛産業の請負業者の国防総省との契約に関する活動を監視するための行動規範として定められたものですが、その中でも画期的だったのは、自主的な開示の概念を導入したことでした。企業組織の中で法令違反、またはそのおそれが発覚した場合には、当局に対して自主的に違反を申告することが適切な不祥事対応であるという考え方が生まれました。
1991年連邦量刑ガイドライン(United States Organization Sentencing Guideline)
米国におけるコンプライアンス・プログラムの制度化に向けた取り組みは、1984年の量刑改革法(Sentencing Reform Act of 1984)に基づき1991年に制定された量刑ガイドライン(Sentencing Guideline)によってさらなる進化を遂げ、米国企業の企業倫理強化に向けた取り組みに大きな影響を与えました。
そこでは、企業が法令遵守のためのコンプライアンス・プログラムを制定・実施している場合には、法令違反で有罪判決を受けたときも、コンプライアンス・プログラムの有効性が評価されれば罰金の量刑が減額されるというメカニズムが確立されました。
例えば、米国の外国公務員に対する贈賄行為を取り締まるFCPAを巡っては、2000年代に入ってから、米国の証券取引委員会や司法省による法執行が急速に増大しましたが、そこでは量刑ガイドラインの考え方に基づき、違反企業に対してコンプライアンス・プログラムの整備を要求するかわりに、訴追の延期や免除を行うといった法運用が一般的に行われるようになりました。コンプライアンス・プログラムの整備に積極的な企業に対しては罪を減免し、そうでない企業に対しては高額の罰金を課すという実務が一般化するようになりました。
コンプライアンス・プログラムは実効性のある有効なプログラムであることが求められます。法令遵守の基準と手続き、上級管理職である責任者の任命、規定に基づく懲罰や教育啓発が実際に行われている必要があります。法令違反に対する情報開示など、捜査への協力の要素も評価の対象となります。
日本におけるコンプライアンス・プログラム
米国におけるコンプライアンス・プログラムの考え方は、日本企業におけるコンプライアンス・プログラムの導入にも影響を与えました。その契機となったのが、1987年に、東芝機械が、外国為替及び外国貿易管理法(外為法)に違反し、輸出禁止対象であった工作機械を輸出した「ココム事件」です。
同事件は米国で大きく政治問題として取り上げられ、東芝グループ製品の輸入禁止などに発展しました。ココム事件を契機に、日本企業にもコンプライアンス・プログラムの制定が必要だとの声が高まりました。海外事業を行うメーカーや商社が、外為法に基づく輸出管理を対象としたコンプライアンス・プログラムを制定し、当時の通商産業省に届け出る体制が整備されました。
日本におけるコンプライアンスの実務は、企業において起こった度重なる不祥事の経験を通じて、次第に整備されていきました。不祥事の原因を解明していくなかで、経営トップ自身のコンプライアンス意識の欠如がしばしば問題となりました。経営トップがコンプライアンスを徹底する決意をメッセージとして企業組織に浸透させることの重要性が認識されるようになりました。役職員の活動を規律するための内部統制を整備し、内部通報制度の設置などを通じた監視の仕組みを強化することが、企業法務の実務として一般化するようになりました。
企業不祥事対応とその予防
不幸にして企業不祥事が起こってしまった場合、不祥事対応としてはどのような取り組みが求められるのでしょうか。日本のかつての企業不祥事を見てみると、企業不祥事に関わった役職員は、会社に対する忠誠心が高いゆえに、会社のためにやむをえず違法な行為を行ってしまったのだと理解されたケースも少なくなかったように思われます。
当該不祥事が発覚した場合、企業は対外的には謝罪の意を示しながらも、企業組織の中では、違反者には必ずしも厳罰を加えることなく、むしろ違反者を守っていこうとする傾向が少なからずあったものと思われます。
しかし、度重なる重大な不祥事事例の教訓と、その共有を通じて、企業を取り巻く規範意識は大きく変容しました。不幸にして企業不祥事が起こった場合には、迅速に事案を公表し、調査対応を行い、再発防止策を策定すべきことが重要視され、隠蔽に対しては社会的なサンクションを課していくような社会基盤が確立されていきました。社会規範・企業倫理・インテグリティの重要性が企業において厳格に求められるようになったのです。
上場会社における不祥事対応のプリンシプル
2016年に日本取引所自主規制法人は、「上場会社における不祥事対応のプリンシプル」を策定し、不祥事に直面した上場会社に強く期待される対応や行動に関する原則(プリンシプル)を策定しました。
そこでは、抽象的で大掴みな原則(プリンシプル)を提示し、関係者がその趣旨・精神を互いに共有した上で、各人が実態に応じて自律的に解釈・判断し行動することを促すプリンシプル・ベースのアプローチが採用されています。
不祥事への具体的な対応は各社の実情や不祥事の内容に即して行われるべきものであり、全ての不祥事に対して一律の基準(ルール・ベース)によって規律することは馴染まないものと考えられます。プリンシプルが上場会社において共有され、それに沿った不祥事対応が広がり適切な実務慣行が醸成されることを通じて、不祥事を起こした上場会社の信頼回復および企業価値再生が的確に図られることが期待されています。 具体的には、以下のような対応が期待されます。
- 不祥事対応のプリンシプル
-
(1) 必要十分な調査範囲を設定の上、その背景等を明らかにした確実な事実認定の下、最適な調査体制を構築し、根本的な原因解明に努めること。
(2) 内部統制の有効性や経営陣の信頼性に相当の疑義が生じている場合、企業価値の毀損が大きい場合、複雑または社会的影響が重大な事案などの場合には、調査の客観性・中立性・専門性を確保するため第三者委員会の設置を委員の選定プロセスを含め検討すること。
(3) 根本原因に即した実効性の高い再発防止策を迅速・着実に実行し、不祥事に関する情報開示を迅速かつ的確に実行すること。
上場会社における不祥事予防のプリンシプル
日本取引所自主規制法人は、さらに2019年11月に、事前対応としての不祥事予防の取り組みを促す「上場会社における不祥事予防のプリンシプル」を策定しました。
不祥事予防のプリンシプルは、不祥事対応のプリンシプルと同様、抽象的で大掴みな原則(プリンシプル)を示しています。企業がプリンシプルの趣旨・精神を互いに共有した上で、各人が実態に応じて自律的に解釈・判断し行動することが求められます。
過去の教訓事例などを通じて、企業不祥事への対応力という観点からは、以下の点を企業として常に点検しながら、高い企業倫理の醸成を図っていくことが必要だと考えられています。
- 不祥事予防のプリンシプル
-
(1) 経営陣のメッセージが正しく従業員に伝わっているか(企業風土の問題)
(2) 万が一不祥事が発生した場合に迅速に問題を解決し、再発防止に結びつける自浄能力があるか(自浄能力の問題)
(3) 経営者の保身等が健全な企業経営を妨げてはいないか(公正な対応の問題)
など
コンプライアンスの学び方
コンプライアンスの実務を学ぶに当たっては、この記事で紹介したように、現代型のコンプライアンス・プログラムがどのような歴史的な経緯で発展を遂げてきたのかの歴史認識を深めると、コンプライアンスについての、より高い感度での理解が得られると私は考えています。
米国の歴史を紐解くと、企業不祥事を契機に、企業内部の不正監視の仕組み作りが少しずつ導入され、その実効性を高めるために、自主開示を促す実務が開発されました。そうした実務が、高額で複雑な減免を伴う罰金制度とセットになって、コンプライアンス・プログラムとして確立されていったのです。さらに現代では、自主開示を促進するため内部通報制度が整備されるようになりました。内部通報制度については、第3回の内部統制の記事で触れていきたいと思います。
我々は、コンプライアンス・プログラムについて、今後さらにどのように発展・進化させていくべきかについて深く考察し、答えを導き出すことが求められています。新たな不祥事や課題に直面した際に、コンプライアンス・プログラムが制度として発展してきた過程を振り返り、しっかりと向き合えるような意識をもって、コンプライアンスについて学んでいくことが大切です。
最近では、個人情報の漏洩、食品異物混入、メーカー製品品質不正(不正検査)の事件などがメディアを賑わせています。メディアで取り上げられる事件について、なぜそのような事件が起こったのか、そしてどのような再発防止策が求められているのかについて、情報を参照しながら考察していくことが求められます。
その際には、日本経済新聞などの記事にアクセスし事件の背景や現状について把握するとともに、できる限り、例えば第三者委員会の報告書などの一次情報にアクセスすることで、より詳細な事件の背景等について精査していくことが肝要です。
もちろん全ての事柄について深掘りすることには限界がある以上、情報は選別していくことが必要となります。しかし、企業法務と呼ばれる講学上の分野は、世の中の考え方の変化も激しく、統一的な理論や体系が存在していないというのも事実です。理論や体系はそうした実務の発展の歴史が代替します。それらを追った上で、自身が実務において抱える身近な問題について課題を掘り下げていく姿勢が何よりも重要です。
(「企業法務の学び方(3)」に続く)
参考文献
弁護士法人中央総合法律事務所編『企業不祥事のケーススタディ――実例と裁判例』(商事法務、2018年)