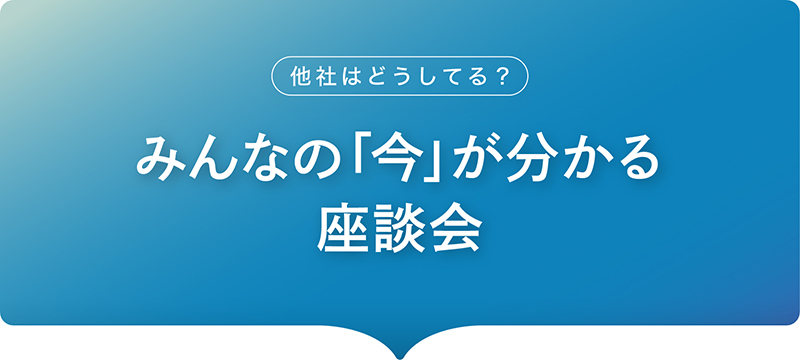変形労働時間制とは? 1カ月単位・1年単位・
フレックスタイム制との違い・メリット・
デメリット・注意点などを分かりやすく解説!
| おすすめ資料を無料でダウンロードできます ✅ 労働時間に関する研修資料 |
- この記事のまとめ
-
変形労働時間制は、一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において、特定の日または週に法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
業務の繁閑や特殊性に応じて、労働者と使用者が互いに工夫しながら労働時間の配分を行うことができるため、レジャー産業、宿泊業や飲食業など、季節や月、週によって繁閑に差がある業種で多く利用されています。
変形労働時間制には、1週間単位、1カ月単位、1年単位の3種類があります。
本記事では、それぞれの変形労働時間制における労働時間の定め方や導入手続き、フレックスタイム制との違い、メリット・デメリットなどを分かりやすく解説します。
※この記事は、2024年12月13日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。
※この記事では、法令名を次のように記載しています。
- 労基法…労働基準法
- 労基則…労働基準法施行規則
目次
変形労働時間制とは
労働時間制度とは
労働時間制度は、法律により労働時間に上限を設けることで、長時間労働を防止し、労働者の健康を保護する制度です。
労基法で定められている法定労働時間と法定休日の日数は、原則として以下のとおりです(労基法32条・35条)。
法定労働時間:休憩時間を除き、1日8時間、1週40時間(特例措置対象事業場の場合は44時間)以内
法定休日:毎週少なくとも1回、または、4週間で4日以上
しかしながら、レジャー産業、宿泊業や飲食業など、季節や月、週によって繁閑に差がある業種では、上記のような原則的な労働時間制度は事業実態にそぐわず、これを遵守しようとすると経営側に多大な負荷がかかりかねません。
そこで、このような業種において経営者側と労働者側の双方に無理が生じないよう、繁忙期の所定労働時間を長くする代わりに、閑散期の所定労働時間を短くするなど、業務の繁閑や特殊性に応じて、労働者と使用者が互いに工夫しながら労働時間の配分を行うことができる制度として変形労働時間制が設けられています。
変形労働時間制とは
変形労働時間制は、労使協定や就業規則等において定めることにより、一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において、特定の日または週に法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
変形労働時間制の種類
変形労働時間制には、平均する期間により以下のような3種類があります。
(1) 1カ月単位
(2) 1年単位
(3) 1週間単位
変形労働時間制を採用している企業の割合
厚生労働省による令和5年度の調査結果によれば、以下のとおり、約6割の企業が変形労働時間制やフレックスタイム制を採用しています。
| 企業規模 | 変形労働時間制採用企業(複数回答) | |||
|---|---|---|---|---|
| 全体 | 1年単位 | 1カ月単位 | フレックスタイム制 | |
| 全体 | 59.3% | 31.5% | 24.0% | 6.8% |
| 1000人以上 | 77.3% | 19.1% | 49.1% | 30.7% |
| 300~999人 | 68.6% | 24.6% | 38.3% | 17.2% |
| 100~299人 | 67.9% | 33.5% | 29.9% | 9.4% |
| 30~99人 | 55.3% | 31.9% | 20.0% | 4.2% |
1カ月単位の変形労働時間制
1カ月単位の変形労働時間制とは
1カ月単位の変形労働時間制とは、
✅ 対象期間を1カ月以内
に定め、その期間内において、
✅ 1週間当たりの労働時間の平均が40時間以内
(特例措置対象事業場の場合は44時間以内)
であれば、特定の日に8時間、特定の週に40時間(特例措置対象事業場の場合は44時間)を超えて労働させることができる制度です(労基法32条の2)。
対象期間および対象者
1カ月単位の変形労働時間制の対象期間は、1カ月以内とされており、1カ月より短く設定することも可能です。
1カ月単位の変形労働時間制は、以下の労働者を除き、全ての労働者に適用することができます。ただし、適用する労働者の範囲は、明確に規定する必要があります。
〈変形労働時間制を適用できない労働者〉
・満18歳未満(労基法60条1項)
・妊娠中や産後1年を経過しない女性が請求した場合(労基法66条1項)
労働時間の定め方
1カ月単位の変形労働時間制では、対象期間における1週間当たりの労働時間の平均が法定労働時間以内である必要があります。
対象期間における労働時間の上限は以下の式により算出できます。
上限時間=1週間の法定労働時間×対象期間の暦日数/7
具体的な上限時間は、以下のとおりです。
| 対象日数 | 原則(週40時間) | 特例措置対象事業場の場合(週44時間) |
|---|---|---|
| 31日 | 177.1時間 | 194.8時間 |
| 30日 | 171.4時間 | 188.5時間 |
| 29日 | 165.7時間 | 182.2時間 |
| 28日 | 160時間 | 176時間 |
| 21日 | 120時間 | 132時間 |
| 14日 | 80時間 | 88時間 |
会社は、上記の上限時間を対象期間内で割り振り、対象期間の全ての労働日ごとの労働時間をあらかじめ具体的に定める必要があります。
なお、変形労働時間制は、週当たりの労働時間についての規制の特例ですから、法定休日については原則どおり毎週1日以上または4週につき4日以上設ける必要があります。
導入手続
1カ月単位の変形労働時間制を導入するためには、以下のいずれかの方法をとります。
(1) 過半数労働組合または労働者の過半数代表者との間で書面による労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出る
(2) 就業規則等に規定する
労使協定や就業規則等では、主に以下の点について定めます。
① 対象労働者の範囲
② 対象期間と起算点
③ 労働日と労働日ごとの労働時間
④ 変形期間を平均して1週間の法定労働時間を超えない旨の定め
⑤ 労使協定の有効期間(労使協定で定める場合)
1年単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制とは
1年単位の変形労働時間制とは、
✅1カ月を超え、1年以内の期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えないこと
を条件として、業務の繁閑に応じ労働時間を配分することができる制度です(労基法32条の4)。
対象期間および対象者
1年単位の変形労働時間制の対象期間は1カ月を超え、1年以内の期間です。
対象期間の中で特に業務の繁忙な時期を特定期間として定めることができます(労基法32条の4第1項3号)。
以下で記載するとおり、特定期間では労働日についての制限が緩和されます。
1年単位の変形労働時間制も、1カ月単位の変形労働時間制と同じく、若年労働者や妊産婦の保護等の要請から適用除外となる労働者を除き、全ての労働者に適用することができます。ただし、その範囲を明確に定める必要があります。
労働時間の定め方
1年単位の変形労働時間制においては、対象期間における1週間当たりの労働時間の平均が40時間となるよう労働時間を定めなければなりません。
なお、通常であれば週44時間までの労働が認められる特例措置事業者であっても、この制度を利用する際には1週間平均の労働時間を週40時間以下とする必要があります(労基則25条の2第4項)。
また、労働者が過度な労働を強いられることがないよう、繁忙期であっても、労働時間は以下の時間内とする必要があります。
- 繁忙期における労働時間の上限
-
・1日の上限:原則10時間
・1週間の上限:52時間
・対象期間において連続して労働させる日数の限度:6日間
ただし、特定期間については、1週間に1日の休日が確保できる日数(最長12日)
また、対象期間が3カ月を超える場合には、上記の制限に加え、以下の制限があります。
- 対象期間が3カ月を超える場合
-
・労働時間が48時間を超える週を連続させることができるのは3週まで
・対象期間を3カ月ごとに区分した各期間において、労働時間が48時間を超える週は、週の初日で数えて3回以下
・対象期間における労働日数の限度は、原則として1年当たり280日
(対象期間が1年未満の場合、次の式により計算した日数(端数切り捨て))
280日×対象期間の歴日数/365
導入手続
1年単位の変形労働時間制を導入するためには、過半数労働組合または労働者の過半数代表者との間で労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。
労使協定では、主に以下の点について定めます。
① 対象労働者の範囲
② 対象期間と起算点
③ 特定期間(必要な場合)
④ 労働日と労働日ごとの労働時間
⑤ 労使協定の有効期間
なお、「④労働日と労働日ごとの労働時間」については、対象期間を1カ月ごとに区分し、労使協定では以下の項目を規定したうえで、各期間の30日以上前に当該各期間における労働日と労働日ごとの労働時間を、過半数労働組合または労働者の過半数代表者の同意を得て書面で定めることもできます。
(1) 最初の期間における労働日と労働日ごとの労働時間
(2) (1)の期間以外の各期間における労働日数と総労働時間
1週単位の非定型的変形労働時間制
1週単位の非定型的変形労働時間制とは
1週間単位の非定型的変形労働時間制とは、規模30人未満の特定の事業において、 労使協定により、1週間単位で毎日の労働時間を弾力的に定めることができる制度です(労基法32条の5第1項)。
対象となる事業および対象者
1週間単位の非定型的変形労働時間制を行うことができる事業者は、事業場における従業員が常時30人未満の規模であって、以下の事業に該当する事業者です。
- 小売業
- 旅館
- 料理・飲食業
従業員の人数要件は、各店舗など各事業場ごとの要件であり、会社全体の従業員数が30人未満である必要はありません。
なお、1週間単位の変形労働時間制も、若年労働者や適用しないことを要求した妊産婦には適用することができません。
労働時間の定め方
1週間単位の非定型的変形労働時間制においては、1週間の労働時間を以下のとおりとする必要があります。
- 1週間の上限:40時間
- 1日の上限:10時間
なお、通常であれば週44時間までの労働が認められる特例措置事業者であっても、この制度を利用する際には1週間の労働時間を週40時間以下とする必要があります(労基則25条の2第4項)。
導入手続
1週間単位の非定型変形労働時間制を採用するためには、過半数労働組合または労働者の過半数代表者との間で、労使協定で主に以下の事項を定めたうえで、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります(労働基準法32条の5第3項)。
① 1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用すること
② 対象となる従業員の範囲
③ 1週間の労働時間を40時間以下、1日の労働時間を10時間以下とすること
④ 有効期間
なお、1週間単位の非定型変形労働時間制では、労使協定に毎日の就業時間を定める必要はありませんが、1週間の各人の労働時間を1週間が開始する前に書面で労働者に通知する必要があります(労基則12条の5第3項)。
ただし、緊急やむをえない事由がある場合には、会社は、あらかじめ通知した労働時間を変更しようとする日の前日までに書面により従業員に通知することにより労働時間を変更することができます(労基則12条の5第3項ただし書)。
フレックスタイム制との違い
フレックスタイム制とは
変形労働時間制と混同されやすいものとして、フレックスタイム制があります。
フレックスタイム制は、一定の清算期間(3カ月を超えない期間)を平均した1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内で、その期間における総労働時間を定め、その範囲内で始業・終業時刻を各労働者がそれぞれ自主的に決定することができる制度です(労基法32条の3)。
労働時間の定め方
フレックスタイム制では、労使協定により清算期間における総労働時間をあらかじめ定めておき、各労働者は、その総労働時間内で自由に始業時間と就業時間を決めることができます。
総労働時間を定めるに当たっては、清算期間における総労働時間が、法定労働時間の総枠を超えないことが必要です。
清算期間における総労働時間≦(清算期間の歴日数/7日)×1週間の法定労働時間
なお、特例措置対象事業場については、清算期間が1カ⽉以内の場合には週平均44時間までとすることが可能ですが、清算期間が1カ⽉を超える場合には、特例措置対象事業場であっても、週平均40時間を超えて労働させる場合には、割増賃⾦の⽀払が必要です(労基則25条の2第4項)。
なお、フレックスタイム制では、労使協定により、労働者が1⽇のうちで必ず働かなければならない時間帯(コアタイム)や労働者が自らの選択によって労働時間を決定することができる時間帯(フレキシブルタイム)を定めることができます。
変形労働時間制との違い
変形労働時間制とフレックスタイム制は、ともに労働時間を柔軟に調整するための制度ですが、それぞれの制度には、以下のような特徴があります。
変形労働時間制:閑散期と繁忙期がある業種において効率的に労働力を投入することで総労働時間を短縮させる制度
フレックスタイム制:一定の総労働時間内で自らの労働時間を自ら調整することで、⽣活と業務の調和を図りながら効率的に働くことができる制度
両制度では、その特徴に応じ、就業時間の決定権者が異なります。
変形労働時間制:期間ごとの業務量に応じた就業時間とするため、使用者が決定
フレックスタイム制:自己のワークライフバランスを調整するため、各労働者が決定
導入手続き
フレックスタイム制を導入するためには、就業規則等により制度を導入することを定めた上で、労使協定を締結する必要があります。
就業規則と労使協定では、以下の点を定めます。
(就業規則)
・始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねること
(労使協定)
①対象となる労働者の範囲
②清算期間
③清算期間における総労働時間(清算期間における所定労働時間)
④標準となる1⽇の労働時間
⑤コアタイム(任意)
⑥フレキシブルタイム(任意)
なお、清算期間が1カ月を超える場合には、労使協定を労働基準監督署に届け出る必要があります。
変形労働時間制のメリット・デメリット
変形労働時間制のメリット
変形労働時間制には、以下のようなメリットがあります。
(1) 企業側のメリット
・時期ごとの業務量にあわせて労働力を配分することができる
・残業代が発生しにくくなり、経費削減となる
(2) 従業員側のメリット
・無駄な労働時間の減少、休日の増加により生活にゆとりが生じる
(1)企業側のメリット
企業側にとっての変形労働時間制の最大のメリットは、時期ごとの業務量に合わせて労働力を配分することができる点です。例えば、海の家やスキー場など、季節によって必要な労働力に大きな差がある業種や、月末に業務が集中する業種などでは、通常の労働時間制では閑散期には労働力が余り、繁忙期には労働力が足りないこととなります。
そこで、変形労働時間制を採用することにより、閑散期には労働時間を短く、繁忙期には労働時間を長く設定することで、労働資源をうまく配分することができます。
また、このような業種の場合、通常の労働時間制では、繁忙期に多くの時間外労働をさせる必要が生じ、多くの残業代が発生しますが、変形労働時間制の場合には、繁忙期に通常より多くの時間を法定労働時間内の労働として割り当てることができるので、通常の制度の場合より残業代が発生しにくくなり、経費削減となります。
(2)従業員側のメリット
従業員側のメリットとしては、閑散期に仕事はないが会社にいなければならないといった無駄な労働時間がなくなり、総労働時間が減ったり、休日がとりやすくなることなどにより、生活にゆとりが生じることがあげられます。
変形労働時間制のデメリット
変形労働時間制には、以下のようなデメリットがあります。
(1) 企業側のデメリット
・導入手続きが煩雑
・導入までに時間やコストがかかる場合がある
・勤務時間管理、残業代算出などの労務管理が複雑になる
(2) 従業員側のデメリット
・期間ごとに勤務時間が異なるため、育児・介護等との調整が困難な場合がある。
・同一時間勤務であっても残業代が減る場合がある
(1)企業側のデメリット
変形労働時間制を導入するには、労使協定を結んで労働基準監督署に届け出たり、就業規則等に定めをおくなど、導入するまでに煩雑な手続きが必要です。
また、導入の際、労使協定や就業規則等であらかじめ労働時間を定めておく必要があり、自社の業務形態に照らし、どのような職種でどのような労働時間を定めるべきか検証したり、定め方等について、専門家の助言が必要な場合もあります。
そのため、導入までに時間や専門家コストがかかる可能性があります。
また、変形労働時間制を導入した場合、労働者ごとに変形労働時間制に対応した労働時間管理や残業代計算をする必要があり、通常の場合に比べ、労務管理に時間や費用がかかる場合があります。
(2)従業員側のデメリット
従業員側のデメリットとしては、1年を通しての就労時間が一定でないため、デイサービスや保育園など、1年を通して同じ時間帯で利用するサービスとの調整が難しい場合があります。
この点については、育児や介護を行う者などに対しては、育児等に必要な時間を確保できるよう配慮しなければならないとされており、事業者は各労働者の実情に合わせて就業時間を調整する必要があります。
また、変形労働時間制では、定められた労働時間を超えて残業したとしても1日8時間以内の労働時間であれば割増賃金が払われないなどの理由で、同一時間働いても残業代が減る可能性があります。
事業者の注意点
変形労働時間制に36協定は必要?
36協定とは、時間外労働や休日労働をさせる場合に、あらかじめ使用者と労働者の間で締結しなければならない「時間外・休日労働に関する協定」をいいます。
変形労働時間制は、原則1日8時間以内、週40時間以内という法定労働時間を柔軟に適用するための制度であり、時間外・休日労働をさせるための制度ではありませんので、変形労働時間制を採用する際に36協定を締結する必要はありません。
しかしながら、変形労働時間制を採用したうえで、変形労働時間制で認められている労働時間を超えて労働させたり、休日労働をさせる場合には、36協定を結ぶ必要があります。
残業代を払う必要はない?
変形労働時間制を採用したうえで、36協定を結んだ場合、36協定で認められた範囲内で残業をさせることができますが、その場合、労基法の規定に従った残業代を支払う必要があります。
なお、変形労働時間制度を採用した場合、例えば1年単位の変形労働時間制では以下のような計算が行われるなど、通常の場合と残業代の算出方法が異なるため、注意が必要です。
- 変形労働時間制の残業代の算出方法
-
(1)1日単位での残業代
1日の所定労働時間が8時間以内の場合、所定労働時間を超えた部分のうち8時間までについては通常の賃金の、8時間を超えた部分については、割増賃金の支払いが必要。
1日の所定労働時間が8時間を超えている場合、所定労働時間を超えた部分について割増賃金の支払いが必要。(2)1週単位での残業代((1)に該当する部分を除く)
1週の所定労働時間が40時間以内の場合、所定労働時間を超えた部分のうち40時間までについては通常の賃金の、40時間を超えた部分については、割増賃金の支払いが必要。
1週の所定労働時間が40時間を超えている場合、所定労働時間を超えた部分について割増賃金の支払いが必要。(3)対象期間単位での残業代((1)(2)に該当する部分を除く)
対象期間における法定労働時間の総枠を超えた部分について割増賃金の支払いが必要
| おすすめ資料を無料でダウンロードできます ✅ 労働時間に関する研修資料 |
参考文献
厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「1か月単位の変形労働時間制」
厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「1年単位の変形労働時間制」