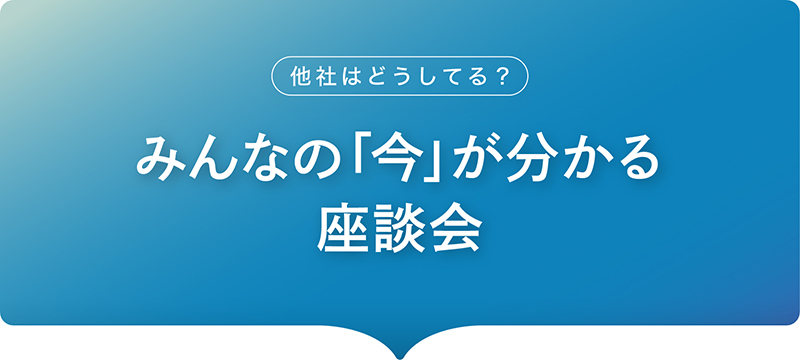法定労働時間とは?
所定労働時間との違い・労働基準法のルール・
残業代の計算方法などを解説!
(※この記事は、2022年1月13日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。)
目次
法定労働時間とは?
「法定労働時間」とは、「1日8時間・週40時間」を原則とする、労働時間の上限を意味します(労働基準法32条1項、2項)。
法定労働時間が設けられているのは、過剰な労働を強いられることにより、労働者の健康が害されることを予防するためです。
法定労働時間と所定労働時間の違い
労働基準法上の「法定労働時間」とは別に、労働時間の上限を定める概念として「所定労働時間」があります。
「所定労働時間」とは、会社が独自に定める勤務時間を意味します。所定労働時間は、法定労働時間の範囲内で定めなければなりません。
所定労働時間と法定労働時間がずれている場合には、「法定内残業」と「法定外残業(時間外労働)」という2種類の残業が発生します。それぞれの違いについては、後記の説明をご参照ください。
月平均所定労働時間とは
実際に残業代を計算する際には、当該月の実日数を合計した所定労働時間ではなく、「月平均所定労働時間」という数値を用います。
毎月の基本給は昇給がない限り一定である一方で、1か月の日数は月ごとに異なります。そのため、当該月の実日数を用いると、残業代計算の基礎となる1時間当たりの基礎賃金(後述)が毎月違うことになってしまいます。
そこで、実際の残業代を計算する際には、以下の式によって算出される月平均所定労働時間を用いて、1時間当たりの基礎賃金を求めます。
なお、月平均所定労働時間が問題となるのは、1時間当たりの基礎賃金を計算する場合のみです。これに対して、所定労働時間を超えたかどうか(残業代が発生するかどうか)の境目を判断する場面では、あくまでも1日単位の所定労働時間が参照される点にご留意ください。
休日・休憩時間の原則
労働基準法では、過重な労働を防ぐ目的で、法定労働時間とは別に、休日と休憩時間に関するルールを定めています。
休日に関するルール
使用者は労働者に対して、原則として毎週1日以上の休日を与えるか、または4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません(労働基準法35条1項、2項)。この労働基準法のルールに基づいて与えられる休日を「法定休日」と言います。
週に2日以上の休日を設定する会社も多く存在しますが(土日休みなど)、法定休日はあくまでも週に1日だけです。法定休日でない休日は「法定外休日」として取り扱われます。
法定休日に労働者を働かせるには、後述する「36協定」を労使間で締結して、休日労働についてのルールを定め、そのルールの範囲内で休日労働を指示する必要があります。休日労働には、通常の賃金に対して35%以上の割増賃金が発生します(労働基準法37条1項、労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令)。
これに対して、法定外休日における労働は、休日労働ではなく時間外労働に当たり、時間外労働をさせる場合も36協定の締結が必要です。
法定外休日労働によって週40時間の労働時間を超過した場合の割増賃金率は25%以上(大企業に限り、月に60時間を超える部分は50%以上)となります(労働基準法37条1項)。中小企業においては、2023年4月1日から月に60時間を超える部分の割増賃金率は50%となります。
休憩に関するルール
使用者は労働者に対して、労働時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩を与えなければなりません(労働基準法34条1項)。労働者は、休憩時間を自由に利用することができます(同条3項)。
実際には、残業を含めて1日の労働時間が8時間を超えるケースが発生し得るため、フルタイムの従業員については、多くの会社が1時間の休憩を付与しています。
なお、休憩時間は原則として、全労働者に対して一斉に与える必要があります(同条2項本文)。ただし、労使協定で合意すれば、バラバラに休憩時間を与えることも可能です(同項ただし書)。
法定労働時間を超えて労働させるには「36協定」の締結が必要
使用者が、法定労働時間を超えて労働者を働かせるためには、労使間で「36協定」を締結して、労働基準監督署に届け出なければなりません(労働基準法36条1項)。
「36協定」とは?
「36協定」とは、時間外労働についてのルールを定める労使協定です。
労働者側は、以下のいずれかが主体となって36協定を締結します。
- 労使協定の締結主体(労働者側)
-
✅ 労働者の過半数で組織する労働組合
✅ 労働者の過半数を代表する者(過半数労働組合がない場合)
36協定によってルールを設けることで、過酷な長時間労働を防止しつつ、労使双方のニーズに応じて労働時間を延長することが可能となります。
36協定によって定めることができる時間外労働の上限
36協定を締結しても、使用者は労働者に対して、無制限に時間外労働を指示できるわけではありません。労働者の健康保持の観点から、36協定では原則として、以下の上限を超える時間外労働を定めることはできないとされています(労働基準法36条4項)。
- 36協定に基づく時間外労働の上限(原則)
-
✅ 1か月につき45時間
✅ 1年につき360時間
なお、事業場において通常予見することができない業務量の大幅な増加などに伴い、臨時的に上記の上限を超えて労働させることができる旨を、36協定で定めることが認められています。ただしその場合も、以下の上限を超えることはできません(同条5項、6項)。
- 36協定に基づく時間外労働の上限(臨時)
-
✅ 時間外労働が年720時間以内
✅ 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
✅ 時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」がすべて1か月当たり80時間以内
✅ 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月以内
所定労働時間・法定労働時間と残業代の関係性・計算方法
所定労働時間と法定労働時間は、残業代を計算する際の重要な基準となります。労働基準法のルールを踏まえて、実際に残業代を計算してみましょう。
法定労働時間内の残業|通常の賃金が発生
会社が定める所定労働時間を超えて働いた場合には、残業代が発生します。
所定労働時間と法定労働時間がずれている場合、「所定労働時間を超えるものの、法定労働時間の範囲内」という残業時間が発生します。これを「法定内残業」と言います。
法定内残業は、残業ではありますが、労働基準法上の「時間外労働」には当たりません。そのため、法定内残業に対しては、通常の賃金が支払われます。
法定労働時間を超える残業|割増賃金が発生
これに対して、法定労働時間を超える残業を「法定外残業」、又は「時間外労働」と言います。
法定外残業(時間外労働)に対しては、労働基準法に従った割増賃金が支払われます(労働基準法37条1項)。割増率は、以下のとおりです。
| 60時間以内の部分 | 25%以上 |
| 月60時間を超える部分 | 50%以上 (中小企業については、2023年3月まで25%以上) |
残業代の計算例
残業代は、以下の計算式によって求められます。
設例を用いて、実際に残業時間を計算してみましょう。
設例のケースでは、月曜から金曜までの5日間につき、所定労働時間を超える、毎日2時間の残業が発生しています。そのうち、「法定内残業」が各1時間、「法定外残業(時間外労働)」が各1時間です。
したがって、この1週間での「法定内残業」は計5時間、「法定外残業(時間外労働)」も計5時間となります。この数字を用いて残業代を計算してみましょう。
法定労働時間には例外がある
「1日8時間・週40時間」を原則とする法定労働時間ですが、労働基準法では、さまざまな例外が設けられています。
特例措置対象事業場では「週44時間」
特例措置対象事業場(=以下のいずれかの業種に該当し、かつ常時使用する労働者が10人未満の事業場)では、法定労働時間は「1日8時間・週44時間」となります。
- 特例措置対象事業場
-
✅ 商業
→卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、その他の商業✅ 映画・演劇業
→映画の映写、演劇、その他✅ 保健衛生業
→病院、診療所、社会福祉施設、浴場業、その他の保健衛生業✅ 接客娯楽業
→旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業
変形労働時間制
「変形労働時間制」とは、法定労働時間を超えているかどうかの判断を、一定の期間における1週間の平均労働時間を基準として行うことができる制度です(労働基準法32条の2、32条の4)。労使協定の締結により、変形労働時間制の導入が認められます。
変形労働時間制には「1か月単位の変形労働時間制」と「1年単位の変形労働時間制」の2パターンがあります。なお、対象期間が1年を超える変形労働時間制は認められていません。
変形労働時間制を導入できる基準とは
会社が変形労働時間制を導入する際の手続きは、1か月単位の変形労働時間制と1年単位の変形労働時間制で異なります。
1か月単位の変形労働時間制は、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は、労働者の過半数を代表する者)との間で労使協定を締結するか、または就業規則などの社内規程でルールを定めれば導入できます。
労使協定の締結が必須ではなく、就業規則等の改定によっても導入できるため、比較的シンプルな手続きといえるでしょう。
1か月単位の変形労働時間制について、労使協定または就業規則等では、以下の事項を定める必要があります。
・対象労働者の範囲
・対象期間(1か月以内)および起算日
・労働日および労働日ごとの労働時間
・有効期間(労使協定に限る)
1年単位の変形労働時間制は、就業規則等の社内規程によって導入することはできず、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は、労働者の過半数を代表する者)との間で労使協定の締結が必須とされています。
1年単位の変形労働時間制について、労使協定で定めるべき事項は以下のとおりです。
・対象労働者の範囲
・対象期間(1か月超1年以内)および起算日
・特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間)
・労働日および労働日ごとの労働時間
・有効期間
なお、1年単位の変形労働時間制については、対象期間中の労働時間が偏り過ぎないように、以下の規制が適用されます。
・労働日数は1年間に280日まで(対象期間が3か月超1年未満の場合は日割計算、3か月以内の場合は上限なし)
・連続労働日数は最長6日まで(特定期間については最長12日まで)
・1日の労働時間は最長10時間、1週間の労働時間は最長52時間まで
・週48時間を超える所定労働時間を設定するのは連続3週以内、かつ3か月の期間ごとに3週以内(いずれも対象期間が3か月以内の場合には適用なし)
フレックスタイム制
「フレックスタイム制」とは、1日の労働時間を、必ず勤務すべき時間帯(コアタイム)と、いつ始業・就業してもよい時間帯(フレキシブルタイム)とに分ける制度です(労働基準法32条の3)。フレックスタイム制では、労働者の裁量によって始業・終業の時刻を決めることができます。なお、コアタイムは必ず設ける必要はなく、すべての時間をフレキシブルタイムとすることも可能です。
フレックスタイム制も、導入時には労使協定の締結が必要となります。
フレックスタイム制では、清算期間(3か月以内で労使協定により設定)当たりの総労働時間が定められています。総労働時間の範囲内であれば、法定労働時間を超えないものとして取り扱われます。
フレックスタイム制で残業代は支払われるのか
フレックスタイム制で働く労働者については、清算期間ごとに残業代の精算を行います。
清算期間における総労働時間を実労働時間が超過した場合は、残業代が発生します。例えば1か月の総労働時間が160時間で、実労働時間が170時間だった場合、会社は労働者に対して10時間分の時間外労働手当を支払わなければなりません。
一方、清算期間における総労働時間を実労働時間が下回った場合には、会社は以下のいずれかの対応をとります。どちらの対応をとるかについては、労使協定の定めに従う必要があります。
①不足分の労働時間に対応する賃金を控除する
②不足分の労働時間を、次の清算期間における総労働時間に加算する
なお②の対応をとる場合でも、加算後の総労働時間が法定労働時間を超えることは認められません。
(例)
4週間の清算期間における総労働時間が160時間の場合
→総労働時間がすでに法定労働時間の上限に達しているため、不足分の労働時間の繰り越し加算は認められない
繁閑の差が激しい一定の業種|1日10時間まで
以下のいずれかの業種に該当し、かつ常時使用する労働者数が30人未満の事業場では、労使協定の締結を条件として、法定労働時間を1日10時間まで延長することができます(労働基準法32条の5、同法施行規則12条の5)。
- 法定労働時間を1日10時間まで延長できる業種
-
✅ 小売業
✅ 旅館
✅ 料理店
✅ 飲食店
裁量労働制
労働基準法では、以下の3つの裁量労働制が認められており、いずれも労働時間について例外的な取扱いが行われます。
事業場外裁量労働制
事業場外で働く労働者について、労働時間を算定し難い場合には、原則として、所定労働時間労働したものとみなされます(労働基準法38条の2第1項)。
この場合、実際には法定労働時間を超えて働いたとしても、所定労働時間が労働時間とみなされるため、時間外労働は発生しません。
専門業務型裁量労働制
高い専門性が求められる以下の職種については、労使協定の締結により、裁量労働制の導入が認められています(労働基準法38条の3)。
- 専門業務型裁量労働制の対象業務
-
✅ 新商品や新技術などの研究開発業務
✅ 情報処理システムの分析、設計業務
✅ 記事取材、編集などの業務
✅ 新たなデザインの考案業務
✅ 放送プロデューサー、ディレクター業務
✅ コピーライター業務
✅ システムコンサルタント業務
✅ インテリアコーディネーター業務
✅ ゲームソフトの創作業務
✅ 証券アナリスト業務
✅ 金融商品の開発業務
✅ 大学教授の業務
✅ M&Aアドバイザリー業務(2024年4月1日より追加)
✅ 公認会計士業務
✅ 弁護士業務
✅ 建築士業務
✅ 不動産鑑定士業務
✅ 弁理士業務
✅ 税理士業務
✅ 中小企業診断士業務
専門業務型裁量労働制では、実際の労働時間にかかわらず、労使協定で定められたみなし労働時間が適用されます。
企画業務型裁量労働制
企画・立案・調査・分析を内容とする職種については、専門業務型裁量労働制の対象でなくても、「企画業務型裁量労働制」の導入により、みなし労働時間を適用することが認められています(労働基準法38条の4)。
ただし、企画業務型裁量労働制を導入するには、労使協定よりも要件の厳しい「労使委員会決議」が必要です。
農林・畜産・養蚕・水産の事業
農林・畜産・養蚕・水産の事業に従事する労働者については、会社勤めの場合などとは異なり、画一的に労働時間を管理することは不適当と考えられています。
そのため、労働時間に関する規制が適用除外とされており(労働基準法41条1号)、法定労働時間の適用はありません。
管理監督者
「管理監督者」とは、権限・待遇・勤務時間の裁量などを考慮して、経営者と一体的な立場にあると評価できる労働者を意味します。
管理監督者には、経営的な判断を随時行うことが要求されるため、法定労働時間を含む労働時間規制が適用されません(労働基準法41条2号前段)。
機密の事務を取り扱う労働者
経営者や管理監督者の活動と一体不可分の職務を取り扱う者は、経営者・管理監督者と行動を共にする性質上、労働時間の規制が適用除外とされています(労働基準法41条2号後段)。
機密の事務を取り扱う労働者には、経営者や管理監督者の秘書などが該当します。
監視又は断続的労働に従事する労働者
監視労働に従事する労働者とは、一定部署にて監視するのを本来の業務とし、身体的・精神的緊張が低い業務を行う労働者のことを言います。
断続的労働に従事する労働者とは、業務が定期的に発生しては終了するといったかたちで労働し、手待時間が、業務に当たる時間を上回る業務に従事する労働者のことを言います。
守衛・用務員・管理人・経営者の運転手などは、監視又は断続的労働者に従事する労働者に該当します。
これらに該当する労働者の場合は、労働基準監督署長の許可を受けた場合に限り、法定労働時間を含む労働時間の規制の適用を除外することができます(労働基準法41条3項)。
高度プロフェッショナル制度の対象労働者
高度な専門性が要求され、労働時間と成果の関連性が薄い以下の職種については、労使委員会決議及び本人の同意等を条件として、「高度プロフェッショナル制度」を導入することが認められます(労働基準法41条の2)。
- 高度プロフェッショナル制度の対象職種
-
✅ 金融商品の開発業務
✅ (他人の)資産運用業務
✅ 自己運用業務
✅ 投資助言業務
✅ コンサルティング業務
✅ 技術・商品・サービスの研究開発業務
高度プロフェッショナル制度が適用される労働者については、法定労働時間を含む労働時間の規制が適用除外となります。
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置
個々の労働者によって異なる労働時間の規制内容を踏まえつつ、使用者は適切に労働時間の管理を行わなければなりません。そのためには、「客観的な記録」と「現場の実態把握」の両面に留意する必要があります。
タイムカード等を用いて、客観的に労働時間を記録する
各労働者の労働時間を正確に把握するためには、労働時間を適正に記録することが重要です。
例えば、以下の方法を用いて、労働時間を客観的に記録することが考えられます。
経営者が現場での労働実態を把握するよう努める
上司の指示により、タイムカードが前倒しで不正打刻させられていたり、労働者が残業時間を過少申告させられたりするケースも散見されます。
こうした事態を防ぐためには、経営者が現場での労働実態を把握することが大切です。現場責任者や個々の労働者と1on1ミーティングを行うなどして、積極的に現場の情報収集に努めましょう。
この記事のまとめ
法定労働時間の記事は以上です。最新の記事に関する情報は、契約ウォッチのメルマガで配信しています。ぜひ、メルマガにご登録ください!
参考文献
厚生労働省ウェブサイト「(3)1カ月又は1年単位の変形労働時間制」
厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」
厚生労働省ウェブサイト「効率的な働き方に向けてフレックスタイム制の導入」