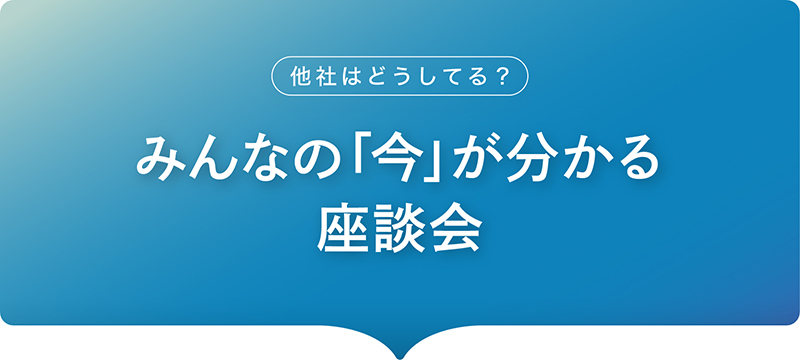顧問とは?
役員や相談役との違い・役割・具体例・
契約のメリット・選び方などを分かりやすく解説!
| おすすめ資料を無料でダウンロードできます ✅ (全国の中小企業編)顧問弁護士活用の実態とニーズ調査レポート |
- この記事のまとめ
-
「顧問」とは、企業などから依頼を受けて、専門的知識や経験に基づくアドバイスやサポートを行う者をいいます。
顧問は「内部顧問」と「外部顧問」に大別されます。内部顧問には退任した取締役が就任し、経営についてアドバイスする例がよく見られます。外部顧問の例としては、顧問弁護士や顧問税理士などが挙げられます。
顧問と契約すると、専門的な知見に基づく客観的なアドバイスを受けられるメリットがあります。また、
・顧問の人脈を活用できる点
・役員が得意分野に集中できる点
・対外的なレピュテーションの向上につながる点
なども、顧問と契約するメリットです。顧問を選ぶ際には、自社が必要としている専門的知識と経験を備えているかどうかを重視しましょう。そのほか、兼職の状況や相談の利便性、顧問料なども重要な考慮要素となります。
この記事では顧問について、基本から分かりやすく解説します。
※この記事は、2023年9月25日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。
目次
顧問とは
「顧問」とは、企業などから依頼を受けて、専門的知識や経験に基づくアドバイスやサポートを行う者をいいます。
顧問の役割
顧問の役割は、依頼元である企業などに対して、専門的知識や経験に基づくアドバイスやサポートを行うことです。
例えば株式会社において、経営上の意思決定をするのは取締役です。
しかし取締役は、あらゆる分野について豊富な知識や経験を有するわけではありません。そのため、取締役の知識や経験だけでは、適切な経営判断を行えない場合があります。
また、取締役が重要な経営判断を行う際には、内部者だけで意思決定をする場合に生じがちな偏見を警戒し、外部者の客観的な意見を聴くべきケースもあります。
顧問と役員・相談役・参与の違い
顧問に関連し、または顧問に近い立場の者を表す言葉として、「役員」「相談役」「参与」などが挙げられます。これらの者と顧問の違いを理解しておきましょう。
①役員
「役員」とは、株式会社における取締役・会計参与・監査役をいいます。
顧問は役員に名を連ねるケースもありますが、一般的には役員としてではなく、それ以外の立場で参画することが多いです。
②相談役
「相談役」とは、経営上の意思決定について、意思決定権者(株式会社であれば取締役)の相談に乗る者をいいます。
相談役の役割は顧問と類似していますが、顧問には外部専門家なども含むのに対して、相談役は会社の内部者(退任後の取締役)などが就任するケースが多いです。
③参与
「参与」とは、取締役に準じて経営上の意思決定を行う者をいいます。
顧問は経営上の意思決定権を有さず、あくまでもアドバイザーに過ぎません。これに対して参与は、取締役に比べると権限が限定されているものの、自ら経営上の意思決定を行う点が特徴的です。
顧問の種類|外部顧問(非常勤顧問)と内部顧問(常勤顧問)
「内部顧問」とは、会社内部から選ばれた顧問です。社内事情に精通しているため、実態に即したアドバイスやサポートをしやすいという特徴があります。内部顧問には、退任した取締役が就任し、経営についてアドバイスする例がよく見られます。
「外部顧問」とは、会社外部から選ばれた顧問です。専門的知識を豊富に有し、客観的なアドバイスができるという特徴があります。外部顧問に就任することが多いのは、顧問弁護士や顧問税理士など士業専門家や、コンサルタントなどです。
顧問の具体例
誰を顧問とすべきであるかは、会社のニーズによって異なります。以下に挙げるのは、顧問に就任することが多い者の一例です。
①内部顧問
・オーナー株主
・退任した取締役
・退任した管理職
など
②外部顧問
・弁護士
・税理士
・公認会計士
・社会保険労務士
・コンサルタント
など
顧問と会社法の関係性
顧問は、会社法において定められた役職ではありません。
ただし、顧問が会社法上の役員を兼ねることはできます。取締役の役職名を「顧問」とするケースなどが一例です。この場合、顧問は会社法上の規制を受けることになります。
顧問が会社法上の役員を兼ねない場合は、顧問に対して直接会社法の規定が適用されることはありません。契約形態に応じて、民法などの規定が適用されます。
顧問の契約形態
企業が顧問と契約する際には、「準委任契約」を締結するのが一般的です。
「準委任」とは、当事者の一方が法律行為でない事務を相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約をいいます(民法656条)。
顧問の業務は、経営上の意思決定に関するアドバイスが中心であり、自ら企業のために法律行為(契約など)をするわけではありません。そのため、顧問の業務は準委任契約に基づくと考えられます。
なお、法律行為の委託を内容とする契約は「委任」といいます。顧問との契約には「委任契約」の名称が付されることも多いですが、契約の法的な性質は実態によって決まります。法律行為の委託が含まれていない場合、「委任契約」という名称であっても、法的には「準委任」に当たると考えられます。
ただし、準委任には委任の規定が準用されるため(民法656条)、準委任と委任を厳密に区別する必要は基本的にありません。
顧問が企業の指揮命令下で業務を行う場合は、準委任ではなく「雇用」に当たることもあり得ます。顧問との契約が雇用である場合は、労働基準法をはじめとした労働法の規定が適用されます。
企業が顧問と契約するメリット
企業が顧問と契約するメリットとしては、以下の各点が挙げられます。
①専門的な知見を活用できる
②客観的なアドバイスを受けられる
③顧問の人脈を活用できる
④取締役が得意分野に集中できる
⑤対外的なレピュテーションの向上につながる
メリット1|専門的な知見を活用できる
顧問と契約することの大きな目的の一つは、顧問が有する専門的な知見を活用することです。
取締役は全ての領域について十分な知識や経験を有するわけではありません。経営上の意思決定を適切に行うためには、取締役の知識や経験が不十分な場合もあります。
会社の内部者が必要な知見を持っていない場合は、顧問にアドバイスを求めることが有用です。顧問の専門領域における知見を活用することにより、会社としてより適切に意思決定を行うことができます。
専門的な知見の活用の観点から顧問として契約することが多いのは、
- 弁護士
- 税理士
- 公認会計士
- 社会保険労務士
などの士業専門家です。特に会社の規模がある程度大きくなると、これらの専門家の知見を必要とする場面が増えるため、顧問としての契約を検討するとよいでしょう。
メリット2|客観的なアドバイスを受けられる
会社内部の者のみで意思決定をしてしまうと、視点が偏り、社会の潮流や客観的な状況にそぐわない意思決定をしてしまうリスクがあります。
このようなリスクを回避するための一選択肢として、経営陣から独立した立場にある顧問にアドバイスを求めることが考えられます。例えば外部のコンサルタントや、経営に関する知見を有する起業家などを顧問とすれば、取締役とは異なる視点からアドバイスを受けることができ、バランスのとれた経営上の意思決定が可能となります。
メリット3|顧問の人脈を活用できる
顧問自身が有する人脈を会社のために活用できる点も、顧問と契約するメリットの一つです。
例えば、長年経済界で活躍した人に顧問を依頼すれば、親交のある経営者を紹介してもらえるなど、ビジネスの機会が広がるでしょう。弁護士や税理士などの士業専門家に顧問を依頼すれば、顧問本人では対応できない事柄についても、同業の専門家の中で対応できる人を紹介してもらえることが多いです。
メリット4|取締役が得意分野に集中できる
顧問の主な役割は、意思決定をする取締役に足りない知識や経験などを補うことです。
取締役が得意としない領域まで全て自分で対応しようとすると、労力が分散してしまい、得意分野でも十分な判断能力を発揮できないおそれがあります。顧問のサポートを受ければ、取締役が得意分野に集中できるようになり、企業として最大のパフォーマンスの発揮が可能となります。
メリット5|対外的なレピュテーションの向上につながる
独立した客観的な立場にいる顧問の起用は、企業のガバナンスの観点からプラスに働きます。例えば、顧問弁護士と契約すれば法務・コンプライアンス、顧問税理士と契約すれば税務に関するガバナンスが向上するでしょう。
こうした顧問の起用を対外的にアナウンスすれば、社会から信頼できる企業であるとみなされ、レピュテーションの向上につながる可能性があります。
顧問を選ぶ際にチェックすべきポイント
顧問として契約する者は、以下のポイントに注目して選ぶとよいでしょう。
①専門的知識・経験
②兼職の状況
③相談の利便性
④顧問料
ポイント1|専門的知識・経験
顧問を選ぶに当たって、どのような専門的知識や経験を有しているかは重要な注目ポイントです。
顧問候補者が有する専門的知識・経験の深さや広さに加えて、その専門性が自社の足りない部分を補うものであるかどうかも検討する必要があります。自社の状況を分析した上で、より大きな貢献を期待できる人に顧問を依頼しましょう。
ポイント2|兼職の状況
顧問として招聘される人は、複数の企業との間で顧問契約などを締結しているケースが多いです。非常勤取締役などとして、他の会社で役員を兼務しているケースもあります。
顧問の兼職はある程度やむを得ない部分がありますが、あまりにも多くの職を兼ねている場合は、1つの企業に割くことのできる労力が限られてしまいます。
兼職が多すぎる顧問は、会社の実態をよく知ろうとせず、実情にそぐわない意見を述べて議論を混乱させたり、逆にほとんど意見を言わず、貢献度が期待に満たなかったりする可能性も考えられます。
このような事態を避けるため、顧問としての契約を検討する人については、必ず事前に兼職の状況を申告させましょう。
ポイント3|相談の利便性
顧問に対してどのような方法で相談できるかは、顧問との契約内容によって異なります。
例えば、顧問がオフィスに常駐する契約であれば、いつでも相談できるので利便性は高いといえます。常駐でなくても、メールなどで何度でも相談できる契約であり、かつ顧問からのレスポンスも早ければ、企業にとっての利便性は高いといえるでしょう。
これに対して、相談の回数が限られている場合や、日程・時間帯が狭く限定されている場合には、相談したい事柄が生じてもスムーズに相談できない可能性があります。
ただし、顧問の拘束時間を長くする場合や、いつでも相談できるように準備してもらう場合には、顧問料が高額となることが多いです。利便性と予算のバランスを考慮し、企業のニーズに合った内容の顧問契約を締結しましょう。
ポイント4|顧問料
顧問に対しては、毎月または定期的に顧問料を支払う必要があります。顧問料は固定費として会社の予算を圧迫し得るので、顧問を選ぶ際には重要な考慮要素の一つです。
顧問料の金額は、依頼先によって異なります。一般的には、経験や能力に長けている専門家の顧問料は高額と考えられますが、必ずしもそうとは限りません。比較的低廉な顧問料で、質の高いアドバイスやサポートを行う専門家もいます。
顧問料を低く抑えるには、複数の依頼先候補から見積もりを取得して比較するのがよいでしょう。もっとも、顧問料の金額だけに注目するのではなく、総合的に見て信頼できる人に顧問を依頼することをおすすめします。
| おすすめ資料を無料でダウンロードできます ✅ (全国の中小企業編)顧問弁護士活用の実態とニーズ調査レポート |