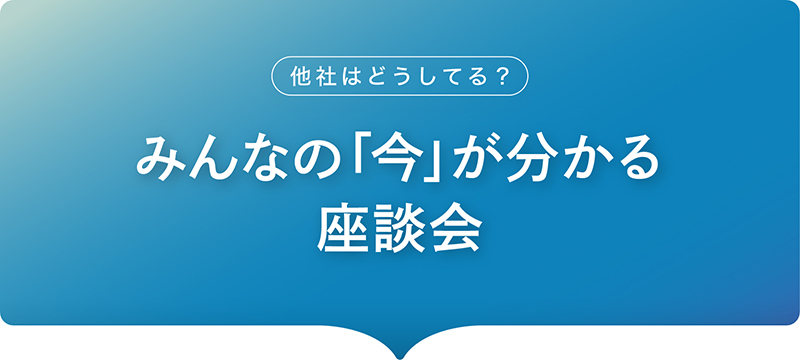フレックスタイム制とは?
コアタイムの意味や
メリット・デメリットを分かりやすく解説!
- この記事のまとめ
-
フレックスタイム制とは、一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、従業員が日ごとの始業・終業時刻、労働時間を自分で決められる制度です。
・業務効率が向上する、人材確保につながるといったメリットがあります。
・2019年の法改正により、清算期間(労働者が労働すべき時間を定める期間)は最長3カ月まで延長可能となりました。
・フレックスタイム制を導入するには、就業規則や労使協定の整備が必要です。本記事では、フレックスタイム制について、基本から詳しく解説します。
※この記事は、2025 年6月30日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。
目次
フレックスタイム制とは
フレックスタイム制の基本的な仕組みについて以下の点を解説します。
- 制度の定義と企業が導入する目的
- コアタイムとフレキシブルタイムの仕組み
- スーパーフレックスタイム制との違い
まずはフレックスタイム制の概要や詳細を理解しておきましょう。
フレックスタイム制の定義と導入目的
フレックスタイム制とは、あらかじめ定めた期間内での総労働時間の範囲内で、従業員が日ごとの始業・終業時刻を自分で決められる働き方です。2019年の法改正により、清算期間は最長3カ月まで延長可能となり、より柔軟な運用ができるようになりました。
なお清算期間とは、その期間内にあらかじめ定められた総労働時間を働けば良いという労働者が労働すべき時間(いわゆる所定労働時間)を定める期間のことです。長さは3カ月以内で1カ月単位や1週間単位で定めることも可能ですが、一般的には1カ月で設定されることが多く、1カ月超にする場合は労使協定を労働基準監督署に届け出る必要もあります。
フレックスタイム制導入の目的としては、ワークライフバランスの向上や通勤負担の軽減、生産性の向上などが挙げられます。育児や介護と仕事の両立を支えたり、多様な働き方のニーズに対応したりする制度として、注目が集まっています。
コアタイムとフレキシブルタイム
フレックスタイム制では、コアタイムとフレキシブルタイムという時間帯を設定することができます。
コアタイムは、必ず勤務する時間帯で、会議や連携業務を行うために設けられるケースが多いです。一方、フレキシブルタイムは出退勤の時刻を自由に選べる時間帯です。
例えば、コアタイムを10時~15時、フレキシブルタイムを6時~10時と15時~19時に設定すれば、6時から勤務したり、19時まで働いたりすることが可能になります。従業員のライフスタイルに合わせた柔軟な働き方を実現できる制度です。
なお、コアタイムは必ず設定しなければいけないわけではなく、コアタイムを設けずに全ての時間帯をフレキシブルタイムとする運用もできます。
スーパーフレックスタイム制との違い
スーパーフレックスタイム制は、コアタイムを設けず、従業員が始業時間・終業時間を自由に決められる制度です。
例えば、朝型の人は早く出社して夕方には退勤、夜型の人は昼過ぎから働き始めて夜遅くまで勤務する、といった働き方もできます。
ただし、自由度が高い分、自己管理やチーム内での連携を意識した運用が求められます。また、夜型勤務の場合22時以降に深夜割増賃金が発生することになるなど、勤怠管理も煩雑になります。
フレックスタイム制のメリット
フレックスタイム制には主に以下のようなメリットがあります。
- 従業員のモチベーション向上につながる
- 業務効率が向上する
- 人材確保につながる
それぞれのメリットについて解説します。
従業員のモチベーション向上につながる
フレックスタイム制では、従業員が自分で働き方を選べると感じられ、仕事への満足度やモチベーションが高まりやすくなります。ライフスタイルや体調、家庭の予定にあわせて働けることで、ワークライフバランスが整い、ストレスの軽減にもつながります。
例えば、保育園の送迎にあわせて出勤時間を調整したり、集中力が高まる時間帯を選んで働いたりすることが可能です。こうした柔軟な働き方ができることで、職場への愛着や働きがいの向上も期待できます。
業務効率が向上する
フレックスタイム制により、従業員が自分にとって最も集中できる時間帯に仕事ができるようになるため、業務の効率が上がることが期待できます。朝型・夜型といった個人の特性にあわせて働けることで、それぞれの力を最大限に発揮できます。通勤ラッシュを避けられることで体力的な負担が軽減される点も、業務効率の向上につながるでしょう。
人材確保につながる
フレックスタイム制の導入は、柔軟な働き方を希望する人材の関心を集めやすく、採用活動における強みとなります。特に育児や介護があるなど、時間に制約のある求職者にとっては勤務時間を調整できることが大きな魅力となるでしょう。
また、働きやすい職場環境が整うことで既存従業員の定着率も向上し、離職の防止にもつながります。結果として、採用コストの削減や人材の安定確保といった効果が期待できます。
フレックスタイム制のデメリット
フレックスタイム制には、主に以下のようなデメリットがあります。
- 労働時間の管理が煩雑化する
- チーム内の連携が難しくなる
- 顧客対応に支障が出る可能性がある
それぞれのデメリットについて解説します。
労働時間の管理が煩雑化する
フレックスタイム制では、従業員ごとの出退勤時間が異なるため、勤怠管理が複雑になりやすいです。清算期間内の総労働時間を正確に把握する必要があり、残業や有給休暇の管理もより細やかな対応が求められます。
月単位や3カ月単位で清算する場合、それぞれの勤務状況をふまえて時間外労働の集計や調整を行う必要があるため、人事・労務担当者の負担が大きくなることもあります。フレックスタイム制の運用にあたっては、勤怠管理システムの導入や計算ルールの整理など、事前の準備が大切です。
チーム内の連携が難しくなる
フレックスタイム制を取り入れると、社員の勤務時間がそれぞれ異なるため、全員がそろう時間が限られてしまうことがあります。その結果、会議の時間調整が難しくなったり、情報共有が遅れたりする可能性があります。
例えば、朝型勤務の社員と夕方に出社する社員が同じプロジェクトに関わる場合、やりとりが1日遅れることも考えられるでしょう。
コミュニケーションのタイムロスを防ぐには、チャットツールや共有シートの活用、会議の録画・議事録の共有など、時間を問わず情報を確認できる仕組みづくりが大切です。
顧客対応に支障が出る可能性がある
フレックスタイム制では、従業員が勤務時間を柔軟に調整できる一方で、顧客対応とのタイミングが合わなくなることがあります。特に取引先の営業時間が決まっている場合、その時間帯に担当者が勤務していなければ、対応が遅れてしまう可能性があります。
例えば、担当者が午後から出勤する勤務形態では、午前中に寄せられた急ぎの問い合わせにすぐ対応できないこともあるでしょう。
こうしたトラブルを防ぐためには、フレックスタイム制を導入する際に、部署ごとの業務内容をふまえて、対応時間の分担や当番制などの体制を整えておくことが大切です。
フレックスタイム制の導入に必要な手続き
フレックスタイム制の導入に必要な手続きは以下のとおりです。
- 就業規則への規定
- 労使協定の締結
- 従業員への周知と運用開始
就業規則や労使協定で明記すべき内容も合わせて解説します。
就業規則への規定
フレックスタイム制を導入する場合は、就業規則にて制度導入の原則を記載する必要があります。
具体的には「始業および終業の時刻は、労働者が自ら決めることができる」と就業規則に明記しておく必要があります。コアタイム・フレキシブルタイムを設けるかどうかに関わらず、必ず明記しておくべき項目です。
労使協定の締結
フレックスタイム制を導入するには、会社と労働者代表との間で労使協定を締結する必要があります。労使協定では、以下の項目を明記する必要があります。
- 対象となる労働者の範囲
- 清算期間と起算日
- 清算期間における総労働時間
- 標準となる1日の労働時間
- コアタイム・フレキシブルタイムを設ける場合の開始・終了時刻
特に、清算期間が1カ月を超える場合は、所轄の労働基準監督署への届出も必要です。協定は制度運用の土台となるため、労使でしっかりと話し合い、お互いが納得できる内容にしておくことが大切です。
労使協定に記載すべき項目とそれぞれの内容について解説します。
対象となる労働者の範囲
フレックスタイム制を適用する際は、対象となる従業員の範囲をあらかじめ明確に定めておく必要があります。
例えば、「全社員を対象とする」「営業部所属の従業員を対象とする」といった形で記載しましょう。
また、誰が制度を利用できるかを周知することで、社内での混乱や不公平感を防ぐことにもつながります。
清算期間と起算日
清算期間と起算日は、労働時間の集計や残業管理の基準となるため、労使協定でしっかりと定めておく必要があります。清算期間とは、従業員が労働すべき時間を決める期間のことです。当初の上限は1カ月でしたが、2019年の法改正により上限は3カ月に変更されました。
起算日は企業が任意で設定でき、いつからいつまでが清算期間になるのかを明確にしておく必要があります。
なお、清算期間が1カ月を超える場合は、労使協定を労働基準監督署へ届出る必要があります。
清算期間における総労働時間
清算期間における総労働時間とは、フレックスタイム制の所定労働時間のことです。清算期間を平均した1週間の所定労働時間が40時間を超えないように設定しなければいけません。
なお、清算期間における総労働時間は、法定労働時間の総枠内に収める必要があります。
| 暦日数 | 法定労働時間の総枠内 |
|---|---|
| 28日 | 160.0時間 |
| 29日 | 165.7時間 |
| 30日 | 171.4時間 |
| 31日 | 177.1時間 |
標準となる1日の労働時間
有給休暇を取得する際に、何時間労働したものとして給与を計算するのか明確にするために標準となる1日の労働時間を就業規則に明記しましょう。一般的にはフレックスタイム制導入時点の1日の所定労働時間数で設定することが多いです。
コアタイム・フレキシブルタイムを設ける場合の開始・終了時刻
就業規則と同様に、コアタイム・フレキシブルタイムを設ける場合はそれぞれの開始・終了時刻を労使協定で明記する必要があります。
なお、コアタイムは労使協定で自由に設定が可能です。日によってコアタイムの時間設定を変更したり、分割したりして設定することもできます。
従業員への周知と運用開始
フレックスタイム制をスムーズに導入するには、制度の内容を丁寧に周知し、段階的に運用を進めることが大切です。
導入前には、社内説明会を開き、制度の概要や勤務時間の考え方、残業代の取り扱いについてわかりやすく説明しましょう。あわせて、よくある質問をまとめたQ&Aの配布や、個別相談の窓口を設けておくと、従業員の不安や疑問にもきめ細かく対応できます。
実際の運用を始める前には、1〜2カ月の試行期間を設けるのがおすすめです。運用状況を見ながらルールの見直しを行うことで、制度が職場によりなじみやすくなります。あらかじめ勤怠管理システムの動作確認をしておくことや、勤怠ルールを再確認することも、スムーズな定着には欠かせません。
フレックスタイム制を導入する際の注意点
フレックスタイム制を導入する際の注意点には以下の点に注意しましょう。
- 清算期間と総労働時間を把握する
- 時間外労働の上限規制の適用
- 残業代の計算を正しく行う
- 遅刻・早退・欠勤を適切に取り扱う
- 休憩時間のルール設定をしておく
それぞれの注意点を理解し、正しく運用しましょう。
清算期間と総労働時間を把握する
フレックスタイム制を適切に運用するためには、清算期間内の総労働時間を正確に把握することが重要です。
例えば、清算期間が1カ月で、暦日数が30日の月であれば、法定労働時間の上限は「30日 ÷ 7日 × 40時間」で約171.4時間です。このように、上限時間は月ごとの暦日数によって変動します。
総労働時間が法定労働時間の上限を超えた場合には、時間外労働として取り扱われます。そのため、事前に基準時間を従業員に共有し、勤怠管理システムで自動計算できる仕組みを整えておくと安心です。
また、働きすぎや労働時間の不足に気づけるように、管理側も週単位や中間時点での労働状況を確認するなど、定期的なチェックを行うことも大切です。
時間外労働の上限規制の適用
フレックスタイム制であっても、時間外労働には上限があり、36協定で定めた範囲内で運用する必要があります。例えば、月45時間・年360時間という上限を超えて労働させる場合には、特別条項付きの36協定を結ぶことが求められます。
なお、36協定に特別条項を設けている場合でも、以下の条件を守らなければなりません。
- 時間外労働が年720時間以内
- 時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満
- 時間外労働と休⽇労働の合計について、2カ月〜6カ月までの平均が全て1⽉当たり80時間以内
- 時間外労働が月45時間を超えるのは年6回まで
また、清算期間内の労働時間に偏りがあると、本人や管理者が気づかないうちに時間外労働の上限を超えてしまうケースもあります。こうした事態を防ぐためには、勤怠管理システムなどを活用し、日々の労働時間をこまめに確認することが大切です。
残業代の計算を正しく行う
フレックスタイム制では、清算期間全体で総労働時間が法定労働時間の上限を超えた場合に、その超過分を残業時間として扱います。日ごとの労働時間ではなく、期間を通じた合計時間で判断する点が、通常の勤務制度との大きな違いです。
例えば暦日数が30日あれば171.4時間が法定労働時間となり、それを上回った労働時間に対して残業代が発生します。また、深夜(22時〜翌5時)や法定休日の労働については、別途割増賃金の支払いが必要です。
さらに、清算期間が1カ月を超える場合には、各月ごとに週平均50時間を超えた時間についても割増の対象となります。
遅刻・早退・欠勤を適切に取り扱う
フレックスタイム制では、始業・終業時刻を従業員が柔軟に決められるため、通常勤務の遅刻や早退とは考え方が異なります。清算期間内の総労働時間内を満たしていれば、遅刻・早退・欠勤扱いとはなりません。
ただし、コアタイムを設けている場合、その時間内に勤務していなければ遅刻・早退と見なされるため、ルールを明確にしておくことが大切です。
例えば、コアタイムが10時〜15時であれば、10時30分の出社は30分の遅刻と判断されます。フレキシブルタイムでは、遅刻や早退は発生しません。
また、コアタイムを設定していて欠勤した場合は、皆勤手当を支給しない・賞与を減給するといった取り扱いを設けることも可能です。
休憩時間のルール設定をしておく
フレックスタイム制を導入する場合でも、労働基準法に定められた休憩時間の取り扱いは従来どおり適用されます。具体的には、1日の労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を取る必要があります。
一斉休憩の原則が適用される業種の場合は、コアタイム中に休憩時間を設ける必要があります。反対に適用されない業種の場合は、休憩時間をいつ取るかに関して従業員の判断に委ねられます。この場合は、休憩時間の長さを就業規則に明記します。
なお、一斉休憩の原則が適用される業種で、コアタイムを設けていない場合は、一斉付与の原則を適用除外にするという労使協定を締結する必要があります。
参考文献
厚生労働省「フレックスタイム制のわかりやすい解説 & 導入の手引き」
監修